第四十一帖 幻 |
41 MABOROSI (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 五十二歳春から十二月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to December, at the age of 52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 第三章 光る源氏の物語 紫の上追悼の秋冬の物語 |
3 Tale of Genji Mourning for Murasaki, from fall to the year-end |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | 第一段 紫の上の一周忌法要 |
3-1 The first anniversary of Murasaki's death |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | 七月七日も、例に変りたること多く、御遊びなどもしたまはで、つれづれに眺め暮らしたまひて、 星逢ひ見る人もなし。まだ夜深う、一所起きたまひて、妻戸押し開けたまへるに、 前栽の露いとしげく、渡殿の戸より とほりて見わたさるれば、出でたまひて、 |
七月七日も、いつもと変わったことが多く、管弦のお遊びなどもなさらず、何もせずに一日中物思いに耽ってお過ごしになって、星合の空を見る人もいない。まだ夜は深く、独りお起きになって、妻戸を押し開けなさると、前栽の露がとてもびっしょりと置いて、渡殿の戸から通して見渡されるので、お出になって、 |
七月七日も例年に変わった |
Sitigwatu nanuka mo, rei ni kahari taru koto ohoku, ohom-asobi nado mo si tamaha de, turedureni nagame kurasi tamahi te, hosiahi miru hito mo nasi. Mada yobukau, hitotokoro oki tamahi te, tumado osiake tamahe ru ni, sensai no tuyu ito sigeku, watadono no to yori tohori te miwatasa rure ba, ide tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | 「 七夕の逢ふ瀬は雲のよそに見て 別れの庭に露ぞおきそふ」 |
「七夕の逢瀬は雲の上の別世界のことと見て その後朝の別れの庭の露に悲しみの涙を添えることよ」 |
七夕の 別れの庭の露ぞ置き添ふ |
"Tanabata no ahuse ha kumo no yoso ni mi te wakare no niha ni tuyu zo oki sohu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.3 | 風の音さへただならずなりゆくころしも、御法事の営みにて、 ついたちころは紛らはしげなり。「 今まで経にける月日よ」と思す ★にも、あきれて明かし暮らしたまふ。 |
風の音までがたまらないものになってゆくころ、御法事の準備で、上旬ころは気が紛れるようである。「今まで生きて来た月日よ」とお思いになるにつけても、あきれる思いで暮らしていらっしゃる。 |
こう口ずさんでおいでになった。秋風らしい風の吹き始めるころからは法事の |
Kaze no oto sahe tada nara zu nari yuku koro simo, ohom-hohuzi no itonami nite, tuitati koro ha magirahasige nari. "Ima made he ni keru tukihi yo!" to obosu ni mo, akire te akasi kurasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.4 | 御正日には、上下の人びと皆斎して、かの曼陀羅など、今日ぞ 供養ぜさせたまふ。例の宵の御行ひに、 御手水など参らする中将の君の扇に、 |
御命日には、上下の人びとがみな精進して、あの曼陀羅などを、今日ご供養あそばす。いつもの宵のご勤行に、御手水を差し上げる中将の君の扇に、 |
命日である十四日には上から下まで六条院の中の人々は精進潔斎して、 |
Ohom-syauniti ni ha, kami simo no hitobito mina imohi si te, kano mandara nado, kehu zo kuyauze sase tamahu. Rei no yohi no ohom-okonahi ni, mi-teudu nado mawira suru Tyuuzyau-no-Kimi no ahugi ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.5 | 「 君恋ふる涙は際もなきものを 今日をば何の果てといふらむ」 |
「ご主人様を慕う涙は際限もないものですが 今日は何の果ての日と言うのでしょう」 |
君恋ふる涙ははてもなきものを 今日をば何のはてといふらん |
"Kimi kohuru namida ha kiha mo naki mono wo kehu wo ba nani no hate to ihu ram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.6 | と書きつけたるを、取りて見たまひて、 |
と書きつけてあるのを、手に取って御覧になって、 |
と書かれてあったのを、手に取ってお読みになってから、院がまたその横へ、 |
to kakituke taru wo, tori te mi tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.7 | 「 人恋ふるわが身も末になりゆけど 残り多かる涙なりけり」 |
「人を恋い慕うわが余命も少なくなったが 残り多い涙であることよ」 |
人恋ふるわが身も末になりゆけど 残り多かる涙なりけり |
"Hito kohuru waga mi mo suwe ni nariyuke do nokori ohokaru namida nari keri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.8 | と、書き添へたまふ。 |
と、書き加えなさる。 |
とお書き添えになった。 |
to, kaki sohe tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.9 | 九月になりて、九日、綿おほひたる菊を御覧じて、 |
九月になって、九日、綿被いした菊を御覧になって、 |
九月になり |
Kugwatu ni nari te, kokonuka, wata ohohi taru kiku wo goranzi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.10 | 「 もろともにおきゐし菊の白露も 一人袂にかかる秋かな」 |
「一緒に起きて置いた菊のきせ綿の朝露も 今年の秋はわたし独りの袂にかかることだ」 |
もろともにおきゐし菊の朝露も ひとり |
"Morotomoni oki wi si kiku no siratuyu mo hitori tamoto ni kakaru aki kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.11 | と院はお歌いになった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 第二段 源氏、出家を決意 |
3-2 Genji decides to go into religion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.1 | 神無月には、おほかたも時雨がちなるころ、いとど眺めたまひて、 夕暮の空のけしきも、えもいはぬ心細さに、「 ▼ 降りしかど」と ★独りごちおはす。 雲居を渡る雁の翼も、うらやましくまぼられたまふ。 |
神無月には、一般に時雨がちなころとて、ますます物思いに沈みなさって、夕暮の空の様子にも、何ともいえない心細さゆえ、「いつも時雨は降ったが」と独り口ずさんでいらっしゃる。雲居を渡ってゆく雁の翼も、羨ましく見つめられなさる。 |
十月は |
Kamnaduki ni ha, ohokata mo siguregati naru koro, itodo nagame tamahi te, yuhugure no sora no kesiki mo, e mo iha nu kokorobososa ni, "Huri sika do" to hitorigoti ohasu. Kumowi wo wataru kari no tubasa mo, urayamasiku mabora re tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
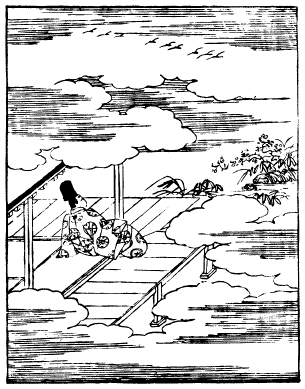 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 | 「 大空をかよふ幻夢にだに 見えこぬ魂の行方たづねよ」 |
「大空を飛びゆく幻術士よ、夢の中にさえ 現れない亡き人の魂の行く方を探してくれ」 |
大空を通ふまぼろし夢にだに 見えこぬ |
"Ohozora wo kayohu maborosi yume ni dani miye ko nu tama no yukuhe tadune yo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.3 | 何ごとにつけても、紛れずのみ、月日に添へて思さる。 |
どのような事につけても、気の紛れることのないばかりで、月日につれて悲しく思わずにはいらっしゃれない。 |
何によっても慰められぬ月日がたっていくにしたがい、院のお悲しみは深くばかりになった。 |
Nanigoto ni tuke te mo, magire zu nomi, tukihi ni sohe te obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.4 | 五節などいひて、世の中そこはかとなく今めかしげなるころ、大将殿の君たち、 童殿上したまへる率て参りたまへり。同じほどにて、二人いとうつくしきさまなり。 御叔父の頭中将、蔵人少将など、 小忌にて、青摺の姿ども ★、きよげにめやすくて、皆うち続き、もてかしづきつつ、もろともに参りたまふ。思ふことなげなるさまどもを見たまふに、 いにしへ、あやしかりし日蔭の折、さすがに思し出でらるべし。 |
五節などといって、世の中がどことなくはなやかに浮き立っているころ、大将殿のご子息たち、童殿上なさって参上なさった。同じくらいの年齢で、二人とてもかわいらしい姿である。御叔父の頭中将や、蔵人少将などは、小忌衣で、青摺の姿がさっぱりして感じよくて、みな引き続いて、お世話しながら一緒に参上なさる。何の物思いもなさそうな様子を御覧になると、昔、心ときめくことのあった五節の折、何といってもお思い出されるであろう。 |
|
Goseti nado ihi te, yononaka sokohakatonaku imamekasige naru koro, Daisyau-dono no Kimi-tati, warahatenzyau si tamahe ru wi te mawiri tamahe ri. Onazi hodo nite, hutari ito utukusiki sama nari. Ohom-wodi no Tou-no-Tyuuzyau, Kuraudo-no-Seusyau nado, womi nite, awozuri no sugata-domo, kiyoge ni meyasuku te, mina uti-tuduki, mote kasiduki tutu, morotomoni mawiri tamahu. Omohu koto nage naru sama-domo wo mi tamahu ni, inisihe, ayasikari si hikage no wori, sasugani obosi ide raru besi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.5 | 「 宮人は豊明といそぐ今日 日影も知らで暮らしつるかな」 |
「宮人が豊明の節会に夢中になっている今日 わたしは日の光も知らないで暮らしてしまったな」 |
宮人は 日かげも知らで暮らしつるかな |
"Miyabito ha Toyonoakari to isogu kehu hikage mo sira de kurasi turu kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.6 | 「 今年をばかくて忍び過ぐしつれば、今は」と、世を去りたまふべきほど近く思しまうくるに、あはれなること、尽きせず。やうやうさるべきことども、御心のうちに思し続けて、さぶらふ人びとにも、ほどほどにつけて、物賜ひなど、おどろおどろしく、今なむ限りとしなしたまはねど、近くさぶらふ人びとは、御本意遂げたまふべきけしきと見たてまつるままに、年の暮れゆくも心細く、悲しきこと限りなし。 |
「今年をこうしてひっそりと過ごして来たので、これまで」と、ご出家なさるべき時を近々にご予定なさるにつけ、しみじみとした悲しみ、尽きない。だんだんとしかるべき事柄を、ご心中にお思い続けなさって、伺候する女房たちにも、身分身分に応じて、お形見分けなど、大げさに、これを最後とはなさらないが、近く伺候する女房たちは、ご出家の本願をお遂げになる様子だと拝見するにつれて、年が暮れてゆくのも心細く、悲しい気持ちは限りがない。 |
今年をこんなふうに隠忍してお通しになった院は、もう次の春になれば出家を実現させてよいわけであるとその用意を少しずつ始めようとされるのであったが、物哀れなお気持ちばかりがされた。院内の人々にもそれぞれ等差をつけて物を与えておいでになるのであった。目だつほどに今日までの御生活に区切りをつけるようなことにはしてお見せにならないのであるが、近くお仕えする人たちには、院が出家の実行を期しておいでになることがうかがえて、今年の終わってしまうことを非常に心細くだれも思った。 |
"Kotosi wo ba kaku te sinobi sugusi ture ba, ima ha." to, yo wo sari tamahu beki hodo tikaku obosi maukuru ni, ahare naru koto, tuki se zu. Yauyau sarubeki koto-domo, mi-kokoro no uti ni obosi tuduke te, saburahu hitobito ni mo, hodohodo ni tuke te, mono tamahi nado, odoroodorosiku, ima nam kagiri to si nasi tamaha ne do, tikaku saburahu hitobito ha, ohom-hoi toge tamahu beki kesiki to mi tatematuru mama ni, tosi no kure yuku mo kokorobosoku, kanasiki koto kagiri nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 第三段 源氏、手紙を焼く |
3-3 Genji makes to burn letters up by maids |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 | 落ちとまりて かたはなるべき人の御文ども、破れば惜し、と ★思されけるにや、すこしづつ残したまへりけるを、もののついでに御覧じつけて、破らせたまひなどするに、かの須磨のころほひ、所々より たてまつれたまひけるもある中に、 かの御手なるは、ことに結ひ合はせてぞありける。 |
後に残っては見苦しいような女の人からのお手紙は、破っては惜しい、とお思いになってか、少しずつ残していらっしゃったのを、何かの機会に御覧になって、破り捨てさせなさるなどすると、あの須磨にいたころ、あちらこちらから差し上げさせなさったものもある中で、あの方のご筆跡の手紙は、特別に一つに結んであったのであった。 |
人の目については不都合であるとお思いになった古い恋愛関係の手紙類をなお破るのは惜しい気があそばされたのか、だれのも少しずつ残してお置きになったのを、何かの時にお見つけになり破らせなどして、また改めて始末をしにおかかりになったのであるが、 |
Oti tomari te kataha naru beki hito no ohom-humi-domo, yare ba wosi, to obosa re keru ni ya, sukosi dutu nokosi tamahe ri keru wo, mono no tuide ni goranzi tuke te, yara se tamahi nado suru ni, kano Suma no korohohi, tokorodokoro yori tatemature tamahi keru mo aru naka ni, kano ohom-te naru ha, kotoni yuhi ahase te zo ari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 | みづからしおきたまひけることなれど、「 久しうなりける世のこと」と思すに、ただ今のやうなる墨つきなど、「げに 千年の形見にしつべかりけるを ★、 見ずなりぬべきよ」と思せば、かひなくて、疎からぬ人びと、二、三人ばかり、御前にて破らせたまふ。 |
ご自身でなさっておいたことだが、「遠い昔のことになった」とお思いになるが、たった今書いたような墨跡などが、「なるほど千年の形見にできそうだが、見ることもなくなってしまうものよ」とお思いになると、何にもならないので、気心の知れた女房、二、三人ほどに、御前で破らせなさる。 |
御自身がしてお置きになったのであるが、古い昔のことであったと前の世のことのようにお思われになりながらも、中をあけてお読みになると、今書かれたもののように、夫人の墨の跡が生き生きとしていた。これは永久に形見として見るによいものであると |
Midukara si oki tamahi keru koto nare do, "Hisasiu nari keru yo no koto" to obosu ni, tada ima no yau naru sumituki nado, "Geni titose no katami ni si tu bekari keru wo, mi zu nari nu beki yo." to obose ba, kahinaku te, utokara nu hitobito, ni, sam-nin bakari, omahe nite yara se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.3 | いと、かからぬほどのことにてだに、過ぎにし人の跡と見るはあはれなるを、ましていとどかきくらし、それとも見分かれぬまで、降りおつる 御涙の水茎に流れ添ふを、人もあまり心弱しと見たてまつるべきが、かたはらいたうはしたなければ、押しやりたまひて、 |
ほんとうに、このようなことでなくさえ、亡くなった人の筆跡と思うと胸が痛くなるのに、ましてますます涙にくれて、どれがどれとも見分けられないほど、流れ出るお涙の跡が文字の上を流れるのを、女房もあまりに意気地がないと拝見するにちがいないのが、見ていられなく体裁悪いので、手紙を押しやりなさって、 |
こんな場合でなくても、 |
Ito, kakara nu hodo no koto nite dani, sugi ni si hito no ato to miru ha ahare naru wo, masite itodo kaki-kurasi, sore to mo mi wakare nu made, huri oturu ohom-namida no miduguki ni nagare sohu wo, hito mo amari kokoroyowasi to mi tatematuru beki ga, kataharaitau hasitanakere ba, osiyari tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.4 | 「 死出の山越えにし人を慕ふとて 跡を見つつもなほ惑ふかな」 |
「死出の山を越えてしまった人を恋い慕って行こうとして その跡を見ながらもやはり悲しみにくれまどうことだ」 |
死出の山越えにし人を慕ふとて 跡を見つつもなほまどふかな |
"Side-no-yama koye ni si hito wo sitahu tote ato wo mi tutu mo naho madohu kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.5 | さぶらふ人びとも、まほにはえ引き広げねど、それとほのぼの見ゆるに、心惑ひどもおろかならず。この世ながら遠からぬ御別れのほどを、いみじと思しけるままに書いたまへる言の葉、げにその折よりもせきあへぬ悲しさ、やらむかたなし。いとうたて、今ひときはの御心惑ひも、女々しく人悪るくなりぬべければ、よくも見たまはで、こまやかに書きたまへるかたはらに、 |
伺候する女房たちも、まともには広げられないが、その筆跡とわずかに分かるので、心動かされることも並々でない。この世にありながらそう遠くでなかったお別れの間中を、ひどく悲しいとお思いのままお書きになった和歌、なるほどその時よりも堪えがたい悲しみは、慰めようもない。まことに情けなく、もう一段とお心まどいも、女々しく体裁悪くなってしまいそうなので、よくも御覧にならず、心をこめてお書きになっている側に、 |
と仰せられた。女房たちも御遠慮がされてくわしく読むことはできないのであったが、端々の文字の少しずつわかっていくだけさえも非常に悲しかった。同じ世にいて、近い所に別れ別れになっている悲しみを、実感のままに書かれてある故人の文章が、その当時以上に今のお心を打つのは道理なことである。こんなにめめしく悲しんで自分は見苦しいとお思いになって、よくもお読みにならないで長く書かれた女王の手紙の横に、 |
Saburahu hitobito mo, maho ni ha e hiki hiroge ne do, sore to honobono miyuru ni, kokoromadohi-domo oroka nara zu. Konoyo nagara tohokara nu ohom-wakare no hodo wo, imizi to obosi keru mama ni kai tamahe ru kotonoha, geni sono wori yori mo seki ahe nu kanasisa, yara m kata nasi. Ito utate, ima hitokiha no mi-kokoromadohi mo, memesiku hitowaruku nari nu bekere ba, yoku mo mi tamaha de, komayakani kaki tamahe ru katahara ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.6 | 「 かきつめて見るもかひなし藻塩草 同じ雲居の煙とをなれ」 |
「かき集めて見るのも甲斐がない、この手紙も 本人と同じく雲居の煙となりなさい」 |
かきつめて見るもかひなし 同じ雲井の煙とをなれ |
"Kaki-tume te miru mo kahi nasi mosihogusa onazi kumowi no keburi to wo nare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.7 | と書きつけて、 皆焼かせたまふ。 |
と書きつけて、みなお焼かせになる。 |
とお書きになって、それも皆焼かせておしまいになった。 |
to kakituke te, mina yaka se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 第四段 源氏、出家の準備 |
3-4 Genji prepares to go into religion |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.1 | 「 御仏名も、今年ばかりにこそは」と 思せばにや、常よりもことに、錫杖の声々などあはれに思さる。行く末ながきことを請ひ願ふも、仏の聞きたまはむこと、 かたはらいたし。 |
「御仏名も、今年限りだ」とお思いになればであろうか、例年よりも格別に、錫杖の声々などがしみじみと思われなさる。行く末長い将来を請い願うのも、仏が何とお聞きになろうかと、耳が痛い。 |
仏名の僧を迎える行事も今年きりのことであるとお思いになると、僧の |
"Ohom-butumyau mo, kotosi bakari ni koso ha." to obose ba ni ya, tune yori mo koto ni, syakuzyau no kowe gowe nado ahareni obosa ru. Yukusuwe nagaki koto wo kohi negahu mo, Hotoke no kiki tamaha m koto, kataharaitasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.2 | 雪いたう降りて、まめやかに積もりにけり。導師のまかづるを、御前に召して、盃など、常の作法よりもさし分かせたまひて、ことに禄など賜はす。年ごろ久しく参り、朝廷にも仕うまつりて、御覧じ馴れたる御導師の、 頭はやうやう色変はりてさぶらふも、あはれに思さる。例の、宮たち、上達部など、あまた参りたまへり。 |
雪がたいそう降って、たくさん積もった。導師が退出するのを、御前にお召しになって、盃など、平常の作法よりも格別になさって、特に禄などを下賜なさる。長年久しく参上し、朝廷にもお仕えして、よくご存知になられている御導師が、頭はだんだん白髪に変わって伺候しているのも、しみじみとお思われなさる。いつもの、親王たち、上達部などが、大勢参上なさった。 |
雪が大降りになって厚く積もった。帰ろうとする導師を院は御前へお呼びになって、杯を賜わったりすることなども普通の仏名式の日以上の手厚いおねぎらいであった。 |
Yuki itau huri te, mameyakani tumori ni keri. Dausi no makaduru wo, o-mahe ni mesi te, sakaduki nado, tune no sahohu yori mo sasi-waka se tamahi te, kotoni roku nado tamahasu. Tosigoro hisasiku mawiri, Ohoyake ni mo tukaumaturi te, goranzi nare taru ohom-Dausi no, kasira ha yauyau iro kahari te saburahu mo, ahareni obosa ru. Rei no, Miya-tati, Kamdatime nado, amata mawiri tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.3 | 梅の花の、わづかにけしきばみはじめて雪にもてはやされたるほど、をかしきを、御遊びなどもありぬべけれど、なほ今年までは、ものの音もむせびぬべき心地したまへば、時によりたるもの、うち誦じなどばかりぞせさせたまふ。 |
梅の花が、わずかにほころびはじめて雪に引き立てられているのが、美しいので、音楽のお遊びなどもあるはずなのだが、やはり今年までは、楽の音にもむせび泣きしてしまいそうな気がなさるので、折に合うものを、口ずさむ程度におさせなさる。 |
梅の花の少し花らしく顔を上げ出したのが、雪の中にきわだって美しく見える日であったから、音楽の遊びもあってしかるべきなのであるが、本年中はなお |
Mume no hana no, wadukani kesikibami hazime te yuki ni motehayasa re taru hodo, wokasiki wo, ohom-asobi nado mo ari nu bekere do, naho kotosi made ha, mono no ne mo musebi nu beki kokoti si tamahe ba, toki ni yori taru mono, uti-zunzi nado bakari zo se sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.4 | まことや、導師の盃のついでに、 |
そう言えば、導師にお盃を賜る時に、 |
導師へ院が杯をおさしになった時のお歌は、 |
Makoto ya, Dausi no sakaduki no tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.5 | 「 春までの命も知らず雪のうちに 色づく梅を今日かざしてむ」 |
「春までの命もあるかどうか分からないから 雪の中に色づいた紅梅を今日は插頭にしよう」 |
春までの命も知らず雪のうちに 色づく梅を今日かざしてん |
"Haru made no inoti mo sira zu yuki no uti ni iroduku mume wo kehu kazasi te m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.6 | 御返し、 |
お返事は、 |
というのであって、お返し、 |
Ohom-kahesi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.7 | 「 千世の春見るべき花と祈りおきて わが身ぞ雪とともにふりぬる」 |
「千代の春を見るべくあなたの長寿を祈りおきましたが わが身は降る雪とともに年ふりました」 |
千代の春見るべきものと祈りおきて わが身ぞ雪とともにふりぬる |
"Tiyo no haru miru beki hana to inori oki te waga mi zo yuki to tomoni huri nuru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.8 | 人びと多く詠みおきたれど、もらしつ。 |
人々も数多く詠みおいたが、省略した。 |
参会者の作も多かったが省いておく。 |
Hitobito ohoku yomi oki tare do, morasi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.9 | その日ぞ、出でたまへる。御容貌、昔の御光にもまた多く添ひて、ありがたくめでたく見えたまふを、この古りぬる齢の僧は、あいなう涙もとどめざりけり。 |
この日、初めて人前にお出になった。ご器量、昔のご威光にもまた一段と増して、素晴らしく見事にお見えになるのを、この年とった老齢の僧は、無性に涙を抑えられないのであった。 |
院の御 |
Sono hi zo, ide tamahe ru. Ohom-katati, mukasi no ohom-hikari ni mo mata ohoku sohi te, arigataku medetaku miye tamahu wo, kono huri nuru yohahi no sou ha, ainau namida mo todome zari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.10 | 年暮れぬと思すも、心細きに、 若宮の、 |
年が暮れてしまったとお思いになるにつけ、心細いので、若宮が、 |
今年が終わることを心細く思召す院であったから、若宮が、 |
Tosi kure nu to obosu mo, kokorobosoki ni, WakaMiya no, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.11 | 「 儺やらはむに、音高かるべきこと、何わざをせさせむ」 |
「追儺をするのに、高い音を立てるには、どうしたらよいでしょう」 |
「 |
"Na yaraha m ni, oto takakaru beki koto, nani waza wo se sase m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.12 | と、走りありきたまふも、「をかしき御ありさまを見ざらむこと」と、よろづに忍びがたし。 |
と言って、走り回っていらっしゃるのも、「かわいいご様子を見なくなることだ」と、何につけ堪えがたい。 |
などと言って、お走り歩きになるのを御覧になっても、このかわいい人も見られぬ生活にはいるのであるとお思いになるのがお寂しかった。 |
to, hasiri ariki tamahu mo, "Wokasiki ohom-arisama wo mi zara m koto." to, yoroduni sinobi gatasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.13 | 「 ▼ もの思ふと過ぐる月日も知らぬまに 年もわが世も今日や尽きぬる」 |
「物思いしながら過ごし月日のたつのも知らない間に 今年も自分の寿命も今日が最後になったか」 |
物 年もわが世も今日や尽きぬる |
"Mono omohu to suguru tukihi mo sira nu ma ni tosi mo waga yo mo kehu ya tuki nuru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4.14 | 朔日のほどのこと、「常よりことなるべく」と、おきてさせたまふ。親王たち、大臣の御引出物、品々の禄どもなど、 何となう思しまうけて、とぞ。 |
元日の日のことを、「例年より格別に」と、お命じあそばす。親王方、大臣への御引出物や、人々への禄などを、またとなくご用意なさって、とあった。 |
元日の参賀の客のためにことにはなやかな |
Tuitati no hodo no koto, "Tune yori kotonaru beku." to, oki te sase tamahu. Miko-tati, Otodo no hikiidemono, sina zina no roku-domo nado, nanitonau obosi mauke te, to zo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/22/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 8/16/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 2/12/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 8/16/2010 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 3.38: Copyright (c) 2003,2015 宮脇文経