第十四帖 澪標 |
14 MIWOTUKUSI (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の二十八歳初冬十月から二十九歳冬まで内大臣時代の物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from October at the age of 28 to in winter at the age of 29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 第四章 明石の物語 住吉浜の邂逅 |
4 Tale of Akashi Chance meeting again in Sumiyoshi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | 第一段 住吉詣で |
4-1 Genji visits to Sumiyoshi-shrine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | その秋、住吉に詣でたまふ。願ども果たしたまふべければ、いかめしき御ありきにて、世の中ゆすりて、上達部、殿上人、我も我もと仕うまつりたまふ。 |
その年の秋に、住吉にご参詣になる。願ほどきなどをなさるご予定なので、盛大なご行列で、世間でも大騷ぎして、上達部、殿上人らが、我も我もとお供申し上げになさる。 |
この秋に源氏は |
Sono aki, Sumiyosi ni maude tamahu. Gwan-domo hatasi tamahu bekere ba, ikamesiki ohom-ariki nite, yononaka yusuri te, Kamdatime, Tenzyaubito, ware mo ware mo to tukaumaturi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | 折しも、かの明石の人、年ごとの例のことにて詣づるを、去年今年は障ることありて、おこたりける、かしこまり取り重ねて、思ひ立ちけり。 |
ちょうどその折、あの明石の人は、毎年恒例にして参詣するのが、去年今年は差し障りがあって、参詣できなかった、そのお詫びも兼ねて思い立ったのであった。 |
ちょうどこの日であった、明石の君が毎年の例で |
Worisimo, kano Akasi-no-Hito, tosigoto no rei no koto nite mauduru wo, kozo kotosi ha saharu koto ari te, okotari keru, kasikomari tori-kasane te, omohitati keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3 | 舟にて詣でたり。岸にさし着くるほど、見れば、ののしりて詣でたまふ 人のけはひ ★、渚に満ちて、 いつくしき神宝を持て続けたり。楽人、 十列など、装束をととのへ、容貌を選びたり。 |
舟で参詣した。岸に着ける時、見ると、大騷ぎして参詣なさる人々の様子、渚にいっぱいあふれていて、尊い奉納品を列をなさせていた。楽人、十人ほど、衣装を整え、顔形の良い者を選んでいた。 |
船で住吉へ来た。海岸のほうへ寄って行くと華美な参詣の行列が寄進する神宝を運び続けて来るのが見えた。楽人、 |
Hune nite maude tari. Kisi ni sasi-tukuru hodo, mire ba, nonosiri te maude tamahu hito no kehahi, nagisa ni miti te, itukusiki kamdakara wo mote-tuduke tari. Gakunin, towotura nado, sauzoku wo totonohe, katati wo erabi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.4 | 「 誰が詣でたまへるぞ」 |
「どなたが参詣なさるのですか」 |
「どなたの御参詣なのですか」 |
"Taga maude tamahe ru zo?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.5 | と 問ふめれば、 |
と尋ねたらしいので、 |
と船の者が陸へ聞くと、 |
to tohu mere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.6 | 「 内大臣殿の御願果たしに詣でたまふを、知らぬ人もありけり」 |
「内大臣殿が、御願ほどきに参詣なさるのを、知らない人もいたのだなあ」 |
「おや、内大臣様の |
"Naidaizindono no ohom-gwanhatasi ni maude tamahu wo, sira nu hito mo ari keri!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.7 | とて、 はかなきほどの下衆だに、心地よげにうち笑ふ。 |
と言って、とるにたりない身分の低い者までもが、気持ちよさそうに笑う。 |
|
tote, hakanaki hodo no gesu dani, kokotiyoge ni uti-warahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.8 | 「 げに、あさましう、月日もこそあれ。 なかなか、この御ありさまを遥かに見るも、身のほど口惜しうおぼゆ。さすがに、かけ離れたてまつらぬ宿世ながら、かく口惜しき際の者だに、もの思ひなげにて、仕うまつるを色節に思ひたるに、何の罪深き身にて、心にかけておぼつかなう思ひきこえつつ、かかりける御響きをも知らで、立ち出でつらむ」 |
「なるほど、あきれたことよ、他の月日もあろうに。かえって、このご威勢を遠くから眺めるのも、わが身の程が情なく思われる。とはいえ、お離れ申し上げられない運命ながら、このような賤しい身分の者でさえも、何の物思いもないふうで、お仕えしているのを晴れがましいことに思っているのに、どのような罪深い身で、心に掛けてお案じ申し上げていながら、これほどの評判であったご参詣のことも知らずに、出掛けて来たのだろう」 |
何とした偶然であろう、ほかの月日もないようにと明石の君は驚いたが、はるかに恋人のはなばなしさを見ては、あまりに懸隔のありすぎるわが身の上であることを痛切に知って悲しんだ。さすがによそながら巡り合うだけの宿命につながれていることはわかるのであったが、笑って行った侍さえ幸福に輝いて見える日に、罪障の深い自分は何も知らずに来て |
"Geni, asamasiu, tukihi mo koso are. Nakanaka, kono ohom-arisama wo harukani miru mo, minohodo kutiwosiu oboyu. Sasuga ni, kakehanare tatematura nu sukuse nagara, kaku kutiwosiki kiha no mono dani, monoomohi nage nite, tukaumaturu wo irohusi ni omohi taru ni, nani no tumi hukaki mi nite, kokoro ni kake te obotukanau omohi kikoye tutu, kakari keru ohom-hibiki wo mo sira de, tatiide tu ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.9 | など思ひ続くるに、いと悲しうて、人知れずしほたれけり。 |
などと思い続けると、実に悲しくなって、人知れず涙がこぼれるのであった。 |
恥ずかしい思いをするのであろうと思い続けると悲しくばかりなった。 |
nado omohi tudukuru ni, ito kanasiu te, hitosirezu sihotare keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | 第二段 住吉社頭の盛儀 |
4-2 Ceremony in front of Sumiyoshi-no-Kami |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | 松原の深緑なるに、花紅葉をこき散らしたると見ゆる表の衣の、濃き薄き、数知らず。 六位のなかにも蔵人は青色しるく見えて、かの賀茂の瑞垣恨みし右近将監も靫負になりて、ことごとしげなる随身具したる蔵人なり。 |
松原の深緑を背景に、花や紅葉をまき散らしたように見える袍衣姿の、濃いのや薄いのが、数知れず見える。六位の中でも蔵人は麹塵色がはっきりと見えて、あの賀茂の瑞垣を恨んだ右近将監も靫負になって、ものものしそうな随身を伴った蔵人である。 |
深い緑の松原の中に花 |
Matubara no hukamidori naru ni, hana momidi wo koki tirasi taru to miyuru uhenokinu no, koki usuki, kazu sira zu. Rokuwi no naka ni mo Kuraudo ha awoiro siruku miye te, kano Kamo no midugaki urami si Ukon-no-Zyou mo Yugehi ni nari te, kotogotosige naru zuizin gusi taru Kuraudo nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | 良清も同じ佐にて、人よりことにもの思ひなきけしきにて、おどろおどろしき赤衣姿、いときよげなり。 |
良清も同じ衛門佐で、誰よりも格別物思いもない様子で、仰々しい緋色姿が、たいそう美しげである。 |
|
Yosikiyo mo onazi Suke nite, hito yori koto ni monoomohi naki kesiki nite, odoroodorosiki akaginu sugata, ito kiyoge nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | すべて見し人びと、引き変へはなやかに、何ごと思ふらむと見えて、うち散りたるに、若やかなる上達部、殿上人の、 我も我もと思ひいどみ、馬鞍などまで飾りを整へ磨きたまへるは、 いみじき物に、田舎人も思へり。 |
すべて見た人々は、うって変わってはなやかになり、何の憂えもなさそうに見えて、散らばっている中で、若々しい上達部、殿上人が、我も我もと競争で、馬や鞍などまで飾りを整え美しく装いしていらっしゃるのは、たいそうな物であると、田舎者も思った。 |
明石に来ていた人たちが昔の面影とは違ったはなやかな姿で人々の中に混じっているのが船から見られた。若い顕官たち、殿上役人が競うように凝った姿をして、馬や |
Subete mi si hitobito, hikikahe hanayaka ni, nanigoto omohu ram to miye te, uti-tiri taru ni, wakayaka naru Kamdatime, Tenzyaubito no, ware mo ware mo to omohi idomi, muma kura nado made kazari wo totonohe migaki tamahe ru ha, imiziki mono ni, winakabito mo omohe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.4 | 御車を遥かに見やれば、なかなか、心やましくて、恋しき御影をもえ見たてまつらず。 河原大臣の御例をまねびて、童随身を賜りたまひける、いとをかしげに装束き、みづら結ひて、紫裾濃の元結なまめかしう、丈姿ととのひ、うつくしげにて十人、さまことに今めかしう見ゆ。 |
お車を遠く見やると、かえって、心が苦しくなって、恋しいお姿をも拝することができない。河原左大臣のご先例にならって、童随身を賜っていらっしゃったが、とても美しそうに装束を着て、みずらを結って、紫の裾濃の元結が優美で、身の丈や姿もそろって、かわいらしい格好をして十人、格別はなやかに見える。 |
源氏の乗った車が来た時、明石の君はきまり悪さに恋しい人をのぞくことができなかった。 |
Ohom-kuruma wo haruka ni miyare ba, nakanaka, kokoroyamasiku te, kohisiki ohom-kage wo mo e mi tatematura zu. Kahara-no-Otodo no ohom-rei wo manebi te, warahazuizin wo tamahari tamahi keru, ito wokasige ni sauzoki, midura yuhi te, murasaki susogo no motoyuhi namamekasiu, take sugata totonohi, utukusige nite zihunin, sama koto ni imamekasiu miyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.5 | 大殿腹の若君、限りなくかしづき立てて、馬添ひ、童のほど、皆作りあはせて、やう変へて装束きわけたり。 |
大殿腹の若君、この上なく大切にお扱いになって、馬に付き添う供人、童の具合など、みな揃いの衣装で、他とは変わって服装で区別していた。 |
近年はあまり許される者のない珍しい随身である。大臣家で生まれた若君は馬に乗せられていて、一班ずつを |
Ohotonobara no Wakagimi, kagirinaku kasiduki tate te, mumazohi, waraha no hodo, mina tukuri ahase te, yau kahe te sauzoki wake tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.6 | 雲居遥かにめでたく見ゆるにつけても、 若君の数ならぬさまにてものしたまふを、 いみじと思ふ。いよいよ 御社の方を拝みきこゆ。 |
雲居遥かな立派さを見るにつけても、若君の人数にも入らない様子でいらっしゃるのを、ひどく悲しいと思う。ますます御社の方角をお拝み申し上げる。 |
最高の貴族の子供というものはこうしたものであるというように、多数の人から大事に扱われて通って行くのを見た時、明石の君は自分の子も兄弟でいながら見る影もなく扱われていると悲しかった。いよいよ |
Kumowi haruka ni medetaku miyuru ni tuke te mo, Wakagimi no kazu nara nu sama nite monosi tamahu wo, imizi to omohu. Iyoiyo Miyasiro no kata wo wogami kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.7 | 国の守参りて、御まうけ、例の大臣などの参りたまふよりは、ことに世になく 仕うまつりけむかし。 |
摂津の国守が参上して、ご饗応の準備、普通の大臣などが参詣なさる時よりは、格別にまたとないくらい立派に奉仕したことであろうよ。 |
摂津守が出て来て一行を |
Kuni-no-Kami mawiri te, ohom-mauke, rei no Otodo nado no mawiri tamahu yori ha, koto ni yo ni naku tukaumaturi kem kasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.8 | いとはしたなければ、 |
とてもいたたまれない思いなので、 |
明石の君はますます自分がみじめに見えた。 |
Ito hasitanakere ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.9 | 「 立ち交じり、数ならぬ身の、いささかのことせむに、神も見入れ、数まへたまふべきにもあらず。帰らむにも中空なり。今日は難波に舟さし止めて、祓へをだにせむ」 |
「あの中に立ちまじって、とるに足らない身の上で、少しばかりの捧げ物をしても、神も御覧になり、お認めくださるはずもあるまい。帰るにしても中途半端である。今日は難波に舟を泊めて、せめてお祓いだけでもしよう」 |
こんな時に自分などが貧弱な |
"Tati-maziri, kazu nara nu mi no, isasaka no koto se m ni, Kami mo miire, kazumahe tamahu beki ni mo ara zu. Kahera m ni mo nakazora nari. Kehu ha Naniha ni hune sasitome te, harahe wo dani sem." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.10 | とて、漕ぎ渡りぬ。 |
と思って、漕いで行った。 |
明石の君の乗った船はそっと住吉を去った。 |
tote, kogi watari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | 第三段 源氏、惟光と住吉の神徳を感ず |
4-3 Genji and Koremitsu are thankful for Sumiyoshi-no-Kami |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | 君は、夢にも知りたまはず、 夜一夜、いろいろのことをせさせたまふ。まことに、神の喜びたまふべきことを、し尽くして、来し方の御願にもうち添へ、ありがたきまで、遊びののしり明かしたまふ。 |
君は、まったくご存知なく、一晩中、いろいろな神事を奉納させなさる。真実に、神がお喜びになるにちがいないことを、あらゆる限りなさって、過去の御願果たしに加えて、前例のないくらいまで、楽や舞の奉納の大騷ぎして夜をお明かしになる。 |
こんなことを源氏は夢にも知らないでいた。夜通しいろいろの音楽舞楽を |
Kimi ha, yume ni mo siri tamaha zu, yohitoyo, iroiro no koto wo se sase tamahu. Makoto ni, Kami no yorokobi tamahu beki koto wo, si tukusi te, kisikata no ohom-gwan ni mo uti-sohe, arigataki made, asobi nonosiri akasi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | 惟光やうの人は、心のうちに神の御徳をあはれにめでたしと思ふ。あからさまに立ち出でたまへるに、さぶらひて、聞こえ出でたり。 |
惟光などのような人は、心中に神のご神徳をしみじみとありがたく思う。ちょっと出ていらっしゃたので、お側に寄って、申し上げた。 |
|
Koremitu yau no hito ha, kokoro no uti ni Kami no ohom-toku wo ahare ni medetasi to omohu. Akarasama ni tatiide tamahe ru ni, saburahi te, kikoye ide tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.3 | 「 住吉の松こそものはかなしけれ 神代のことをかけて思へば」 |
「住吉の松を見るにつけ感慨無量です 昔のことがを忘れられずに思われますので」 |
住吉の松こそものは悲しけれ 神代のことをかけて思へば |
"Sumiyosi no matu koso mono ha kanasikere Kamiyo no koto wo kake te omohe ba |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.4 | げに、と思し出でて、 |
いかにもと、お思い出しになって、 |
源氏もそう思っていた。 |
Geni, to obosi-ide te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.5 | 「 荒かりし波のまよひに住吉の 神をばかけて忘れやはする |
「あの須磨の大嵐が荒れ狂った時に 念じた住吉の神の御神徳をどうして忘られようぞ |
「荒かりし 神をばかけて忘れやはする |
"Arakari si nami no mayohi ni Sumiyosi no Kami wo ba kake te wasure yaha suru |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.6 | 験ありな」 |
霊験あらたかであったな」 |
確かに私は霊験を見た人だ」 |
Sirusi ari na!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.7 | とのたまふも、いとめでたし。 |
とおっしゃるのも、たいそう素晴らしい。 |
と言う様子も美しい。 |
to notamahu mo, ito medetasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | 第四段 源氏、明石の君に和歌を贈る |
4-4 Genji sends out a waka to Akashi-no-Kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | かの明石の舟、この響きに圧されて、過ぎぬることも聞こゆれば、「 知らざりけるよ」と、あはれに思す。神の御しるべを思し出づるも、おろかならねば、「 いささかなる消息をだにして、心慰めばや。 なかなかに思ふらむかし」と思す。 |
あの明石の舟が、この騷ぎに圧倒されて、立ち去ったことも申し上げると、「知らなかったなあ」と、しみじみと気の毒にお思いになる。神のお導きとお思い出しになるにつけ、おろそかには思われないので、「せめてちょっとした手紙だけでも遣わして、気持ちを慰めてやりたい。かえってつらい思いをしていることだろう」とお思いになる。 |
こちらの |
Kano Akasi no hune, kono hibiki ni osa re te, sugi nuru koto mo kikoyure ba, "Sira zari keru yo!" to, ahare ni obosu. Kami no ohom-sirube wo obosi iduru mo, oroka nara ne ba, "Isasaka naru seusoko wo dani si te, kokoro nagusame baya. Nakanaka ni omohu ram kasi." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
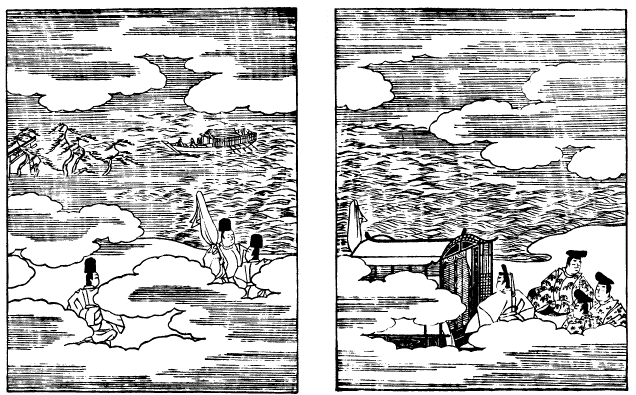 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.2 | 御社立ちたまて、所々に逍遥を尽くしたまふ。難波の御祓へ、七瀬によそほしう仕まつる。堀江のわたりを御覧じて、 |
御社をご出発になって、あちこちの名所に遊覧なさる。難波のお祓い、七瀬に立派にお勤めになる。堀江のあたりを御覧になって、 |
住吉を立ってから源氏の一行は海岸の風光を愛しながら浪速に出た。そこでは祓いをすることになっていた。 |
Miyasiro tati tama' te, tokorodokoro ni seuyeu wo tukusi tamahu. Naniha no ohom-harahe, nanase ni yosohosiu tukamaturu. Horie no watari wo goranzi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.3 | 「 ▼ 今はた同じ難波なる」 |
「今はた同じ難波なる」 |
「今はた同じ浪速なる」 |
"Ima hata onazi Naniha naru." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.4 | と、御心にもあらで、うち誦じたまへるを、御車のもと近き惟光、 うけたまはりやしつらむ、さる召しもやと、例にならひて懐にまうけたる柄短き筆など、御車とどむる所にてたてまつれり。「 をかし」と思して、畳紙に、 |
と、無意識のうちに、ふと朗誦なさったのを、お車の近くにいる惟光、聞きつけたのであろうか、そのような御用もあろうかと、いつものように懐中に準備しておいた柄の短い筆などを、お車を止めた所で差し上げた。「よく気がつくな」と感心なさって、畳紙に、 |
(身をつくしても逢はんとぞ思ふ)と我知らず口に出た。車の近くから惟光が口ずさみを聞いたのか、その用があろうと例のように懐中に用意していた柄の短い筆などを、源氏の車の留められた際に提供した。源氏は懐紙に書くのであった。 |
to, mikokoro ni mo ara de, uti-zyuzi tamahe ru wo, ohom-kuruma no moto tikaki Koremitu, uketamahari ya si tu ram, saru mesi mo ya to, rei ni narahi te hutokoro ni mauke taru tuka mizikaki hude nado, ohom-kuruma todomuru tokoro nite tatemature ri. "Wokasi" to obosi te, tataugami ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.5 | 「 みをつくし恋ふるしるしにここまでも めぐり逢ひけるえには深しな」 |
「身を尽くして恋い慕っていた甲斐のあるここで めぐり逢えたとは、縁は深いのですね」 |
みをつくし恋ふるしるしにここまでも めぐり逢ひける |
"Mi wo tukusi kohuru sirusi ni koko made mo meguriahi keru eni ha hukasi na |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.6 | とて、たまへれば、かしこの心知れる下人して遣りけり。駒並めて、うち過ぎたまふにも、 心のみ動くに、露ばかりなれど、 いとあはれにかたじけなくおぼえて、うち泣きぬ。 |
と書いて、お与えになると、あちらの事情を知っている下人を遣わして贈るのであった。馬を多数並べて、通り過ぎて行かれるにつけても、心が乱れるばかりで、ほんの歌一首ばかりのお手紙であるが、実にしみじみともったいなく思われて、涙がこぼれた。 |
惟光に渡すと、明石へついて行っていた男で、入道家の者と心安くなっていた者を使いにして明石の君の船へやった。派手な一行が浪速を通って行くのを見ても、女は自身の |
tote, tamahe re ba, kasiko no kokorosire ru simobito site yari keri. Koma name te, uti-sugi tamahu ni mo, kokoro nomi ugoku ni, tuyu bakari nare do, ito ahare ni katazikenaku oboye te, uti-naki nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.7 | 「 数ならで難波のこともかひなきに などみをつくし思ひそめけむ」 |
「とるに足らない身の上で、何もかもあきらめておりましたのに どうして身を尽くしてまでお慕い申し上げることになったのでしょう」 |
数ならでなにはのこともかひなきに 何みをつくし思ひ |
"Kazu nara de Naniha no koto mo kahinaki ni nado miwotukusi omohi some kem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.8 | 田蓑の島に御禊仕うまつる、御祓への物につけてたてまつる。日暮れ方になりゆく。 |
田蓑の島で禊を勤めるお祓いの木綿につけて差し上げる。日も暮れ方になって行く。 |
|
Tamino-no-sima ni misogi tukaumaturu, ohom-harahe no mono ni tuke te tatematuru. Hi kuregata ni nari yuku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.9 | 夕潮満ち来て、入江の鶴も声惜しまぬほど ★の あはれなる折からなればにや、人目もつつまず、あひ見まほしくさへ思さる。 |
夕潮が満ちて来て、入江の鶴も、声惜しまず鳴く頃のしみじみとした情趣からであろうか、人の目も憚らず、お逢いしたいとまで、思わずにはいらっしゃれない。 |
夕方の満潮時で、海べにいる |
Yuhusiho miti ki te, irie no tadu mo kowe wosima nu hodo no ahare naru worikara nare ba ni ya, hitome mo tutuma zu, ahi mi mahosiku sahe obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.10 | 「 露けさの昔に似たる旅衣 ▼ 田蓑の島の名には隠れず」 |
「涙に濡れる旅の衣は、昔、海浜を流浪した時と同じようだ 田蓑の島という名の蓑の名には身は隠れないので」 |
露けさの昔に似たる |
"Tuyukesa no mukasi ni ni taru tabigoromo Tamino-no-sima no na ni ha kakure zu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.11 | 道のままに、かひある逍遥遊びののしりたまへど、御心にはなほかかりて思しやる。遊女どもの集ひ参れる、上達部と聞こゆれど、若やかにこと好ましげなるは、皆、 目とどめたまふべかめり。されど、「 いでや、をかしきことも、もののあはれも、人からこそあべけれ。なのめなることをだに、すこしあはき方に寄りぬるは、心とどむるたよりもなきものを」と思すに、 おのが心をやりて、よしめきあへるも疎ましう思しけり。 |
道すがら、結構な遊覧や奏楽をして大騷ぎなさるが、お心にはなおも掛かって思いをお馳せになる。遊女連中が集まって参っているが、上達部と申し上げても、若々しく風流好みの方は、皆、目を留めていらっしゃるようである。けれども、「さあ、風流なことも、ものの情趣も、相手の人柄によるものだろう。普通の恋愛でさえ、少し浮ついたものは、心を留める点もないものだから」とお思いになると、自分の心の赴くままに、嬌態を演じあっているのも、嫌に思われるのであった。 |
と源氏は歌われるのであった。遊覧の旅をおもしろがっている人たちの中で源氏一人は時々暗い心になった。高官であっても若い好奇心に富んだ人は、小船を |
Miti no mama ni, kahi aru seuyeu asobi nonosiri tamahe do, mikokoro ni ha naho kakari te obosiyaru. Asobi-domo no tudohi mawire ru, Kamdatime to kikoyure do, wakayaka ni koto konomasige naru ha, mina, me todome tamahu beka' meri. Saredo, "Ideya, wokasiki koto mo, mono no ahare mo, hito kara koso a' bekere. Nanome naru koto wo dani, sukosi ahaki kata ni yori nuru ha, kokoro todomuru tayori mo naki mono wo." to obosu ni, onoga kokoro wo yari te, yosimeki ahe ru mo utomasiu obosi keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 第五段 明石の君、翌日住吉に詣でる |
4-5 Akashi-no-Kimi visits to Sumiyoshi-shrine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.1 | かの人は、過ぐしきこえて、またの日ぞ吉ろしかりければ、御幣たてまつる。ほどにつけたる願どもなど、かつがつ果たしける。 また、なかなかもの思ひ添はりて、明け暮れ、口惜しき身を思ひ嘆く。 |
あの人は、通り過ぎるのをお待ち申して、次の日が日柄も悪くはなかったので、幣帛を奉る。身分相応の願ほどきなど、ともかくも済ませたのであった。また一方、かえって物思いが加わって、朝に晩に、取るに足らない身の上を嘆いている。 |
明石の君は源氏の一行が |
Kano hito ha, sugusi kikoye te, matanohi zo yorosikari kere ba, mitegura tatematuru. Hodo ni tuke taru gwan-domo nado, katugatu hatasi keru. Mata, nakanaka monoomohi sohari te, akekure, kutiwosiki mi wo omohi nageku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.2 | 今や京におはし着くらむと思ふ日数も経ず、御使あり。このころのほどに迎へむことをぞのたまへる。 |
今頃は京にお着きになっただろうと思われる日数もたたないうちに、お使いがある。近々のうちに迎えることをおっしゃっていた。 |
もう京へ源氏の着くころであろうと思ってから間もなく源氏の使いが明石へ来た。近いうちに京へ迎えたいという手紙を持って来たのである。 |
Ima ya Kyau ni ohasi tuku ram to omohu hikazu mo he zu, ohom-tukahi ari. Konokoro no hodo ni mukahe m koto wo zo notamahe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.3 | 「 いと頼もしげに、数まへのたまふめれど、いさや、また、 ▼ 島漕ぎ離れ、中空に心細きことやあらむ」 |
「とても頼りがいありそうに、一人前に扱ってくださるようだけれども、どうかしら、また、故郷を出て、どっちつかずの心細い思いをするのではないかしら」 |
頼もしいふうに恋人の一人として認められている自分であるが、故郷を立って京へ出たのちにまで源氏の愛は変わらずに続くものであろうかと考えられることによって |
"Ito tanomosige ni, kazumahe notamahu mere do, isaya, mata, sima kogi hanare, nakazora ni kokorobosoki koto ya ara m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.4 | と、思ひわづらふ。 |
と思い悩む。 |
女は苦しんでいた。 |
to, omohi wadurahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.5 | 入道も、さて出だし 放たむは、いとうしろめたう、さりとて、かく埋もれ過ぐさむを思はむも、なかなか来し方の年ごろよりも、心尽くしなり。よろづにつつましう、思ひ立ちがたきことを聞こゆ。 |
入道も、そのように手放すのは、まことに不安で、そうかといって、このように埋もれて過すことを考えると、かえって今までよりも、物思いが増す。いろいろと気後れがして、決心しがたい旨を申し上げる。 |
入道も手もとから娘を離してやることは不安に思われるのであるが、そうかといってこのまま田舎に置くことも悲惨な気がして源氏との関係が生じなかった時代よりもかえって苦労は多くなったようであった。女からは源氏をめぐるまぶしい人たちの中へ出て行く自信がなくて出京はできないという返事をした。 |
Nihudau mo, sate idasi hanata m ha, ito usirometau, saritote, kaku udumore sugusa m wo omoha m mo, nakanaka kisikata no tosigoro yori mo, kokorodukusi nari. Yorodu ni tutumasiu, omohitati gataki koto wo kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/21/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 10/3/2009(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Latest updated 6/21/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/3/2009 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 4.00: Copyright (c) 2003,2024 宮脇文経