第十九帖 薄雲 |
19 USUGUMO (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の内大臣時代 三十一歳冬十二月から三十二歳秋までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from December in winter at the age of 31 to fall at the age of 32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 明石の物語 母子の雪の別れ |
1 Tale of Akashi Parting daughter from mother in snow days |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 明石、姫君の養女問題に苦慮する |
1-1 Akashi worries herself about adoption of her daughter to Murasaki's |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 冬になりゆくままに、 川づらの住まひ ★、いとど心細さまさりて、うはの空なる心地のみしつつ明かし暮らすを、君も、 |
冬になるにしたがって、川辺の生活は、ますます心細さがつのっていって、上の空のような心地ばかりしながら毎日を暮らしているのを、君も、 |
冬になって来て川沿いの家にいる人は心細い思いをすることが多く、気の落ち着くこともない日の続くのを、源氏も見かねて、 |
Huyu ni nari yuku mama ni, kahadura no sumahi, itodo kokorobososa masari te, uhanosora naru kokoti nomi si tutu akasi kurasu wo, Kimi mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 「 なほ、かくては、え過ぐさじ。かの、近き所に思ひ立ちね」 |
「やはり、このまま過すことは、できまい。あの、邸に近い所に移ることを決心なさい」 |
「これではたまらないだろう、私の言っている近い家へ引っ越す決心をなさい」 |
"Naho, kakute ha, e sugusa zi. Kano, tikaki tokoro ni omohitati ne." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | と、すすめたまへど、「 ▼ つらき所多く心見果てむも、 残りなき心地すべきを、 いかに言ひてか」などいふやうに思ひ乱れたり。 |
と、お勧めになるが、「冷淡な気持ちを多くすっかり見てしまうのも、未練も残らないことになるだろうから、何と恨みを言ったらよいものだろうか」などというように思い悩んでいた。 |
と勧めるのであったが、「宿変へて待つにも見えずなりぬればつらき所の多くもあるかな」という歌のように、恋人の冷淡に思われることも地理的に |
to, susume tamahe do, "Turaki tokoro ohoku kokoro mi hate m mo, nokori naki kokoti su beki wo, ikani ihi te ka?" nado ihu yau ni omohi midare tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | 「 さらば、この若君を。かくてのみは、便なきことなり。 思ふ心あれば、かたじけなし。対に聞き置きて、常にゆかしがるを、しばし見ならはさせて、袴着の事なども、人知れぬさまならずしなさむとなむ思ふ」 |
「それでは、この若君を。こうしてばかりいては、不都合なことです。将来に期するところもあるので、恐れ多いことです。対の君も耳にして、いつも見たがっているのですが、しばらくの間馴染ませて、袴着の祝いなども、ひっそりとではなく催そうと思う」 |
「あなたがいやなら姫君だけでもそうさせてはどう。こうしておくことは将来のためにどうかと思う。私はこの子の運命に予期していることがあるのだから、その暁を思うともったいない。西の |
"Saraba, kono Wakagimi wo. Kaku te nomi ha, binnaki koto nari. Omohu kokoro are ba, katazikenasi. Tai ni kikioki te, tune ni yukasigaru wo, sibasi mi narahasase te, hakamagi no koto nado mo, hito sire nu sama nara zu si nasa m to nam omohu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | と、まめやかに語らひたまふ。「 さ思すらむ」と思ひわたることなれば、いとど胸つぶれぬ。 |
と、真剣にご相談になる。「きっとそのようにおっしゃるだろう」とかねて思っていたことなので、ますます胸がつぶれる思いがした。 |
源氏はねんごろにこう言うのであったが、源氏がそう計らおうとするのでないかとは、明石が以前から想像していたことであったから、この言葉を聞くとはっと胸がとどろいた。 |
to, mameyaka ni katarahi tamahu. "Sa obosu ram." to omohi wataru koto nare ba, itodo mune tubure nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | 「 改めてやむごとなき方にもてなされたまふとも、人の漏り聞かむことは、なかなかにや、つくろひがたく思されむ」 |
「今さら尊い人として大切に扱われなさっても、人が漏れ聞くだろうことは、かえって、とりつくろいにくくお思いになるのではないでしょうか」 |
「よいお母様の子にしていただきましても、ほんとうのことは世間が知っていまして、何かと |
"Aratame te yamgotonaki kata ni motenasa re tamahu tomo, hito no mori kika m koto ha, nakanaka ni ya, tukurohi gataku obosa re m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | とて、放ちがたく思ひたる、ことわりには あれど、 |
と言って、手放しがたく思っているのは、もっともなことではあるが、 |
手放しがたいように女は思うふうである。 |
tote, hanati gataku omohi taru, kotowari ni ha are do, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | 「うしろやすからぬ方にやなどは、な疑ひたまひそ。かしこには、年経ぬれど、かかる人もなきが、さうざうしくおぼゆるままに、 前斎宮のおとなびものしたまふをだにこそ、あながちに扱ひきこゆめれば、まして、かく 憎みがたげなめるほどを、おろかには 見放つまじき心ばへに」 |
「安心できない取り扱いを受けやしまいかなどと、決してお疑いなさいますな。あちらには、何年にもなるのに、このような子どももいないのが、淋しい気がするので、前斎宮の大きくおなりでいらしゃるのをさえ、無理に親代わりのお世話申しているようなので、まして、このようにあどけない年頃の人を、いいかげんなお世話はしない性格です」 |
「あなたが賛成しないのはもっともだけれど、継母の点で不安がったりはしないでおおきなさい。あの人は私の所へ来てずいぶん長くなるのだが、こんなかわいい者のできないのを寂しがってね、 |
"Usiroyasukara nu kata ni ya nado ha, na utagahi tamahi so. Kasiko ni ha, tosi he nure do, kakaru hito mo naki ga, sauzausiku oboyuru mama ni, saki-no-Saiguu no otonabi monosi tamahu wo dani koso, anagati ni atukahi kikoyu mere ba, masite, kaku nikumi gatage na' meru hodo wo, oroka ni ha mihanatu maziki kokorobahe ni." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | など、女君の御ありさまの思ふやうなることも語りたまふ。 |
などと、女君のご様子が申し分ないことをお話になる。 |
源氏は紫の |
nado, Womnagimi no ohom-arisama no omohu yau naru koto mo katari tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10 | 「 げに、いにしへは、いかばかりのことに定まりたまふべきにかと、つてにも ほの聞こえし御心の、名残なく静まりたまへるは、おぼろけの御宿世にもあらず、人の御ありさまも、ここらの御なかにすぐれたまへるにこそは」と思ひやられて、「 数ならぬ人の並びきこゆべきおぼえにもあらぬを、 さすがに、立ち出でて、人もめざましと思すことやあらむ。わが身は、とてもかくても同じこと。生ひ先遠き人の御うへも、つひには、かの御心にかかるべきにこそあめれ。さりとならば、げにかう何心なきほどにや譲りきこえまし」と思ふ。 |
「ほんとに、昔は、どれほどの方に落ち着かれるのだろうかと、噂にちらっと聞いたご好色心がすっかりお静まりになったのは、並大抵のご宿縁ではなく、お人柄のご様子もおおぜいの方々の中でも優れていらっしゃるからこそだろう」と想像されて、「一人前でもない者がご一緒させていただける扱いでもないのに、それにもかかわらず、さし出たら、あの方も身の程知らずなと、お思いになるやも知れぬ。自分の身は、どうなっても同じこと。将来のある姫君のお身の上も、ゆくゆくは、あの方のお心次第であろう。そうとならば、なるほどこのように無邪気な間にお譲り申し上げようかしら」と思う。 |
それはほんとうであるに違いない、昔はどこへ源氏の愛は落ち着くものか想像もできないという |
"Geni, inisihe ha, ikabakari no koto ni sadamari tamahu beki ni ka to, tute ni mo hono-kikoye si mi-kokoro no, nagori naku sidumari tamahe ru ha, oboroke no ohom-sukuse ni mo ara zu, hito no ohom-arisama mo, kokora no ohom-naka ni sugure tamahe ru ni koso ha." to omohiyara re te, "Kazu nara nu hito no narabi kikoyu beki oboye ni mo ara nu wo, sasuga ni, tatiide te, hito mo mezamasi to obosu koto ya ara m. Waga mi ha, totemokakutemo onazi koto. Ohisaki tohoki hito no ohom-uhe mo, tuhini ha, kano mi-kokoro ni kakaru beki ni koso a' mere. Sari to nara ba, geni kau nanigokoronaki hodo ni ya yuduri kikoye masi." to omohu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11 | また、「手を放ちて、うしろめたからむこと。つれづれも慰む方なくては、 いかが明かし暮らすべからむ。何につけてか、たまさかの御立ち寄りもあらむ」など、さまざまに思ひ乱るるに、身の憂きこと、限りなし。 |
また一方では、「手放したら、不安でたまらないだろうこと。所在ない気持ちを慰めるすべもなくなっては、どのようにして毎日を暮らしてゆけようか。何を目当てとして、たまさかのお立ち寄りがあるだろうか」などと、さまざまに思い悩むにつけ、身の上のつらいこと、際限がない。 |
しかしまた気がかりでならないことであろうし、つれづれを慰めるものを失っては、自分は何によって日を送ろう、姫君がいるためにたまさかに |
Mata, "Te wo hanati te, usirometakara m koto. Turedure mo nagusamu kata naku te ha, ikaga akasi kurasu bekara m? Nani ni tuke te ka, tamasaka no ohom-tatiyori mo ara m?" nado, samazama ni omohi midaruru ni, mi no uki koto, kagiri nasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 尼君、姫君を養女に出すことを勧める |
1-2 Mother advices to Akashi to adopt her daughter to Murasaki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 尼君、思ひやり深き人にて、 |
尼君、思慮の深い人なので、 |
尼君は思慮のある女であったから、 |
Amagimi, omohiyari hukaki hito nite, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 「 あぢきなし。見たてまつらざらむことは、いと胸いたかりぬべけれど、つひにこの御ためによかるべからむことをこそ思はめ。浅く思してのたまふことにはあらじ。ただうち頼みきこえて、渡したてまつりたまひてよ。母方からこそ、帝の御子も際々におはすめれ。この大臣の君の、世に二つなき御ありさまながら、世に仕へたまふは、 故大納言の、今ひときざみなり劣りたまひて、更衣腹と言はれたまひし、けぢめにこそはおはすめれ。まして、ただ人はなずらふべきことにもあらず。 |
「つまりません。お目にかかれないことは、とても胸の痛いことにちがいありませんが、結局は、姫君の御ためによいことだろうことを考えなさい。浅いお考えでおっしゃることではあるまい。ただご信頼申し上げて、お渡し申されよ。母方の身分によって、帝の御子もそれぞれに差がおありになるようです。この大臣の君が、世に二人といない素晴らしいご様子でありながら、朝廷にお仕えなさっているのは、故大納言が、いま一段劣っていらっしゃって、更衣腹と言われなさった、その違いなのでいらっしゃるようです。ましてや、臣下の場合では、比較することもできません。 |
「あなたが姫君を手放すまいとするのはまちがっている。ここにおいでにならなくなることは、どんなに苦しいことかはしれないけれど、あなたは母として姫君の最も幸福になることを考えなければならない。姫君を愛しないでおっしゃることでこれはありませんよ。あちらの奥様を信頼してお渡しなさいよ。母親次第で陛下のお子様だって階級ができるのだからね。源氏の大臣がだれよりもすぐれた天分を持っていらっしゃりながら、 |
"Adikinasi. Mi tatematura zara m koto ha, ito mune itakari nu bekere do, tuhini kono ohom-tame ni yokaru bekara m koto wo koso omoha me. Asaku obosi te notamahu koto ni ha ara zi. Tada uti-tanomi kikoye te, watasi tatematuri tamahi te yo. Hahagata kara koso, Mikado no miko mo kihagiha ni ohasu mere. Kono Otodo-no-Kimi no, yo ni hutatu naki ohom-arisama nagara, yo ni tukahe tamahu ha, ko-Dainagon no, ima hitokizami nari otori tamahi te, Kauibara to iha re tamahi si, kedime ni koso ha ohasu mere. Masite, tadaudo ha nazurahu beki koto ni mo ara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | また、 親王たち、大臣の御腹といへど、 なほさし向かひたる劣りの所には、人も思ひ落とし、親の御もてなしも、え等しからぬものなり。まして、これは、やむごとなき御方々にかかる人、出でものしたまはば、こよなく消たれたまひなむ。ほどほどにつけて、親にもひとふしもてかしづかれぬる人こそ、やがて落としめられぬはじめとはなれ。御袴着のほども、いみじき心を尽くすとも、かかる 深山隠れにては、何の栄かあらむ。ただ任せきこえたまひて、もてなしきこえたまはむありさまをも、聞きたまへ」 |
また、親王方、大臣の御腹といっても、やはり正妻の劣っているところよりは、世間も軽視し、父親のご待遇も、同等にできないものなのです。まして、この姫君は、身分の高い女君方にこのような姫君が、お生まれになったら、すっかり忘れ去られてしまうでしょう。身分相応につけ、父親にひとかどに大切にされた人こそは、そのまま軽んぜられないもととなるのです。御袴着の祝いも、どんなに一生懸命におこなっても、このような人里離れた所では、何の見栄えがありましょう。ただお任せ申し上げなさって、そのおもてなしくださるご様子を、見ていらっしゃい」 |
また親王様だって、大臣の家だって、良い奥様から生まれたお子さんと、劣った生母を持つお子さんとは人の尊敬のしかたが違うし、親だって公平にはおできにならないものです。姫君の場合を考えれば、まだ幾人もいらっしゃるりっぱな奥様方のどっちかで姫君がお生まれになれば、当然肩身の狭いほうのお嬢さんにおなりになりますよ。一体女というものは親からたいせつにしてもらうことで将来の運も招くことになるものよ。 |
Mata, Miko-tati, Otodo no ohom-hara to ihe do, naho sasimukahi taru otori no tokoro ni ha, hito mo omohi otosi, oya no ohom-motenasi mo, e hitosikara nu mono nari. Masite, kore ha, yamgotonaki ohom-katagata ni kakaru hito, ide monosi tamaha ba, koyonaku keta re tamahi na m. Hodohodo ni tuke te, oya ni mo hitohusi mote-kasiduka re nuru hito koso, yagate otosime rare nu hazime to ha nare. Ohom-hakamagi no hodo mo, imiziki kokoro wo tukusu tomo, kakaru miyamagakure nite ha, nani no haye ka ara m? Tada makase kikoye tamahi te, motenasi kikoye tamaha m arisama wo mo, kiki tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | と教ふ。 |
と教える。 |
と娘に |
to wosihu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | さかしき人の心の占どもにも、もの問はせなどするにも ★、なほ「渡りたまひてはまさるべし」とのみ言へば、思ひ弱りにたり。 |
賢い人の将来の予想などにも、また占わせたりなどをしても、やはり「お移りになった方が良いでしょう」とばかり言うので、気が弱くなってきた。 |
賢い人に聞いて見ても、占いをさせてみても、二条の院へ渡すほうに姫君の幸運があるとばかり言われて、明石は子を放すまいと固執する力が弱って行った。 |
Sakasiki hito no kokoro no ura-domo ni mo, mono toha se nado suru ni mo, naho "Watari tamahi te ha masaru besi." to nomi ihe ba, omohi-yowari ni tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 殿も、しか思しながら、思はむところのいとほしさに、しひてもえのたまはで、 |
殿も、そのようにお思いになりながら、悲しむ人の気の毒さに、無理におっしゃることもできないで、 |
源氏もそうしたくは思いながらも、女の気持ちを尊重してしいて言うことはしなかった。手紙のついでに、 |
Tono mo, sika obosi nagara, omoha m tokoro no itohosisa ni, sihite mo e notamaha de, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 「 御袴着のことは、いかやうにか ★」 |
「袴着のお祝いは、どのようにか」 |
袴着の仕度にかかりましたか |
"Ohom-hakamagi no koto ha, ikayau ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | とのたまへる御返りに、 |
とおっしゃるお返事に、 |
と書いた返事に、 |
to notamahe ru ohom-kaheri ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 「 よろづのこと、かひなき身にたぐへきこえては、げに生ひ先もいとほしかるべくおぼえはべるを、たち交じりても、いかに人笑へにや」 |
「何事につけても、ふがいないわたくしのもとにお置き申しては、お言葉どおり将来もおかわいそうに思われますが、またご一緒させていただいても、どんなにもの笑いになりましょうやら」 |
何事も無力な母のそばにおりましては気の毒でございます。先日のお言葉のように |
"Yorodu no koto, kahinaki mi ni taguhe kikoye te ha, geni ohisaki mo itohosikaru beku oboye haberu wo, tatimaziri te mo, ikani hitowarahe ni ya?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | と聞こえたるを、いとどあはれに思す。 |
と申し上げたので、ますますお気の毒にお思いになる。 |
と言って来たのを源氏は哀れに思った。 |
to kikoye taru wo, itodo ahare ni obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 日など取らせたまひて、忍びやかに、さるべきことなどのたまひおきてさせたまふ。放ちきこえむことは、なほいとあはれにおぼゆれど、「 君の御ためによかるべきことをこそは」と念ず。 |
吉日などをお選びになって、ひっそりと、しかるべき事がらをお決めになって準備させなさる。手放し申すことは、やはりとてもつらく思われるが、「姫君のご将来のために良いことを第一に」と我慢する。 |
源氏はいよいよ二条の院ですることになった姫君の袴着の吉日を選ばせて、式の用意を命じていた。式は式でも紫夫人の手へ姫君を渡しきりにすることは今でも堪えがたいことに明石は思いながらも、何事も姫君の幸福を先にして考えねばならぬと悲痛な決心をしていた。 |
Hi nado torase tamahi te, sinobiyaka ni, sarubeki koto nado notamahi oki te sase tamahu. Hanati kikoye m koto ha, naho ito ahare ni oboyure do, "Kimi no ohom-tame ni yokaru beki koto wo koso ha." to nenzu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 「 乳母をもひき別れなむこと。明け暮れのもの思はしさ、つれづれをもうち語らひて、慰めならひつるに、いとど たつきなきことさへ取り添へ、いみじくおぼゆべきこと」と、君も泣く。 |
「乳母とも離れてしまうこと。朝な夕なの物思い、所在ない時を話相手にして、つね日頃慰めてきたのに、ますます頼りとするものがなくなることまで加わって、どんなにか悲しい思いをせねばならないこと」と、女君も泣く。 |
|
"Menoto wo mo hiki-wakare na m koto. Akekure no mono-omohasisa, turedure wo mo uti-katarahi te, nagusame narahi turu ni, itodo tatuki naki koto sahe torisohe, imiziku oboyu beki koto." to, Kimi mo naku. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | 乳母も、 |
乳母も、 |
と |
Menoto mo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | 「 さるべきにや、おぼえぬさまにて、見たてまつりそめて、 年ごろの御心ばへの、忘れがたう恋しう おぼえたまふべきを、うち絶えきこゆることはよもはべらじ。つひにはと頼みながら、しばしにても、よそよそに、思ひのほかの交じらひしはべらむが、安からずも はべるべきかな」 |
「そうなるはずの宿縁だったのでしょうか、思いがけないことで、お目にかかるようになって、長い間のお心配りが、忘れがたくきっと恋しく思われなさいましょうが、ふっつり縁が切れることは決してありますまい。行く末はと期待しながら、しばらくの間であっても、別れ別れになって、思いもかけないご奉公をしますのが、不安でございましょうねえ」 |
「前生の因縁だったのでございましょうね、不意にお宅で |
"Sarubeki ni ya, oboye nu sama nite, mi tatematuri some te, tosigoro no mi-kokorobahe no, wasure gatau kohisiu oboye tamahu beki wo, uti-taye kikoyuru koto ha yo mo habera zi. Tuhini ha to tanomi nagara, sibasi nite mo, yosoyoso ni, omohi no hoka no mazirahi si habera m ga, yasukara zu mo haberu beki kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.15 | など、うち泣きつつ過ぐすほどに、 師走にもなりぬ。 |
などと、泣き泣き日を過ごしているうちに、十二月にもなってしまった。 |
と |
nado, uti-naki tutu sugusu hodo ni, Sihasu ni mo nari nu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 明石と乳母、和歌を唱和 |
1-3 Akashi and nurse talk and comfort with waka each other |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | 雪、霰がちに、心細さまさりて、「 あやしくさまざまに、もの思ふべかりける身かな」と、うち嘆きて、常よりも この君を撫でつくろひつつ見ゐたり。 |
雪、霰の日が多く、心細い気持ちもいっそうつのって、「不思議と何かにつけ、物思いがされるわが身だわ」と、悲しんで、いつもよりもこの姫君を撫でたり身なりを繕ったりしながら見ていた。 |
雪や |
Yuki, arare-gati ni, kokorobososa masari te, "Ayasiku samazama ni, mono omohu bekari keru mi kana!" to, uti-nageki te, tune yori mo kono Kimi wo nade tukurohi tutu mi wi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 雪かきくらし降りつもる朝、来し方行く末のこと、残らず思ひつづけて、例はことに 端近なる出で居などもせぬを、汀の氷など見やりて、白き衣どものなよよかなるあまた着て、眺めゐたる様体、頭つき、うしろでなど、「 限りなき人と聞こゆとも、かうこそはおはすらめ」と人びとも見る。落つる涙をかき払ひて、 |
雪が空を暗くして降り積もった翌朝、過ぎ去った日々のことや将来のこと、何もかもお考え続けて、いつもは特に端近な所に出ていることなどはしないのだが、汀の氷などを眺めやって、白い衣の柔らかいのを幾重にも重ね着て、物思いに沈んでいる容姿、頭の恰好、後ろ姿などは、「どんなに高貴なお方と申し上げても、こんなではいらっしゃろう」と女房たちも見る。落ちる涙をかき払って、 |
大雪になった朝、過去未来が思い続けられて、平生は縁に近く出るようなこともあまりないのであるが、端のほうに来て明石は |
Yuki kaki-kurasi huri tumoru asita, kisikata yukusuwe no koto, nokora zu omohi tuduke te, rei ha koto ni hasidika naru idewi nado mo se nu wo, migiha no kohori nado miyari te, siroki kinu-domo no nayoyoka naru amata ki te, nagame wi taru yaudai, kasiratuki, usirode nado, "Kagirinaki hito to kikoyu tomo, kau koso ha ohasu rame." to hitobito mo miru. Oturu namida wo kakiharahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | 「 かやうならむ日、ましていかにおぼつかなからむ」と、 らうたげにうち嘆きて、 |
「このような日は、今にもましてどんなにか心淋しいことでしょう」と、痛々しげに嘆いて、 |
「こんな日にはまた特別にあなたが恋しいでしょう」と |
"Kayau nara m hi, masite ikani obotukanakara m?" to, rautage ni uti-nageki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 雪深み深山の道は晴れずとも ★ なほ文かよへ跡絶えずして」 |
「雪が深いので奥深い山里への道は通れなくなろうとも どうか手紙だけはください、跡の絶えないように」 |
雪深き なほふみ通へ跡たえずして |
"Yuki hukami miyama no miti ha hare zu tomo naho humi kayohe ato taye zu si te |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | とのたまへば、乳母、うち泣きて、 |
とおっしゃると、乳母、泣いて、 |
乳母も泣きながら、 |
to notamahe ba, Menoto, uti-naki te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 「 雪間なき吉野の山を訪ねても 心のかよふ跡絶えめやは」 |
「雪の消える間もない吉野の山奥であろうとも必ず訪ねて行って 心の通う手紙を絶やすことは決してしません」 |
雪間なき 心の通ふ跡絶えめやは |
"Yukima naki Yosino no yama wo tadune te mo kokoro no kayohu ato taye me yaha |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | と言ひ慰む。 |
と言って慰める。 |
と慰めるのであった。 |
to ihi nagusam. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 明石の母子の雪の別れ |
1-4 Parting daughter from mother in snow days |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | この雪すこし解けて渡りたまへり。例は待ちきこゆるに、 さならむとおぼゆることにより、胸うちつぶれて、 人やりならず、おぼゆ。 |
この雪が少し解けてお越しになった。いつもはお待ち申し上げているのに、きっとそうであろうと思われるために、胸がどきりとして、誰のせいでもない、自分の身分低いせいだと思わずにはいられない。 |
この雪が少し解けたころに源氏が来た。平生は待たれる人であったが、今度は姫君をつれて行かれるかと思うことで、源氏の訪れに胸騒ぎのする明石であった。 |
Kono yuki sukosi toke te watari tamahe ri. Rei ha mati kikoyuru ni, sa nara m to oboyuru koto ni yori, mune uti-tubure te, hitoyarinara zu, oboyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 「 わが心にこそあらめ。いなびきこえむをしひてやは、あぢきな」とおぼゆれど、「軽々しきやうなり」と、せめて思ひ返す。 |
「自分の一存によるのだわ。お断り申し上げたら無理はなさるまい。つまらないことを」と思わずにはいられないが、「軽率なようなことだわ」と、無理に思い返す。 |
自分の意志で決まることである、謝絶すればしいてとはお言いにならないはずである、自分がしっかりとしていればよいのであると、こんな気も明石はしたが、約束を変更することなどは軽率に思われることであると反省した。 |
"Waga kokoro ni koso ara me. Inabi kikoye m wo sihite yaha, adiki na!" to oboyure do, "Karugarusiki yau nari." to, semete omohikahesu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | いとうつくしげにて、 前にゐたまへるを見たまふに、 |
とてもかわいらしくて、前に座っていらっしゃるのを御覧になると、 |
美しい顔をして前にすわっている子を見て源氏は、 |
Ito utukusige ni te, mahe ni wi tamahe ru wo mi tamahu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 「 おろかには思ひがたかりける人の宿世かな」 |
「おろそかには思えない宿縁の人だなあ」 |
この子が間に生まれた明石と自分の因縁は並み並みのものではないと思った。 |
"Oroka ni ha omohi gatakari keru hito no sukuse kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | と思ほす。この春より ▼ 生ふす御髪、 尼削ぎのほどにて ★、ゆらゆらとめでたく、つらつき、まみの薫れるほどなど、言へばさらなり。よそのものに思ひやらむほどの ▼ 心の闇、推し量りたまふに、いと心苦しければ、 うち返しのたまひ明かす。 |
とお思いになる。今年の春からのばしている御髪、尼削ぎ程度になって、ゆらゆらとしてみごとで、顔の表情、目もとのほんのりとした美しさなど、いまさら言うまでもない。他人の養女にして遠くから眺める母親の心惑いを推量なさると、まことに気の毒なので、繰り返して安心するように言って夜を明かす。 |
今年から伸ばした髪がもう肩先にかかるほどになっていて、ゆらゆらとみごとであった。顔つき、目つきのはなやかな美しさも類のない幼女である。これを手放すことでどんなに |
to omohosu. Kono haru yori ohusu migusi, amasogi no hodo nite, yurayura to medetaku, turatuki, mami no kawore ru hodo nado, ihe ba sara nari. Yoso no mono ni omohiyara m hodo no kokoro no yami, osihakari tamahu ni, ito kurusikere ba, utikahesi notamahi akasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 「 何か。かく口惜しき身のほどならずだにもてなしたまはば」 |
「いいえ。取るに足りない身分でないようにお持てなしさえいただけしましたら」 |
「いいえ、それでいいと思っております。私の生みましたという傷も隠されてしまいますほどにしてやっていただかれれば」 |
"Nanika? Kaku kutiwosiki mi no hodo nara zu dani motenasi tamaha ba." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | と聞こゆるものから、念じあへずうち泣くけはひ、 あはれなり。 |
と申し上げるものの、堪え切れずにほろっと泣く様子、気の毒である。 |
と言いながらも、忍びきれずに泣く明石が哀れであった。 |
to kikoyuru monokara, nenzi ahe zu uti-naku kehahi, ahare nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
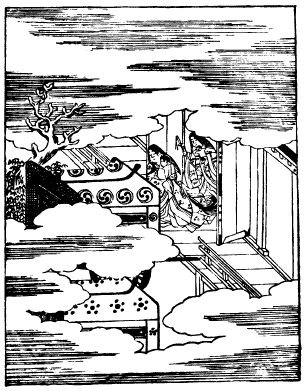 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | 姫君は、何心もなく、 御車に乗らむことを急ぎたまふ。寄せたる所に、 母君みづから抱きて出でたまへり。片言の、声はいとうつくしうて、袖をとらへて、「 乗りたまへ」と引くも、いみじうおぼえて、 |
姫君は、無邪気に、お車に乗ることをお急ぎになる。寄せてある所に、母君自身抱いて出ていらっしゃった。片言で、声はとてもかわいらしくて、袖をつかまえて、「お乗りなさい」と引っ張るのも、ひどく堪らなく悲しくて、 |
姫君は無邪気に父君といっしょに車へ早く乗りたがった。車の寄せられてある所へ明石は自身で姫君を抱いて出た。片言の美しい声で、 |
Himegimi ha, nanigokoro mo naku, mi-kuruma ni nora m koto wo isogi tamahu. Yose taru tokoro ni, Hahagimi midukara idaki te ide tamahe ri. Katakoto no, kowe ha ito utukusiu te, sode wo torahe te, "Nori tamahe." to hiku mo, imiziu oboye te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | 「 末遠き二葉の松に引き別れ いつか木高きかげを見るべき」 |
「幼い姫君にお別れしていつになったら 立派に成長した姿を見ることができるのでしょう」 |
末遠き二葉の松に引き分かれ いつか木高きかげを見るべき |
"Suwe tohoki hutaba no matu ni hiki-wakare ituka kodakaki kage wo miru beki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | えも言ひやらず、いみじう泣けば、 |
最後まで言い切れず、ひどく泣くので、 |
とよくも言われないままで非常に明石は泣いた。 |
E mo ihiyara zu, imiziu nake ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | 「 さりや。あな苦し」と思して、 |
「無理もない。ああ、気の毒な」とお思いになって、 |
こんなことも想像していたことである、心苦しいことをすることになったと源氏は |
"Sariya. Ana kurusi!" to obosi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 「 生ひそめし根も深ければ武隈の ★ 松に小松の千代をならべむ |
「生まれてきた因縁も深いのだから いづれ一緒に暮らせるようになりましょう |
「 松に小松の千代を並べん |
"Ohi some si ne mo hukakere ba Takekuma no matu ni komatu no tiyo wo narabe m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.13 | のどかにを」 |
安心なさい」 |
気を長くお待ちなさい」 |
nodoka ni wo!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.14 | と、慰めたまふ。さることとは思ひ静むれど、えなむ堪へざりける。 乳母の少将とて、あてやかなる人ばかり、御佩刀、天児やうの物取りて乗る。人だまひによろしき若人、童女など乗せて、 御送りに参らす。 |
と、慰めなさる。そうなることとは思って気持ちを落ち着けるが、とても堪えきれないのであった。乳母の少将と言った、気品のある女房だけが、御佩刀、天児のような物を持って乗る。お供の車には見苦しくない若い女房、童女などを乗せて、お見送りに行かせた。 |
と慰めるほかはないのである。道理はよくわかっていて抑制しようとしても |
to, nagusame tamahu. Saru koto to ha omohi sidumure do, e nam tahe zari keru. Menoto no Seusyau tote, ateyaka naru hito bakari, mihakasi, amagatu yau no mono tori te noru. Hitodamahi ni yorosiki wakaudo, waraha nado nose te, ohom-okuri ni mawirasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.15 | 道すがら、とまりつる人の心苦しさを、「 いかに。罪や得らむ」と思す。 |
道中、後に残った人の気の毒さを、「どんなにつらかろう。罪を得ることだろうか」とお思いになる。 |
源氏は道々も明石の心を思って罪を作ることに知らず知らず自分はなったかとも思った。 |
Mitisugara, tomari turu hito no kokorogurusisa wo, "Ikani? Tumi ya u ram." to obosu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 第五段 姫君、二条院へ到着 |
1-5 Akashi's daughter is adopted into Murasaki in Nijo-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 | 暗うおはし着きて、御車寄するより、はなやかにけはひことなるを、田舎びたる心地どもは、「 はしたなくてや交じらはむ」と思ひつれど、 西表をことにしつらはせたまひて、小さき御調度ども、うつくしげに調へさせたまへり。乳母の局には、西の渡殿の、北に当れるをせさせたまへり。 |
暗くなってお着きになって、お車を寄せるや、華やかな感じ格別なので、田舎暮らしに慣れた人々の心地には、「さぞや、きまりの悪い奉公をすることになろうか」と思ったが、西面の部屋を特別に用意させなさって、数々の小さいお道具類をかわいらしげに準備させておありになった。乳母の部屋には、西の渡殿の北側に当たる所を用意させておありになった。 |
暗くなってから着いた二条の院のはなやかな空気はどこにもあふれるばかりに見えて、田舎に |
Kurau ohasi tuki te, mi-kuruma yosuru yori, hanayaka ni kehahi koto naru wo, winakabi taru kokoti-domo ha, "Hasitanaku te ya maziraha m?" to omohi ture do, nisiomote wo koto ni siturahase tamahi te, tihisaki ohom-deudo-domo, utukusige ni totonohe sase tamahe ri. Menoto no tubone ni ha, nisi no watadono no, kita ni atare ru wo se sase tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.2 | 若君は、道にて寝たまひにけり。抱き下ろされて、泣きなどはしたまはず。こなたにて御くだもの参りなどしたまへど、やうやう見めぐらして、母君の見えぬをもとめて、らうたげにうちひそみたまへば、乳母召し出でて、慰め紛らはしきこえたまふ。 |
若君は、途中でお眠りになってしまっていた。抱きおろされても、泣いたりなどなさらない。こちらでお菓子をお召し上がりなどなさるが、だんだんと見回して、母君が見えないのを探して、いじらしげにべそかいていらっしゃるので、乳母をお呼び出しになって、慰めたり気を紛らわしてさし上げなさる。 |
姫君は途中で眠ってしまったのである。抱きおろされて目がさめた時にも泣きなどはしなかった。夫人の居間で菓子を食べなどしていたが、そのうちあたりを見まわして母のいないことに気がつくと、かわいいふうに不安な表情を見せた。源氏は乳母を呼んでなだめさせた。 |
Wakagimi ha, miti nite ne tamahi ni keri. Idaki orosa re te, naki nado ha si tamaha zu. Konata nite ohom-kudamono mawiri nado si tamahe do, yauyau mi megurasi te, Hahagimi no miye nu wo motome te, rautage ni uti-hisomi tamahe ba, Menoto mesiide te, nagusame magirahasi kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.3 | 「 山里のつれづれ、ましていかに」と思しやるはいとほしけれど、 明け暮れ思すさまにかしづきつつ、見たまふは、 ものあひたる心地したまふらむ。 |
「山里の所在なさは、以前にもましてどんなにであろうか」とお思いやりになると気の毒であるが、朝な夕なにお思いどおりにお世話しいしい、それを御覧になるのは、満足のいく心地がなさるだろう。 |
残された母親はましてどんなに悲しがっていることであろうと、想像されることは、源氏に心苦しいことであったが、こうして最愛の妻と二人でこのかわいい子をこれから育てていくことは非常な幸福なことであるとも思った。 |
"Yamazato no turedure, masite, ikani?" to obosiyaru ha itohosikere do, akekure obosu sama ni kasiduki tutu, mi tamahu ha, mono ahi taru kokoti si tamahu ram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.4 | 「 いかにぞや、人の思ふべき瑕 なきことは、このわたりに出でおはせで」 |
「どうしてなのか、世間が非難する欠点のない子は、こちらにはお生まれにならないで」 |
どうしてあの人に生まれて、この人に生まれてこなかったか、自分の娘として完全に |
"Ikani zo ya? Hito no omohu beki kizu naki koto ha, kono watari ni ide ohase de." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.5 | と、口惜しく思さる。 |
と、残念にお思いになる。 |
さすがに残念にも源氏は思うのであった。 |
to, kutiwosiku obosa ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.6 | しばしは、人びともとめて泣きなどしたまひしかど、おほかた心やすくをかしき心ざまなれば、 上にいとよくつき睦びきこえたまへれば、「 いみじううつくしきもの得たり」と思しけり。こと事なく抱き扱ひ、もてあそびきこえたまひて、乳母も、おのづから近う仕うまつり馴れにけり。また、 やむごとなき人の乳ある、添へて参りたまふ。 |
しばらくの間は、女房たちを探して泣いたりなどなさったが、だいたいが素直でかわいらしい性質なので、上にたいそうよく懐いてお慕いになるので、「とてもかわいらしい子を得た」とお思いになった。余念もなく抱いたり、あやしなさったりして、乳母も、自然とお側近くにお仕えするように慣れてしまった。また、身分の高い人で乳の出る人を、加えてお仕えなさる。 |
当座は母や祖母や、大井の家で見 |
Sibasi ha, hitobito motome te naki nado si tamahi sika do, ohokata kokoroyasuku wokasiki kokorozama nare ba, Uhe ni ito yoku tuki mutubi kikoye tamahe re ba, "Imiziu utukusiki mono e tari." to obosi keri. Kotogoto naku idaki atukahi, moteasobi kikoye tamahi te, Menoto mo, onodukara tikau tukaumaturi nare ni keri. Mata, yamgotonaki hito no ti aru, sohe te mawiri tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.7 | 御袴着は、何ばかりわざと思しいそぐことはなけれど、けしきことなり。御しつらひ、雛遊びの心地してをかしう見ゆ。参りたまへる客人ども、ただ明け暮れのけぢめしなければ、あながちに目も立たざりき。ただ、姫君の襷引き結ひたまへる胸つきぞ、うつくしげさ添ひて 見えたまひつる。 |
御袴着のお祝いは、どれほども特別にご準備なさることもないが、その儀式は格別である。お飾り付けは、雛遊びを思わせる感じでかわいらしく見える。参上なさったお客たち、常日頃からも来客で賑わっているので、特に目立つこともなかった。ただ、姫君が襷を掛けていらっしゃる胸元が、かわいらしさが加わってお見えになった。 |
|
Ohom-hakamagi ha, nani bakari wazato obosi isogu koto ha nakere do, kesiki koto nari. Ohom-siturahi, hihinaasobi no kokoti si te wokasiu miyu. Mawiri tamahe ru marauto-domo, tada akekure no kedime si nakere ba, anagati ni me mo tata zari ki. Tada, Himegimi no tasuki hiki-yuhi tamahe ru munetuki zo, utukusigesa sohi te miye tamahi turu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | 第六段 歳末の大堰の明石 |
1-6 Akashi's lonely days in the year-end |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.1 | 大堰には、尽きせず恋しきにも、 身のおこたりを嘆き添へたり。さこそ言ひしか、尼君もいとど涙もろなれど、かくもてかしづかれたまふを聞くはうれしかりけり。 何ごとをか、なかなか訪らひきこえたまはむ、ただ御方の人びとに、乳母よりはじめて、世になき色あひを思ひいそぎてぞ、 贈りきこえたまひける。 |
大堰では、いつまでも恋しく思われるにつけ、わが身のつたなさを嘆き加えていた。そうは言ったものの、尼君もひとしお涙もろくなっているが、このように大切にされていらっしゃるのを聞くのは嬉しかった。いったい、どんなことを、なまじお見舞い申し上げなされようか、ただ、お付きの人々に、乳母をはじめとして、非常に立派な色合いの装束を思い立って、準備してお贈り申し上げなさるのであった。 |
大井の山荘では毎日子を恋しがって明石が泣いていた。自身の愛が足らず、考えが足りなかったようにも後悔していた。尼君も泣いてばかりいたが、姫君の大事がられている消息の伝わってくることはこの人にもうれしかった。十分にされていて袴着の贈り物などここから持たせてやる必要は何もなさそうに思われたので、姫君づきの女房たちに、乳母をはじめ新しい一重ねずつの華美な衣裳を |
Ohowi ni ha, tuki se zu kohisiki ni mo, mi no okotari wo nageki sohe tari. Sakoso ihi sika, Amagimi mo itodo namida moro nare do, kaku motekasiduka re tamahu wo kiku ha uresikari keri. Nanigoto wo ka, nakanaka toburahi kikoye tamaha m, tada Ohomkata no hitobito ni, Menoto yori hazime te, yo ni naki iroahi wo omohi isogi te zo, okuri kikoye tamahi keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.2 | 「 待ち遠ならむも、いとどさればよ」と思はむに、いとほしければ、年の内に忍びて渡りたまへり。 |
「訪れが間遠になるのも、ますます、思ったとおりだ」と思うだろうと、気の毒なので、年の内にこっそりとおいでになった。 |
子さえ取ればあとは無用視するように女が思わないかと気がかりに思って年内にまた源氏は大井へ行った。 |
"Matidoho nara m mo, itodo sareba yo." to omoha m ni, itohosikere ba, tosi no uti ni sinobi te watari tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.3 | いとどさびしき住まひに、明け暮れのかしづきぐさをさへ離れきこえて、思ふらむことの心苦しければ、御文なども絶え間なく遣はす。 |
ますます寂しい生活で、朝な夕なのお世話する相手にさえお別れ申して、寂しい思いをしていることが気の毒なので、お手紙なども絶え間なくお遣わしになる。 |
寂しい山荘住まいをして、唯一の慰めであった子供に離れた女に同情して源氏は絶え間なく手紙を送っていた。 |
Itodo sabisiki sumahi ni, akekure no kasidukigusa wo sahe hanare kikoye te, omohu ram koto no kokorogurusikere ba, ohom-humi nado mo, tayema naku tukahasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6.4 | 女君も、今はことに 怨じきこえたまはず、うつくしき人に罪ゆるしきこえたまへり。 |
女君も、今では特にお恨み申し上げなさらず、かわいらしい姫君に免じて大目に見てさし上げていらっしゃった。 |
夫人ももうこのごろではかわいい人に免じて恨むことが少なくなった。 |
Womnagimi mo, ima ha koto ni wenzi kikoye tamaha zu, utukusiki hito ni tumi yurusi kikoye tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 10/27/2009(ver.2-2) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 10/27/2009(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 7/15/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 10/27/2009 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 4.00: Copyright (c) 2003,2024 宮脇文経