第三十二帖 梅枝 |
32 MUMEGAYE (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の太政大臣時代 三十九歳一月から二月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo-Daijin era, from January to February at the age of 39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 第一章 光る源氏の物語 薫物合せ |
1 Tale of Hikaru-Genji Playing a comparison of incense |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 第一段 六条院の薫物合せの準備 |
1-1 Genji prepares a playing comparison of incense at Rokujo-in |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | 御裳着のこと、思しいそぐ御心おきて、世の常ならず。 春宮も同じ二月に、御かうぶりのことあるべければ、 やがて御参りもうち続くべきにや。 |
御裳着の儀式、ご準備なさるお心づかい、並々ではない。春宮も同じ二月に、御元服の儀式がある予定なので、そのまま御入内も続くのであろうか。 |
源氏が十一歳の姫君の |
Ohom-mogi no koto, obosi isogu mi-kokorookite, yo no tune nara zu. Touguu mo onazi Kisaragi ni, ohom-kauburi no koto aru bekere ba, yagate ohom-mawiri mo uti-tuduku beki ni ya? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | 正月の晦日なれば、公私のどやかなるころほひに、薫物合はせたまふ。 大弐の奉れる香ども 御覧ずるに、「 なほ、いにしへのには劣りてやあらむ」と思して、二条院の御倉開けさせたまひて、唐の物ども取り渡させたまひて、御覧じ比ぶるに、 |
正月の月末なので、公私ともにのんびりとした頃に、薫物合わせをなさる。大宰大弐が献上したいくつもの香を御覧になると、「やはり、昔の香には劣っていようか」とお思いになって、二条院の御倉を開けさせなさって、唐の品々を取り寄せなさって、ご比較なさると、 |
一月の末のことで、公私とも |
Syaugwatu no tugomori nare ba, ohoyake watakusi nodoyaka naru korohohi ni, takimono ahase tamahu. Daini no tatemature ru kau-domo goranzuru ni, "Naho, inisihe no ni ha otori te ya ara m?" to obosi te, Nideu-no-win no mi-kura ake sase tamahi te, Kara no mono-domo tori-watasa se tamahi te, goranzi kuraburu ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 | 「 錦、綾なども、なほ古きものこそなつかしうこまやかにはありけれ」 |
「錦、綾なども、やはり古い物が好ましく上品であった」 |
「織物などもやはり古い物のほうに芸術的なものが多い」 |
"Nisiki, aya nado mo, naho huruki mono koso natukasiu komayaka ni ha ari kere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 | とて、近き御しつらひの、物の覆ひ、敷物、茵などの端どもに、 故院の御世の初めつ方、高麗人のたてまつれりける綾、緋金錦どもなど、今の世のものに似ず、なほさまざま御覧じあてつつせさせたまひて、 このたびの綾、羅などは、人びとに賜はす。 |
とおっしゃって、身近な調度類の、物の覆いや、敷物、座蒲団などの端々に、故院の御代の初め頃、高麗人が献上した綾や、緋金錦類など、今の世の物には比べ物にならず、さらにいろいろとご鑑定なさっては、今回の綾、羅などは、女房たちにご下賜なさる。 |
といって、式場用の物の |
tote, tikaki ohom-siturahi no, mono no ohohi, sikimono, sitone nado no hasi-domo ni, ko-Win no mi-yo no hazime-tu-kata, Komaudo no tatemature ri keru aya, higonki-domo nado, ima no yo no mono ni ni zu, naho samazama goranzi ate tutu se sase tamahi te, konotabi no aya, usumono nado ha, hitobito ni tamaha su. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.5 | 香どもは、昔今の、取り並べさせたまひて、御方々に配りたてまつらせたまふ。 |
数々の香は、昔のと今のを、取り揃えさせなさって、ご夫人方にお配り申し上げさせなさる。 |
香の原料に昔のと今のとを両方取り混ぜて六条院内の夫人たちと、源氏の尊敬する女友だちに送って、 |
Kau-domo ha, mukasi ima no, tori-narabe sase tamahi te, ohom-katagata ni kubari tatematura se tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.6 | 「 二種づつ合はせさせたまへ」 |
「二種類づつ調合なさって下さい」 |
二種類ずつの薫香を作られたい |
"Hutakusa dutu ahase sase tamahe." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.7 | と、 聞こえさせたまへり。贈り物、上達部の禄など、世になきさまに、 内にも外にも、ことしげくいとなみたまふに添へて、方々に選りととのへて、鉄臼の音耳 かしかましきころなり。 |
と、お願い申し上げさせなさった。贈物や、上達部への禄など、世にまたとないほどに、内にも外にも、お忙しくお作りなさるに加えて、それぞれに材料を選び準備して、鉄臼の音が喧しく聞こえる頃である。 |
と告げた。裳着の式日の贈り物、高官たちへの |
to, kikoye sase tamahe ri. Okuri-mono, Kamdatime no roku nado, yo ni naki sama ni, uti ni mo to ni mo, koto sigeku itonami tamahu ni sohe te, katagata ni eri totonohe te, kanausu no oto mimi kasikamasiki koro nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.8 | 大臣は、寝殿に離れおはしまして、 承和の御いましめの二つの方を ★、 いかでか御耳には伝へたまひけむ、心にしめて合はせたまふ。 |
大臣は、寝殿に離れていらっしゃって、承和の帝の御秘伝の二つの調合法を、どのようにしてお耳にお伝えなさったのであろうか、熱心にお作りになる。 |
源氏は南の町の寝殿へ、夫人の所から離れてこもりながら、どうして習得したのか承和の |
Otodo ha, Sinden ni hanare ohasimasi te, Zyouwa no ohom-imasime no hutatu no hau wo, ikadeka ohom-mimi ni ha tutahe tamahi kem, kokoro ni sime te ahase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.9 | 上は、東の中の放出に、 御しつらひことに深う しなさせたまひて、 八条の式部卿の御方を伝へて、 かたみに挑み合はせたまふほど、いみじう秘したまへば、 |
紫の上は、東の対の中の放出に、御設備を特別に厳重におさせになって、八条の式部卿の御調合法を伝えて、互いに競争して調合なさっている間に、たいそう秘密にしていらっしゃるので、 |
夫人は東の |
Uhe ha, himgasi no naka no Hanatiide ni, ohom-siturahi kotoni hukau si nasa se tamahi te, Hatideu-no-Sikibukyau no ohom-hau wo tutahe te, katamini idomi ahase tamahu hodo, imiziu hisi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.10 | 「 匂ひの深さ浅さも、勝ち負けの定めあるべし」 |
「匂いの深さ浅さも、勝負けの判定にしよう」 |
こうして夫婦の中にも、秘密をうかがわれまいと苦心する香の優劣を勝負にしよう |
"Nihohi no hukasa asasa mo, katimake no sadame aru besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.11 | と大臣のたまふ。 人の御親げなき御あらそひ心なり ★。 |
と大臣がおっしゃる。子を持つ親御らしくない競争心である。 |
と言っていた。姫君の親である人たちらしくない競争である。 |
to Otodo notamahu. Hito no ohom-oyage naki ohom-arasohi gokoro nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.12 | いづ方にも、御前にさぶらふ人あまたならず。御 調度どもも、そこらのきよらを尽くしたまへるなかにも、香壺の御筥どものやう、壺の姿、火取りの心ばへも、目馴れぬさまに、今めかしう、やう変へさせたまへるに、 所々の心を尽くしたまへらむ匂ひどもの、すぐれたらむどもを、かぎあはせて入れむと思すなりけり。 |
どちらにも、御前に伺候する女房は多くいない。御調度類も、多く善美を尽くしていらっしゃる中でも、いくつもの香壷の御箱の作り具合、壷の恰好、香炉の意匠も、見慣れない物で、当世風に、趣向を変えさせていらっしゃるのが、あちらこちらで一生懸命にお作りになったような香の中で、優れた幾種かを、匂いを比べた上で入れようとお考えなのである。 |
どの夫人の所にもこの調合の室に侍している女房は選ばれた少数の者であった。式用の小道具を精巧をきわめて製作させた中でも、特に香合の箱の形、 |
Idukata ni mo, omahe ni saburahu hito amata nara zu. Ohom-teudo-domo mo, sokora no kiyora wo tukusi tamahe ru naka ni mo, kaugo no ohom-hako-domo no yau, tubo no sugata, hitori no kokorobahe mo, menare nu sama ni, imamekasiu, yau kahe sase tamahe ru ni, tokorodokoro no kokoro wo tukusi tamahe ra m nihohi-domo no, sugure tara m domo wo, kagi ahase te ire m to obosu nari keri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 第二段 二月十日、薫物合せ |
1-2 The comparison of incense is done at February 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | 二月の十日、雨すこし降りて、御前近き紅梅盛りに、色も香も似るものなきほどに、 兵部卿宮渡りたまへり。 御いそぎの今日明日になりにけることども、訪らひきこえたまふ。昔より取り分きたる御仲なれば、隔てなく、そのこと かのこと、と聞こえあはせたまひて、 花をめでつつおはするほどに、 前斎院よりとて、 散りすきたる梅の枝につけたる御文持て参れり。宮、 聞こしめすこともあれば、 |
二月の十日、雨が少し降って、御前近くの紅梅の盛りに、色も香も他に似る物がない頃に、兵部卿宮がお越しになった。御裳着の支度が今日明日に迫ってお忙しいことについて、ご訪問なさる。昔から特別にお仲が好いので、隠し隔てなく、あの事この事、とご相談なさって、紅梅の花を賞美なさっていらっしゃるところに、前斎院からと言って、散って薄くなった梅の枝に結び付けられているお手紙を持ってまいった。宮、お聞きになっていたこともあるので、 |
二月の十日であった。雨が少し降って、前の庭の紅梅が色も香もすぐれた名木ぶりを発揮している時に、 |
Kisaragi no towoka, ame sukosi huri te, omahe tikaki koubai sakari ni, iro mo ka mo niru mono naki hodo ni, Hyaubukyau-no-Miya watari tamahe ri. Ohom-isogi no kehu asu ni nari ni keru koto-domo, toburahi kikoye tamahu. Mukasi yori toriwaki taru ohom-naka nare ba, hedate naku, sono koto kano koto, to kikoye ahase tamahi te, hana wo mede tutu ohasuru hodo ni, saki-no-Saiwin yori tote, tiri suki taru mume no eda ni tuke taru ohom-humi mote mawire ri. Miya, kikosimesu koto mo are ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
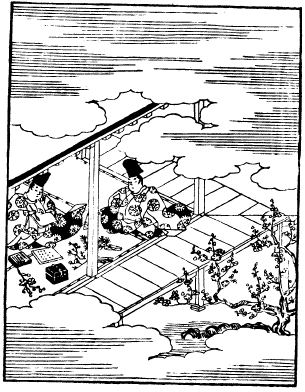 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | 「 いかなる御消息のすすみ参れるにか」 |
「どのようなお手紙があちらから参ったのでしょうか」 |
「どんなおたよりがあちらから来たのでしょう」 |
"Ikanaru ohom-seusoko no susumi mawire ru ni ka?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 | とて、をかしと思したれば、ほほ笑みて、 |
とおっしゃって、興味をお持ちになっているので、にっこりして、 |
とお言いになって、好奇心を起こしておいでになるふうの見えるのを、源氏はただ、 |
tote, wokasi to obosi tare ba, hohowemi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.4 | 「 いと馴れ馴れしきこと聞こえつけたりしを、まめやかに急ぎものしたまへるなめり」 |
「たいそう無遠慮なことをお願い申し上げたところ、几帳面に急いでお作りになったのでしょう」 |
「失礼なお願いを私がしましたのを、すぐにその香を作ってくだすったのです」 |
"Ito narenaresiki koto kikoye tuke tari si wo, mameyaka ni isogi monosi tamahe ru na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.5 | とて、御文は引き隠したまひつ。 |
とおっしゃって、お手紙はお隠しになった。 |
こう言って、お手紙は隠してしまった。 |
tote, ohom-humi ha hiki-kakusi tamahi tu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.6 | 沈の筥に、 瑠璃の坏二つ据ゑて、大きにまろがしつつ入れたまへり。心葉、紺瑠璃には五葉の枝、白きには 梅を選りて、同じくひき結びたる糸のさまも、 なよびやかになまめかしうぞしたまへる。 |
沈の箱に、瑠璃の香壷を二つ置いて、大きく丸めてお入れになってある。心葉は、紺瑠璃のには五葉の枝を、白いのには白梅を彫って、同じように結んである糸の様子も、優美で女性的にお作りになってある。 |
|
Din no hako ni, ruri no tuki hutatu suwe te, ohoki ni marogasi tutu ire tamahe ri. Kokoroba, konruri ni ha goehu no eda, siroki ni ha mume wo eri te, onaziku hiki musubi taru ito no sama mo, nayobiyaka ni namamekasiu zo si tamahe ru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.7 | 「 艶あるもののさまかな」 |
「優雅な感じのする出来ばえですね」 |
「 |
"En aru mono no sama kana!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.8 | とて、 御目止めたまへるに、 |
とおっしゃって、お目を止めなさると、 |
と宮は言って、ながめておいでになったが、 |
tote, ohom-me tome tamahe ru ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.9 | 「 花の香は散りにし枝にとまらねど うつらむ袖に浅くしまめや」 |
「花の香りは散ってしまった枝には残っていませんが、 香を焚きしめた袖には深く残るでしょう」 |
花の香は散りにし うつらん袖に浅くしまめや |
"Hana no ka ha tiri ni si eda ni tomara ne do utura m sode ni asaku sima me ya |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.10 | ほのかなるを御覧じつけて、宮はことことしう誦じたまふ。 |
薄墨のほんのりとした筆跡を御覧になって、宮は仰々しく口ずさみなさる。 |
という歌が小さく書かれてあるのにお目がついて、わざとらしくお読み上げになった。 |
Honoka naru wo goranzi tuke te, Miya ha kotokotosiu zuzi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.11 | 宰相中将、 御使尋ねとどめさせたまひて、いたう酔はしたまふ。紅梅襲の唐の細長添へたる女の装束かづけたまふ。 御返りもその色の紙にて、 御前の花を折らせてつけさせたまふ。 |
宰相中将、お使いの者を捜し出して引き止めさせなさって、たいそう酔わせなさる。紅梅襲の唐の細長を添えた女装束をお与えになる。お返事も同じ紙の色で、御前の花を折らせてお付けになる。 |
宰相の中将が来た使いを捜させ |
Saisyau-no-Tyuuzyau, ohom-tukahi tadune todome sase tamahi te, itau yohasi tamahu. Koubaigasane no kara no hosonaga sohe taru womna no sauzoku kaduke tamahu. Ohom-kaheri mo sono iro no kami nite, omahe no hana wo wora se te tuke sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.12 | 宮、 |
宮、 |
Miya, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.13 | 「 うちのこと思ひやらるる御文かな。何ごとの隠ろへあるにか、深く隠したまふ」 |
「どんな内容か気になるお手紙ですね。どのような秘密があるのか、深くお隠しになさるな」 |
「何だか内容の知りたくなるお手紙ですが、なぜそんなに秘密になさるのだろう」 |
"Uti no koto omohiyara ruru ohom-humi kana! Nanigoto no kakurohe aru ni ka, hukaku kakusi tamahu." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.14 | と恨みて、いとゆかしと思したり。 |
と恨んで、ひどく見たがっていらっしゃった。 |
と言って、宮は見たがっておいでになる。 |
to urami te, ito yukasi to obosi tari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.15 | 「 何ごとかはべらむ。隈々しく思したるこそ、苦しけれ」 |
「何でもありません。秘密があるようにお思いになるのが、かえって迷惑です」 |
「何があるものですか、そんなふうによけいな想像をなさるから困るのです」 |
"Nanigoto ka habera m? Kumagumasiku obosi taru koso, kurusikere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.16 | とて、御硯のついでに、 |
とおっしゃって、御筆のついでに、 |
と言って、斎院へ今書いた歌をまた紙にしたためて宮へお見せした。 |
tote, ohom-suzuri no tuide ni, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.17 | 「 花の枝にいとど心をしむるかな ★ 人のとがめむ香をばつつめど」 |
「花の枝にますます心を惹かれることよ 人が咎めるだろうと隠しているが」 |
花の 人のとがむる香をばつつめど |
"Hana no ye ni itodo kokoro wo simuru kana Hito no togame m ka wo ba tutume do |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.18 | とやありつらむ。 |
とでもあったのであろうか。 |
というのであるらしい。 |
to ya ari tu ram. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.19 | 「 まめやかには、好き好きしきやうなれど、 またもなかめる人の上にて、これこそはことわりのいとなみなめれと、 思ひたまへなしてなむ。 いと醜ければ、疎き人はかたはらいたさに、 中宮まかでさせたてまつりてと 思ひたまふる ★。親しきほどに馴れきこえかよへど、恥づかしきところの深うおはする宮なれば、 何ごとも世の常にて見せたてまつらむ、かたじけなくてなむ」 |
「実のところ、物好きなようですが、二人といない娘のことですから、こうするのが当然の催しであろうと、存じましてね。たいそう不器量ですから、疎遠な方にはきまりが悪いので、中宮を御退出おさせ申し上げてと存じております。親しい間柄でお慣れ申し上げているが、気の置ける点が深くおありの宮なので、何事も世間一般の有様でお見せ申しては、恐れ多いことですから」 |
「少し物好きなようですが、一人娘の成年式だからやむをえないと自分では |
"Mameyaka ni ha, sukizukisiki yau nare do, mata mo nakame ru hito no uhe nite, kore koso ha kotowari no itonami na' mere to, omohi tamahe nasi te nam. Ito minikukere ba, utoki hito ha katahara itasa ni, Tyuuguu makade sase tatematuri te to, omohi tamahuru. Sitasiki hodo ni nare kikoye kayohe do, hadukasiki tokoro no hukau ohasuru Miya nare ba, nanigoto mo yo no tune nite mise tatematura m, katazikenaku te nam." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.20 | など、聞こえたまふ。 |
などと、申し上げなさる。 |
などと源氏は言っていた。 |
nado, kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.21 | 「 あえものも、げに、かならず思し寄るべきことなりけり」 |
「あやかるためにも、おっしゃるとおり、きっとお考えになるはずのことなのでしたね」 |
「そうですね。あやかる人は選ばねばなりませんね。それにはこの上もない方ですよ」 |
"Ayemono mo, geni, kanarazu obosi yoru beki koto nari keri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.22 | と、ことわり申したまふ。 |
と、ご判断申し上げなさる。 |
と宮は源氏の計らいの当を得ていることをお言いになった。 |
to, kotowari mausi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 第三段 御方々の薫物 |
1-3 Wives of Genji make incense for playing comparison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.1 | このついでに、御方々の合はせたまふども、おのおの御使して、 |
この機会に、ご夫人方がご調合なさった薫物を、それぞれお使いを出して、 |
前斎院から香の届けられたことと、宮のおいでになったのを機会にして、夫人らの調製した |
Kono tuide ni, ohom-katagata no ahase tamahu domo, onoono ohom-tukahi site, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.2 | 「 この夕暮れのしめりにこころみむ」 |
「今日の夕方の雨じめりに試してみよう」 |
「湿りけのある今日の空気が香の試験に適していると思いますから」 |
"Kono yuhugure no simeri ni kokoromi m." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.3 | と聞こえたまへれば、さまざまをかしうしなして 奉りたまへり。 |
とお話申し上げなさっていたので、それぞれに趣向を凝らして差し上げなさった。 |
と言いやられたのである。夫人たちからは、いろいろに作られた香が、いろいろに飾られて来た。 |
to kikoye tamahe re ba, samazama wokasiu si nasi te tatematuri tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.4 | 「 これ分かせたまへ。誰れにか見せむ ★」 |
「これらをご判定ください。あなたでなくて誰に出来ましょう」 |
「これを審判してください。あなたのほかに頼む人はない」 |
"Kore waka se tamahe. Tare ni ka mise m?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.5 | と聞こえたまひて、御火取りども召して、こころみさせたまふ。 |
と申し上げなさって、いくつもの御香炉を召して、お試しになる。 |
こう源氏は言って、火入れなどを取り寄せて香をたき試みた。 |
to kikoye tamahi te, ohom-hitori-domo mesi te, kokoromi sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.6 | 「 知る人にもあらずや」 |
「知る人というほどの者ではありませんが」 |
「知る人(君ならでたれにか見せむ梅の花色をも香をも知る人ぞ知る)でもないのですがね」 |
"Siru hito ni mo ara zu ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.7 | と卑下したまへど、言ひ知らぬ匂ひどもの、進み遅れたる香一種などが、いささかの咎を分きて、あながちに劣りまさりのけぢめをおきたまふ。 かのわが御二種のは、今ぞ取う出させたまふ。 |
と謙遜なさるが、何とも言えない匂いの中で、香りの強い物や弱い物の一つなどが、わずかの欠点を識別して、強いて優劣の区別をお付けになる。あのご自分の二種の香は、今お取り出させになる。 |
と宮は |
to hige si tamahe do, ihisira nu nihohi-domo no, susumi okure taru kau hitokusa nado ga, isasaka no toga wo waki te, anagati ni otori masari no kedime wo oki tamahu. Kano waga ohom-hutakusa no ha, ima zo toude sase tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.8 | 右近の陣の御溝水のほとりになずらへて、西の渡殿の下より出づる汀近う 埋ませたまへるを、 惟光の宰相の子の兵衛尉、堀りて参れり。宰相中将、取りて伝へ参らせたまふ。宮、 |
右近の陣の御溝水の辺に埋める例に倣って、西の渡殿の下から湧き出る遣水の近くに埋めさせなさっていたのを、惟光の宰相の子の兵衛尉が、掘り出して参上した。宰相中将が、受け取って差し上げさせなさる。宮、 |
|
Ukon no din no mi-kahamidu no hotori ni nazurahe te, nisi no watadono no sita yori iduru migiha tikau uduma se tamahe ru wo, Koremitu-no-Saisyau no ko no Hyauwe-no-Zyou, hori te mawire ri. Saisyau-no-Tyuuzyau, tori te tutahe mawira se tamahu. Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.9 | 「 いと苦しき判者にも当たりてはべるかな。いと煙たしや」 |
「とても難しい判者に任命されたものですね。とても煙たくて閉口しますよ」 |
「苦しい審判者になったものですよ。第一けむい」 |
"Ito kurusiki hanza ni mo atari te haberu kana! Ito kebutasi ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.10 | と、悩みたまふ。 同じうこそは、いづくにも散りつつ広ごるべかめるを、人びとの心々に合はせたまへる、深さ浅さを、かぎあはせたまへるに、いと興あること多かり。 |
と、お困りになる。同じのは、どこにでも伝わって広がっているようだが、それぞれの好みで調合なさった、深さ浅さを、聞き分けて御覧になると、とても興味深いものが数多かった。 |
と宮は苦しそうに言っておいでになった。同じ法が広く伝えられていても、個人個人の趣味がそれに加わってでき上がった薫香のよさ悪さを比較して |
to, nayami tamahu. Onaziu koso ha, iduku ni mo tiri tutu hirogoru beka' meru wo, hitobito no kokorogokoro ni aha se tamahe ru, hukasa asasa wo, kagi ahase tamahe ru ni, ito kyou aru koto ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.11 | さらにいづれともなき中に、斎院の御黒方、 さいへども、心にくくしづやかなる匂ひ、ことなり。侍従は、大臣の 御は、 すぐれてなまめかしうなつかしき香なりと定めたまふ。 |
まったくどれと言えない香の中で、斎院の御黒方、そうは言っても、奥ゆかしく落ち着いた匂い、格別である。侍従の香は、大臣のその御香は、優れて優美でやさしい香りである、とご判定になさる。 |
どれが第一の物とも決められない中にも斎院のお作りになった |
Sarani idure to mo naki naka ni, Saiwin no ohom-Kurobau, sa ihe domo, kokoronikuku siduyaka naru nihohi, koto nari. Zizyuu ha, Otodo no ohom ha, sugure te namamekasiu natukasiki ka nari to sadame tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.12 | 対の上の御は、 三種ある中に、梅花、はなやかに今めかしう、すこしはやき心しつらひを添へて、めづらしき薫り加はれり。 |
対の上の御香は、三種ある中で、梅花の香が、ぱっと明るくて当世風で、少し鋭く匂い立つように工夫を加えて、珍しい香りが加わっていた。 |
紫の |
Tai-no-Uhe no ohom ha, mikusa aru naka ni, Baikwa, hanayaka ni imamekasiu, sukosi hayaki kokorositurahi wo sohe te, medurasiki kawori kuhahare ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.13 | 「 このころの風にたぐへむには、さらにこれにまさる匂ひあらじ ★」 |
「今頃の風に薫らせるには、まったくこれに優る匂いはあるまい」 |
「このごろの |
"Konokoro no kaze ni taguhe m ni ha, sarani kore ni masaru nihohi ara zi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.14 | とめでたまふ。 |
と賞美なさる。 |
と宮はおほめになる。 |
to mede tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.15 | 夏の御方には、人びとの、かう心々に挑みたまふなる中に、数々にも立ち出でずやと、 煙をさへ思ひ消えたまへる御心にて、ただ 荷葉を一種合はせたまへり。さま変はりしめやかなる香して、あはれになつかし。 |
夏の御方におかれては、このようにご夫人方が思い思いに競争なさっている中で、人並みにもなるまいと、煙にさえお考えにならないご気性で、ただ荷葉の香を一種調合なさった。一風変わって、しっとりした香りで、しみじみと心惹かれる。 |
|
Natu-no-Ohomkata ni ha, hitobito no, kau kokoro gokoro ni idomi tamahu naru naka ni, kazukazu ni mo tatiide zu ya to, keburi wo sahe omohi kiye tamahe ru ohom-kokoro nite, tada Kaehu wo hitokusa ahase tamahe ri. Sama kahari simeyaka naru ka site, ahare ni natukasi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.16 | 冬の御方にも、 時々によれる匂ひの定まれるに消たれむもあいなしと思して、薫衣香の方のすぐれたるは、 前の朱雀院のをうつさせたまひて、公忠朝臣の、ことに選び仕うまつれりし百歩の方など思ひ得て、 世に似ずなまめかしさを取り集めたる、心おきてすぐれたりと、いづれをも無徳ならず定めたまふを、 |
冬の御方におかれても、季節季節に基づいた香が決まっているから、負けるのもつまらないとお考えになって、薫衣香の調合法の素晴らしいのは、前の朱雀院のをお学びなさって、源公忠朝臣が、特別にお選び申した百歩の方などを思いついて、世間にない優美さを調合した、その考えが素晴らしいと、どれも悪い所がないように判定なさるのを、 |
冬の夫人である |
Huyu-no-ohomkata ni mo, tokidoki ni yore ru nihohi no sadamare ru ni keta re m mo ainasi to obosi te, Kunoekau no hau no sugure taru ha, saki no SyuzyakuWin no wo utusa se tamahi te, Kimtada-no-Asom no, kotoni erabi tukaumature ri si Hyakubu no hau nado omohi e te, yo ni ni zu namamekasisa wo tori-atume taru, kokorookite sugure tari to, idure wo mo mutoku nara zu sadame tamahu wo, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.17 | 「 心ぎたなき判者なめり」 |
「当たりさわりのない判者ですね」 |
「八方美人の審判者だ」 |
"Kokorogitanaki hanza na' meri." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3.18 | と聞こえたまふ。 |
と申し上げなさる。 |
と言って源氏は笑っていた。 |
to kikoye tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 第四段 薫物合せ後の饗宴 |
1-4 A banquet of the playing comparison of incense |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.1 | 月さし出でぬれば、大御酒など参りて、昔の御物語などしたまふ。 霞める月の影心にくきを、雨の名残の風すこし吹きて、花の香なつかしきに、御殿のあたり言ひ知らず匂ひ満ちて、人の御心地いと艶あり。 |
月が出たので、御酒などをお召し上がりになって、昔のお話などをなさる。霞んでいる月の光が奥ゆかしいところに、雨上がりの風が少し吹いて、梅の花の香りが優しく薫り、御殿の辺りに何とも言いようもなく匂い満ちて、皆のお気持ちはとてもうっとりしている。 |
月が出てきたので酒が座に運ばれて、宮と源氏は昔の話を始めておいでになった。うるんだ月の光の |
Tuki sasi-ide nure ba, ohomiki nado mawiri te, mukasi no ohom-monogatari nado si tamahu. Kasume ru tuki no kage kokoronikuki wo, ame no nagori no kaze sukosi huki te, hana no ka natukasiki ni, otodo no atari ihi-sira-zu nihohi miti te, hito no ohom-kokoti ito en ari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2 | 蔵人所の方にも、明日の御遊びのうちならしに、御琴どもの装束などして、殿上人などあまた参りて、をかしき笛の音ども聞こゆ。 |
蔵人所の方にも、明日の管弦の御遊の試演に、お琴類の準備などをして、殿上人などが大勢参上して、美しい幾種もの笛の音が聞こえて来る。 |
|
Kuraudodokoro no kata ni mo, asu no ohom-asobi no uti-narasi ni, ohom-koto-domo no sauzoku nado si te, Tenzyaubito nado amata mawiri te, wokasiki huwe no ne-domo kikoyu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.3 | 内の大殿の頭中将、弁少将なども、見参ばかりにてまかづるを、とどめさせたまひて、御琴ども召す。 |
内の大殿の頭中将、弁少将なども、挨拶だけで退出するのを、お止めさせになって、いくつも御琴をお取り寄せになる。 |
内大臣の子の |
Uti-no-Ohoidono no Tou-no-Tyuuzyau, Ben-no-Seusyau nado mo, genzam bakari nite makaduru wo, todome sase tamahi te, ohom-koto-domo mesu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.4 | 宮の御前に琵琶、大臣に 箏の御琴参りて、頭中将、和琴賜はりて、はなやかに掻きたてたるほど、いとおもしろく聞こゆ。宰相中将、横笛吹きたまふ。 折にあひたる調子、雲居とほるばかり吹きたてたり。弁少将、拍子取りて、「 梅が枝」出だしたるほど ★、 いとをかし。 童にて、韻塞ぎの折、「高砂」謡ひし君なり。宮も大臣もさしいらへしたまひて、ことことしからぬものから、をかしき夜の御遊びなり。 |
宮の御前に琵琶、大臣に箏の御琴を差し上げて、頭中将は、和琴を賜って、賑やかに合奏なさっているのは、たいそう興趣深く聞こえる。宰相中将、横笛をお吹きになる。季節にあった調べを、雲居に響くほど吹き立てた。弁少将は拍子を取って、「梅が枝」を謡い出したところ、たいそう興味深い。子供の時、韻塞ぎの折に、「高砂」を謡った君である。宮も大臣も一緒にお謡いになって、仰々しくはないが、趣のある夜の管弦の催しである。 |
頭中将は |
Miya no omahe ni biha, Otodo ni sau no ohom-koto mawiri te, Tou-no-Tyuuzyau, wagon tamahari te, hanayaka ni kaki-tate taru hodo, ito omosiroku kikoyu. Saisyau-no-Tyuuzyau, yokobue huki tamahu. Wori ni ahi taru teusi, kumowi tohoru bakari huki tate tari. Ben-no-Seusyau, hyausi tori te, mume-ga-e idasi taru hodo, ito wokasi. Waraha nite, winhutagi no wori, takasago utahi si Kimi nari. Miya mo Otodo mo sasi-irahe si tamahi te, kotokotosikara nu monokara, wokasiki yo no ohom-asobi nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.5 | 御土器参るに、宮、 |
お杯をお勧めになる時に、宮が、 |
酒杯がさされた時に、宮は、 |
Ohom-kaharake mawiru ni, Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.6 | 「 鴬の声にやいとどあくがれむ 心しめつる花のあたりに |
「鴬の声にますます魂が抜け出しそうです 心を惹かれた花の所では、 |
「うぐひすの声にやいとどあくがれん 心しめつる花のあたりに |
"Uguhisu no kowe ni ya itodo akugare m kokoro sime turu hana no atari ni |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.7 | ▼ 千代も経ぬべし」 |
千年も過ごしてしまいそうです」 |
千年もいたくなってます」 |
Tiyo mo he nu besi." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.8 | と聞こえたまへば、 |
とお詠み申し上げなさると、 |
と源氏へお言いになった。 |
to kikoye tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.9 | 「 色も香もうつるばかりにこの春は 花咲く宿をかれずもあらなむ」 |
「色艶も香りも移り染まるほどに、今年の春は 花の咲くわたしの家を絶えず訪れて下さい」 |
色も香もうつるばかりにこの春は 花咲く宿をかれずもあらなん |
"Iro mo ka mo uturu bakari ni kono haru ha hana saku yado wo kare zu mo ara nam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.10 | 頭中将に賜へば、取りて、宰相中将にさす。 |
頭中将におさずけになると、受けて、宰相中将に廻す。 |
と源氏は歌ってから、杯を頭の中将へさした。中将は杯を受けたあとで宰相の中将へ杯をまわした。 |
Tou-no-Tyuuzyau ni tamahe ba, tori te, Saisyau-no-Tyuuzyau ni sasu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.11 | 「 鴬のねぐらの枝もなびくまで なほ吹きとほせ夜半の笛竹」 |
「鴬のねぐらの枝もたわむほど 夜通し笛の音を吹き澄まして下さい」 |
うぐひすのねぐらの枝も なほ吹き通せ |
"Uguhisu no negura no eda mo nabiku made naho huki tohose yoha no huetake |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.12 | 宰相中将、 |
宰相中将は、 |
と頭の中将は歌ったのである。 |
Saisyau-no-Tyuuzyau, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.13 | 「 心ありて風の避くめる花の木に とりあへぬまで吹きや寄るべき |
「気づかって風が避けて吹くらしい梅の花の木に むやみに近づいて笛を吹いてよいものでしょうか |
「心ありて風のよぐめる花の木に とりあへぬまで吹きやよるべき |
"Kokoro ari te kaze no yoku meru hana no ki ni tori-ahe nu made huki ya yoru beki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.14 | 情けなく」 |
無風流ですね」 |
少しひどいでしょうね」 |
Nasakenaku." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.15 | と、皆うち笑ひたまふ。弁少将、 |
と言うと、皆お笑いになる。弁少将は、 |
と宰相中将が言うと皆笑った。弁の少将が、 |
to, mina uti warahi tamahu. Ben-no-Seusyau, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.16 | 「 霞だに月と花とを隔てずは ねぐらの鳥もほころびなまし」 |
「霞でさえ月と花とを隔てなければ ねぐらに帰る鳥も鳴き出すことでしょう」 |
かすみだに月と花とを隔てずば ねぐらの鳥もほころびなまし |
"Kasumi dani tuki to hana to wo hedate zu ha negura no tori mo hokorobi na masi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.17 | まことに、明け方になりてぞ、宮帰りたまふ。御贈り物に、みづからの御料の御直衣の御よそひ一領、手触れたまはぬ薫物二壺添へて、 御車にたてまつらせたまふ。宮、 |
ほんとうに、明け方になって、宮はお帰りになる。御贈物に、ご自身の御料の御直衣のご装束一揃い、手をおつけになっていない薫物を二壷添えて、お車までお届けになる。宮は、 |
と言った。長居のしたくなる所であるとお言いになったとおりに、宮は明け方になってお帰りになるのであった。源氏は贈り物に、自身のために作られてあった |
Makoto ni, akegata ni nari te zo, Miya kaheri tamahu. Ohom-okurimono ni, midukara no goreu no ohom-nahosi no ohom-yosohi hito-kudari, te hure tamaha nu takimono huta-tubo sohe te, ohom-kuruma ni tatematura se tamahu. Miya, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.18 | 「 花の香をえならぬ袖にうつしもて ことあやまりと妹やとがめむ」 |
「この花の香りを素晴らしい袖に移して帰ったら 女と過ちを犯したのではないかと妻が咎めるでしょう」 |
花の香をえならぬ ことあやまりと |
"Hana no ka wo e nara nu sode ni utusi mote koto ayamari to imo ya togame m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.19 | とあれば、 |
と言うので、 |
宮がこうお歌いになったと聞いて、 |
to are ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.20 | 「 いと屈したりや」 |
「たいそう弱気ですな」 |
「何と言いわけをしようと御心配なのだね」 |
"Ito kutusi tari ya!" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.21 | と笑ひたまふ。 御車かくるほどに、 追ひて、 |
と言ってお笑いになる。お車に牛を繋ぐところに、追いついて、 |
と源氏は笑った。お車はもう走り出そうとしていたのであったが、使いを追いつかせて、 |
to warahi tamahu. Ohom-kuruma kakuru hodo ni, ohi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.22 | 「 めづらしと故里人も待ちぞ見む 花の錦を着て帰る君 |
「珍しいと家の人も待ち受けて見ましょう この花の錦を着て帰るあなたを |
「めづらしとふるさと人も待ちぞ見ん 花の錦を着て帰る君 |
"Medurasi to hurusatobito mo mati zo mi m hana no nisiki wo ki te kaheru Kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.23 | またなきことと思さるらむ」 |
めったにないこととお思いになるでしょう」 |
この上ないことだと御満足なさるでしょう」 |
Mata naki koto to obosaru ram." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.24 | とあれば、 いといたうからがりたまふ。次々の君達にも、ことことしからぬさまに、細長、小袿などかづけたまふ。 |
とおっしゃるので、とてもつらがりなさる。以下の公達にも、大げさにならないようにして、細長、小袿などをお与えになる。 |
と源氏がお伝えさせると宮は苦笑をあそばされた。頭中将や弁の少将などにも目だつほどの |
to are ba, ito itau karagari tamahu. Tugitugi no Kimi-tati ni mo, kotokotosikara nu sama ni, hosonaga, koutiki nado kaduke tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/21/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 2/18/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 9/29/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 2/18/2010 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 4.00: Copyright (c) 2003,2024 宮脇文経