第四十一帖 幻 |
41 MABOROSI (Ohoshima-bon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光る源氏の准太上天皇時代 五十二歳春から十二月までの物語 |
Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from spring to December, at the age of 52 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 第二章 光る源氏の物語 紫の上追悼の夏の物語 |
2 Tale of Genji Mourning for Murasaki, in summer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 第一段 花散里や中将の君らと和歌を詠み交わす |
2-1 Genji composes and exchanges waka with Hanachirusato and Chujo-no-Kimi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | 夏の御方より、御衣更の御装束たてまつりたまふとて、 |
夏の御方から、お衣更のご装束を差し上げなさるとあって、 |
夏の |
Natu-no-Ohomkata yori, ohom-koromogahe no ohom-sauzoku tatematuri tamahu tote, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.2 | 「 夏衣裁ち替へてける今日ばかり 古き思ひもすすみやはせぬ」 |
「夏の衣に着替えた今日だけは 昔の思いも思い出しませんでしょうか」 |
夏ごろもたちかへてける今日ばかり 古き思ひもすすみやはする |
"Natu goromo tati kahe te keru kehu bakari huruki omohi mo susumi yaha se nu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.3 | 御返し、 |
お返事、 |
この歌が添えられてあった。お返事、 |
Ohom-kahesi, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.4 | 「 羽衣の薄きに変はる今日よりは 空蝉の世ぞいとど悲しき」 |
「羽衣のように薄い着物に変わる今日からは はかない世の中がますます悲しく思われます」 |
羽衣のうすきにかはる今日よりは |
"Hagoromo no usuki ni kaharu kehu yori ha utusemi no yo zo itodo kanasiki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.5 | 祭の日、いとつれづれにて、「 今日は物見るとて、人びと心地よげならむかし」とて、御社のありさまなど思しやる。 |
賀茂祭の日、とても所在ないので、「今日は見物しようとして、女房たちは気持ちよさそうだろう」と思って、御社の様子などをご想像なさる。 |
|
Maturi no hi, ito turedure nite, "Kehu ha mono miru tote, hitobito kokotiyoge nara m kasi." tote, miyasiro no arisama nado obosiyaru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.6 | 「 女房など、いかにさうざうしからむ。里に忍びて出でて見よかし」などのたまふ。 |
「女房などは、どんなに手持ち無沙汰だろう。そっと里下がりして見て来なさい」などとおしゃる。 |
「女房たちは皆寂しいだろう、実家のほうへ行って、そこから見物に出ればいい」などとも言っておいでになった。 |
"Nyoubau nado, ikani sauzausikara m. Sato ni sinobi te ide te miyo kasi." nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
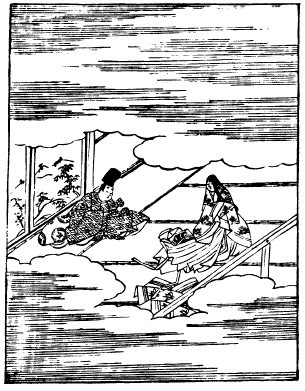 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.7 | 中将の君の、東面にうたた寝したるを、歩みおはして見たまへば、いとささやかにをかしきさまして、起き上がりたり。つらつきはなやかに、匂ひたる顔をもて隠して、すこしふくだみたる髪のかかりなど、 をかしげなり。紅の黄ばみたる気添ひたる袴、萱草色の単衣、いと濃き鈍色に黒きなど、うるはしからず重なりて、裳、唐衣も脱ぎすべしたりけるを、とかく引きかけなどするに、葵をかたはらに置きたりけるを 寄りて取りたまひて、 |
中将の君が、東表の間でうたた寝しているのを、歩いていらっしゃって御覧になると、とても小柄で美しい様子で起き上がった。顔の表情は明るくて、美しい顔をちょっと隠して、少しほつれた髪のかかっている具合など、見事である。紅の黄色味を帯びた袴に、萱草色の単衣、たいそう濃い鈍色の袿に黒い表着など、きちんとではなく重着して、裳や、唐衣も脱いでいたが、あれこれ着掛けなどするが、葵を側に置いてあったのを側によってお取りになって、 |
中将の君が東の座敷でうたた寝しているそばへ院が寄ってお行きになると、美しい小柄な中将の君は起き上がった。赤くなっている顔を恥じて隠しているが、少し癖づいてふくれた髪の横に見えるのがはなやかに見えた。紅の黄がちな色の |
Tyuuzyau-no-Kimi no, himgasi omote ni utatane si taru wo, ayumi ohasi te mi tamahe ba, ito sasayakani wokasiki sama site, okiagari tari. Turatuki hanayakani, nihohi taru kaho wo mote-kakusi te, sukosi hukudami taru kami no kakari nado, wokasige nari. Kurenawi no kibami taru ke sohi taru hakama, kwanzau iro no hitohe, ito koki nibiiro ni kuroki nado, uruhasikara zu kasanari te, mo, karaginu mo nugi subesi tari keru wo, tokaku hiki-kake nado suru ni, ahuhi wo katahara ni oki tari keru wo yori te tori tamahi te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.8 | 「 いかにとかや。この名こそ忘れにけれ」とのたまへば、 |
「何と言ったかね。この名前を忘れてしまった」とおっしゃると、 |
「何という草だったかね。名も忘れてしまったよ」とお言いになると、 |
"Ikani to ka ya? Kono na koso wasure ni kere." to notamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.9 | 「 さもこそはよるべの水に水草ゐめ 今日のかざしよ名さへ忘るる」 |
「いかにもよるべの水も古くなって水草が生えていましょう 今日の插頭の名前さえ忘れておしまいになるとは」 |
さもこそは寄るべの水に 今日のかざしよ名さへ忘るる |
"Samo koso ha yorube no midu ni mikusa wi me kehu no kazasi yo na sahe wasururu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.10 | と、恥ぢらひて聞こゆ。げにと、いとほしくて、 |
と、恥じらいながら申し上げる。なるほどと、お気の毒なので、 |
と恥じらいながら中将は言った。そうであったと哀れにお思いになって、 |
to, hadirahi te kikoyu. Geni to, itohosiku te, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.11 | 「 おほかたは思ひ捨ててし世なれども 葵はなほや摘みをかすべき」 |
「だいたいは執着を捨ててしまったこの世ではあるが この葵はやはり摘んでしまいそうだ」 |
おほかたは思ひ捨ててし世なれども あふひはなほやつみおかすべき |
"Ohokata ha omohi sute te si yo nare domo ahuhi ha naho ya tumi wokasu beki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.12 | など、一人ばかりをば思し放たぬけしきなり。 |
などと、一人だけはお思い捨てにならない様子である。 |
こんなこともお言いになり、なおこの人にだけは |
nado, hitori bakari wo ba obosi hanata nu kesiki nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 第二段 五月雨の夜、夕霧来訪 |
2-2 Yugiri visits to Genji's room in the rainy night |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.1 | 五月雨は、いとど眺めくらしたまふより他のことなく、さうざうしきに、十余日の月はなやかにさし出でたる雲間のめづらしきに、大将の君御前にさぶらひたまふ。 |
五月雨の時は、ますます物思いに沈んでお暮らしになるより他のことなく、物寂しいところに、十日過ぎの月が明るくさし出た雲間が珍しいので、大将の君が御前に伺候なさっている。 |
|
Samidare ha, itodo nagame kurasi tamahu yori hoka no koto naku, sauzausiki ni, zihuyo niti no tuki hanayaka ni sasiide taru kumoma no medurasiki ni, Daisyau-no-Kimi omahe ni saburahi tamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.2 | 花橘の、月影にいときはやかに見ゆる薫りも、追風なつかしければ、 千代を馴らせる声も ★せなむ、と待たるるほどに、にはかに立ち出づる村雲のけしき、いとあやにくにて、 いとおどろおどろしう降り来る雨に添ひて、さと吹く風に灯籠も吹きまどはして、空暗き心地するに、「 窓を打つ声」など ★、めづらしからぬ古言を、うち誦じ たまへるも、折からにや、 妹が垣根におとなはせまほしき御声なり。 |
花橘が、月光にたいそうくっきりと見える薫りも、その追い風がやさしい感じなので、花橘にほととぎすの千年も馴れ親しんでいる声を聞かせて欲しい、と待っているうちに、急にたち出た村雲の様子が、まったくあいにくなことで、とてもざあざあ降ってくる雨に加わって、さっと吹く風に燈籠も吹き消して、空も暗い感じがするので、「窓を打つ声」などと、珍しくもない古詩を口ずさみなさるのも、折からか、妻の家に聞かせてやりたいようなお声である。 |
花 |
Hanatatibana no, tukikage ni ito kihayakani miyuru kawori mo, ohikaze natukasikere ba, tiyo wo narase ru kowe mo se nam, to mata ruru hodo ni, nihakani tati iduru murakumo no kesiki, ito ayaniku nite, ito odoroodorosiu huri kuru ame ni sohi te, sato huku kaze ni touro mo huki madohasi te, sora kuraki kokoti suru ni, "Mado wo utu kowe" nado, medurasikara nu hurukoto wo, uti-zyunzi tamahe ru mo, wori kara ni ya, imo ga kakine ni otonaha se mahosiki ohom-kowe nari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.3 | 「 独り住みは、ことに変ることなけれど、あやしうさうざうしくこそありけれ。深き山住みせむにも、かくて身を馴らはしたらむは、こよなう心澄みぬべきわざなりけり」などのたまひて、「 女房、ここに、くだものなど参らせよ。男ども召さむもことことしきほどなり」などのたまふ。 |
「独り住みは、格別に変わったことはないが、妙に物寂しい感じがする。深い山住みをするにも、こうして身を馴らすのは、この上なく心が澄みきることであった」などとおっしゃって、「女房よ、こちらに、お菓子などを差し上げよ。男たちを召し寄せるのも大げさな感じである」などとおっしゃる。 |
「独身生活というものは、私一人が経験しているものでもないが、怪しいほど寂しいものだ。山へはいってしまう前にこうして習慣をつけておくことは非常によいことだと思う」などと院はお言いになって、「女房たち、ここへ菓子でも出すがよい。男たちに命じるほどのことでもないから」などとも気をつけておいでになった。 |
"Hitori zumi ha, kotoni kaharu koto nakere do, ayasiu sauzausiku koso ari kere. Hukaki yamazumi se m ni mo, kaku te mi wo narahasi tara m ha, koyonau kokoro sumi nu beki waza nari keri." nado notamahi te, "Nyoubau, koko ni, kudamono nado mawirase yo. Wonoko-domo mesa m mo kotokotosiki hodo nari." nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.4 | 心には、ただ空を眺めたまふ ★御けしきの、尽きせず心苦しければ、「かくのみ思し紛れずは、御行ひにも心澄ましたまはむこと難くや」と、見たてまつりたまふ。「 ほのかに見し御面影だに忘れがたし。ましてことわりぞかし」と、思ひゐたまへり。 |
心中には、ただ空を眺めていらっしゃるご様子が、どこまでもおいたわしいので、「こんなにまでお忘れになれないのでは、ご勤行にもお心をお澄しになることも難しいのでないか」と、拝見なさる。「かすかに見た御面影でさえ忘れ難い。まして無理もないことだ」と、思っていらっしゃった。 |
夕霧は空をおながめになる院の寂しい御表情を見ていて、こんなふうにいつまでもいつまでも故人を悲しんでおいでになっては、出家をされても透徹した信仰におはいりになることはむずかしくはないかと思っていた。ほのかな |
Kokoro ni ha, tada sora wo nagame tamahu ohom-kesiki no, tuki se zu kokorogurusikere ba, "Kaku nomi obosi magire zu ha, ohom-okonahi ni mo kokoro sumasi tamaha m koto kataku ya?" to, mi tatematuri tamahu. "Honokani mi si ohom-omokage dani wasure gatasi. Masite kotowari zo kasi." to, omohi wi tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 第三段 ほととぎすの鳴き声に故人を偲ぶ |
2-3 Genji and Yugiri remember Murasaki as a little cuckoo singing in the night |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | 「 昨日今日と思ひたまふるほどに、御果てもやうやう近うなりはべりにけり。いかやうにかおきて思しめすらむ」 |
「昨日今日と思っておりましたうちに、ご一周忌もだんだん近くなってまいりました。どのようにあそばすお積もりでいらっしゃいましょうか」 |
「昨日か今日のことのように思っておりますうちに御一周忌にももう近づいてまいります。御法事はどんなふうにあそばすおつもりでございますか」 |
"Kinohu kehu to omohi tamahuru hodo ni, ohom-hate mo yauyau tikau nari haberi ni keri. Ikayauni ka oki te obosimesu ram?" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | と申したまへば、 |
とお尋ね申し上げなさると、 |
と大将が言うと、 |
to mawosi tamahe ba, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | 「 何ばかり、世の常ならぬことを かはものせむ。かの心ざしおかれたる極楽の曼陀羅など、このたびなむ供養ずべき。経などもあまたありけるを、なにがし僧都、皆その心くはしく聞きおきたなれば、また加へてすべきことどもも、かの僧都の言はむに従ひてなむものすべき」などのたまふ。 |
「何ほども、世間並み以上のことをしようとは思わない。あの望んでおかれた極楽の曼陀羅など、今回は供養しよう。経などもたくさんあったが、某僧都が、すべてその事情を詳しく聞きおいたそうだから、それに加えてしなければならない事柄も、あの僧都が言うことに従って催そう」などとおっしゃる。 |
「何も普通と違ったことをしようと思っていない。女王が作らせたままになっている極楽の |
"Nani bakari, yo no tune nara nu koto wo kaha monose m. Kano kokorozasi oka re taru gokuraku no mandara nado, konotabi nam kuyauzu beki. Kyau nado mo amata ari keru wo, Nanigasi-Soudu, mina sono kokoro kuhasiku kikioki ta' nare ba, mata kuhahe te su beki koto-domo mo, kano Soudu no iha m ni sitagahi te nam monosu beki." nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.4 | 「 かやうのこと、もとよりとりたてて思しおきてけるは、うしろやすきわざなれど、この世にはかりそめの御契りなりけりと 見たまふには、形見といふばかりとどめきこえたまへる人だにものしたまはぬこそ、 口惜しうはべれ」 |
「このようなことは、ご生前から特別にお考え置きになっていたことは、来世のため安心なことですが、この世にはかりそめのご縁であったとお思いなりますのは、お形見と言えるようにお残し申されるお子様さえいらっしゃなかったのが、残念なことでございます」 |
「御自身の御法要についてのことまでもお |
"Kayau no koto, motoyori toritate te obosi oki te keru ha, usiroyasuki waza nare do, konoyo niha karisome no ohom-tigiri nari keri to mi tamahu ni ha, katami to ihu bakari todome kikoye tamahe ru hito dani monosi tamaha nu koso, kutiwosiu habere." |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.5 | と申したまへば、 |
と申し上げなさると、 |
to mawosi tamahe ba, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.6 | 「 それは、仮ならず、命長き人びとにも、さやうなることのおほかた少なかりける。みづからの口惜しさにこそ。そこにこそは、門は広げたまはめ」などのたまふ。 |
「それは、縁浅からず、寿命の長い人びとでも、そのようなことはだいたいが少なかった。自分自身の拙さなのだ。そなたこそ、家門を広げなさい」などとおっしゃる。 |
「しかし子は早く死なずに現存している妻のほうにも少なかったのだからね。私自身が子は少なくしか持てない宿命だったのだろう。あなたによって子孫を広げてもらえばいい」などと院はお言いになるのであって、 |
"Sore ha, kari nara zu, inoti nagaki hitobito ni mo, sayau naru koto no ohokata sukunakari keru. Midukara no kutiwosisa ni koso. Soko ni koso ha, kado ha hiroge tamaha me." nado notamahu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.7 | 何ごとにつけても、忍びがたき 御心弱さのつつましくて、過ぎにしこといたうものたまひ出でぬに、待たれつる 山ほととぎすのほのかにうち鳴きたるも、「 いかに知りてか」と ★、 聞く人ただならず。 |
どのような事につけても、堪えきれないお心の弱さが恥ずかしくて、過ぎ去ったことをたいして口にお出しにならないが、待っていた時鳥がかすかにちょっと鳴いたのも、「どのようにして知ってか」と、聞く人は落ち着かない。 |
何につけても忍びがたい悲しみの外へ誘い出されることをお恐れになり、故人のこともあまりお話しにならぬうちに、「いにしへのこと語らへば |
Nani-goto ni tuke te mo, sinobi-gataki mi-kokoroyowasa no tutumasiku te, sugi ni si koto itau mo notamahi ide nu ni, mata re turu yamahototogisu no honoka ni uti-naki taru mo, "Ikani siri te ka." to, kiku hito tada nara zu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.8 | 「 亡き人を偲ぶる宵の村雨に 濡れてや来つる山ほととぎす」 |
「亡き人を偲ぶ今宵の村雨に 濡れて来たのか、山時鳥よ」 |
|
"Naki hito wo sinoburu yohi no murasame ni nure te ya ki turu yamahototogisu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.9 | とて、いとど空を眺めたまふ。大将、 |
と言って、ますます空を眺めなさる。大将、 |
前よりもいっそう悲しいまなざしで空を院はおながめになった。夕霧は、 |
tote, itodo sora wo nagame tamahu. Daisyau, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.10 | 「 ほととぎす君につてなむふるさとの 花橘は今ぞ盛りと」 |
「時鳥よ、あなたに言伝てしたい 古里の橘の花は今が盛りですよと」 |
古さとの花 |
"Hototogisu kimi ni tute na m hurusato no hanatatibana ha ima zo sakari to |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.11 | 女房など、多く言ひ集めたれど、とどめつ。 大将の君は、やがて御宿直にさぶらひたまふ。寂しき御一人寝の心苦しければ、時々かやうにさぶらひたまふに、 おはせし世は、いと気遠かりし御座のあたりの、いたうも立ち離れぬなどにつけても、思ひ出でらるる ことも多かり。 |
女房なども、たくさん詠んだが、省略した。大将の君は、そのままお泊まりになる。寂しいお独り寝がおいたわしいので、時々このように伺候なさるが、生きていらっしゃった当時は、とても近づきにくかったご座所の近辺に、たいして遠く離れていないことなどにつけても、思い出される事柄が多かった。 |
と歌った。この時に女房たちもそれぞれ歌を |
Nyoubau nado, ohoku ihi atume tare do, todome tu. Daisyau-no-Kimi ha, yagate ohom-tonowi ni saburahi tamahu. Sabisiki ohom-hitorine no kokorogurusikere ba, tokidoki kayauni saburahi tamahu ni, ohase si yo ha, ito ke-dohokari si omasi no atari no, itau mo tati hanare nu nado ni tuke te mo, omohi ide raruru koto mo ohokari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 第四段 蛍の飛ぶ姿に故人を偲ぶ |
2-4 Genji remembers Murasaki as fireflies flying in the night |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.1 | いと暑きころ、涼しき方にて眺めたまふに、池の蓮の盛りなるを見たまふに、「 いかに多かる」など ★、まづ思し出でらるるに、ほれぼれしくて、つくづくとおはするほどに、日も暮れにけり。 ひぐらしの声はなやかなるに、御前の撫子の夕映えを ★、一人のみ見たまふは、げにぞかひなかりける。 |
たいそう暑いころ、涼しい所で物思いに耽っていらっしゃる折、池の蓮の花が盛りなのを御覧になると、「なんと多い涙か」などと、何より先に思い出されるので、茫然として、つくねんとしていらっしゃるうちに、日も暮れてしまった。蜩の声がにぎやかなので、御前の撫子が夕日に映えた様子を、独りだけで御覧になるのは、本当に甲斐のないことであった。 |
暑いころに涼しい |
Ito atuki koro, suzusiki kata nite nagame tamahu ni, ike no hatisu no sakari naru wo mi tamahu ni, "Ikani ohokaru?" nado, madu obosi ide raruru ni, horeboresiku te, tukuduku to ohasuru hodo ni, hi mo kure ni keri. Higurasi no kowe hanayaka naru ni, omahe no nadesiko no yuhubae wo, hitori nomi mi tamahu ha, geni zo kahinakari keru. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.2 | 「 つれづれとわが泣き暮らす夏の日を かことがましき虫の声かな」 |
「することもなく涙とともに日を送っている夏の日を わたしのせいみたいに鳴いている蜩の声だ」 |
つれづれとわが泣き暮らす夏の日を かごとがましき虫の声かな |
"Turedureto waga naki kurasu natu no hi wo kakoto gamasiki musi no kowe kana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.3 | 蛍のいと多う飛び交ふも、「 夕殿に蛍飛んで」と ★、例の、古事もかかる筋にのみ口馴れたまへり。 |
螢がとても数多く飛び交っているのも、「夕べの殿に螢が飛んで」と、いつもの、古い詩もこうした方面にばかり口馴れていらっしゃった。 |
|
Hotaru no ito ohou tobikahu mo, "Sekiden ni hotaru ton de" to, rei no, hurukoto mo kakaru sudi ni nomi kuti nare tamahe ri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.4 | 「 夜を知る蛍を見ても悲しきは ★ 時ぞともなき思ひなりけり」 |
「夜になったことを知って光る螢を見ても悲しいのは 昼夜となく燃える亡き人を恋うる思いであった」 |
夜を知る蛍を見ても悲しきは 時ぞともなき思ひなりけり |
"Yoru wo siru hotaru wo mi te mo kanasiki ha toki zo to mo naki omohi nari keri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated 9/22/2010(ver.2-3) 渋谷栄一校訂(C) Last updated 8/16/2010(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) |
Last updated 2/12/2002 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) |
|
Last updated 8/16/2010 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源氏物語の世界 再編集プログラム Ver 4.00: Copyright (c) 2003,2024 宮脇文経