第五帖 若紫
光る源氏の十八歳春三月晦日から冬十月までの物語
#
本文
渋谷栄一訳
与謝野晶子訳
注釈
第一章 紫上の物語 若紫の君登場、三月晦日から初夏四月までの物語
第一段 三月晦日、加持祈祷のため、北山に出向く
【参らせたまへど】- 「参ら」未然形(して差し上げる、謙譲の意を含む動詞)、使役の助動詞「せ」連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」已然形。受手(源氏)尊敬で、おさせなさるが、の意になる。
【ある人】- 以下会話文が挿入され、「など聞こゆれば」に係る。
「北山 になむ、なにがし寺 といふ所 に、かしこき行 ひ人 はべる。
去年 の夏 も世 におこりて、人 びとまじなひわづらひしを、やがてとどむるたぐひ、あまたはべりき。
ししこらかしつる時 はうたてはべるを、とくこそ試 みさせたまはめ」
ししこらかしつる
去年の夏も世間に流行して、人々がまじないあぐねたのを、たちどころに治した例が、多数ございました。
こじらせてしまうと厄介でございますから、早くお試しあそばすとよいでしょう」
【まじなひわづらひしを】- 過去の助動詞「し」連体形は「ある人」の身近な体験を語るニュアンス。
【あまたはべりき】- 過去の助動詞「き」終止形も同じく身近な体験を語るニュアンス。
【うたてはべるを】- 丁寧の補助動詞「はべる」連体形+接続助詞「を」順接、原因理由を表す。やっかいでございますから。
【とくこそ試みさせたまはめ】- 係助詞「こそ」は推量の助動詞「め」已然形、適当の意に係る、係結びの法則。尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまは」未然形、二重敬語。会話文中の用例。
ごく内密に行こう」とおっしゃって、お供に親しい者四、五人ほど連れて、まだ夜明け前にお出かけになる。
「老体になっておりまして、岩窟を一歩出ることもむずかしいのですから」
僧の返辞はこんなだった。
「それではしかたがない、そっと微行で行ってみよう」
こう言っていた源氏は、親しい家司四、五人だけを伴って、夜明けに京を立って出かけたのである。
【老いかがまりて、室の外にもまかでず】- 「かしこき行ひ人」の言葉を、使者が伝える。 【まかでず】-「まかづ」は「出る」の謙譲語。外出いたしません、というニュアンス。
【申したれば】- 主語は使者。完了の助動詞「たれ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件。この段は「たり」(完了の助動詞)を基調にして語られる。
【いかがはせむ。いと忍びてものせむ】- 源氏の詞。「ものせむ」は、行こう、の意。
やや深 う入 る所 なりけり。
三月 のつごもりなれば、京 の花盛 りはみな過 ぎにけり。
山 の桜 はまだ盛 りにて、入 りもておはするままに、霞 のたたずまひもをかしう見 ゆれば、かかるありさまもならひたまはず、所狭 き御身 にて、めづらしう思 されけり。
三月の晦日なので、京の花盛りはみな過ぎてしまっていた。
山の桜はまだ盛りで、入って行かれるにつれて、霞のかかった景色も趣深く見えるので、このような山歩きもご経験なく、窮屈なご身分なので、珍しく思われなさるのであった。
【三月のつごもりなれば】- 季節が語られる。三月晦、晩春の山景。
【京の花盛りはみな過ぎにけり。山の桜はまだ盛りにて】- 「京の花」と「山の桜」とが対比された対句じたての文。完了の助動詞「に」連用形+過去の助動詞「けり」終止形。『異本紫明抄』は引歌として、「里はみな散り果てにしを足引の山の桜はまだ盛りなりけり」(玉葉集春下 二二七 躬恒)を指摘する。
【入りもておはするままに】- 主語は源氏。「おはす」は「行く」の尊敬語。
【霞のたたずまひ】- 春の景物として霞が描かれる。
【をかしう見ゆれば】- 「をかしう見ゆれば」は「めづらしう思されけり」に続く。「かかるありさまも」から「御身にて」までは、源氏の体験や日常の生活状況を説明した挿入句。
【所狭き御身にて】- 断定の助動詞「に」連用形。
【めづらしう思されけり】- 「思さ」未然形は「思ふ」の尊敬表現。自発の助動詞「れ」連用形。過去の助動詞「けり」終止形。
峰高く、深い岩屋の中に、聖は入っているのだった。
お登りになって、誰ともお知らせなさらず、とてもひどく粗末な身なりをしていらっしゃるが、はっきり誰それと分かるご風采なので、
源氏は自身のだれであるかを言わず、服装をはじめ思い切って簡単にして来ているのであるが、迎えた僧は言った。
【聖入りゐたりける】- 大島本は「ゐ」と表記する。完了の助動詞「たり」連用形。過去の助動詞「ける」連体形、係助詞「ぞ」の係結びの法則。強調を表す。聖は岩屋の中に座っていたのであった、というニュアンス。源氏たち一行が見た描写。
【登りたまひて、誰とも知らせたまはず】- 主語は源氏。
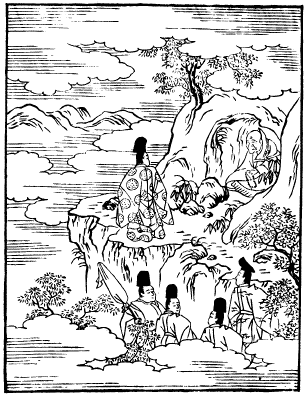
先日、お召しになった方でいらっしゃいましょうか。
今は、現世のことを考えておりませんので、修験の方法も忘れておりますのに、どうして、このようにわざわざお越しあそばしたのでしょうか」
【召しはべりしにやおはしますらむ】- 「召しはべりし方にや」の意。断定の助動詞「に」連用形、係助詞「や」疑問の意、推量の助動詞「らむ」連体形に係る、係結びの法則。「おはします」は「おはす」よりさらに高い敬語表現。源氏の姿を眼前にしながら「らむ」(視界外推量)というのは、心理的距離感を表す。
【思ひたまへねば】- 謙譲の補助動詞「たまへ」未然形+打消の助動詞「ね」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【捨て忘れてはべるを】- 丁寧の補助動詞「はべる」連体形+接続助詞「を」逆接。
【いかで、かうおはしましつらむ】- 「おはします」は「おはす」より高い敬語表現。完了の助動詞「つ」終止形。推量の助動詞「らむ」連体形(原因推量)は、上に副詞「いかで」疑問の意があるので。
まことに立派な大徳なのであった。
しかるべき薬を作って、お呑ませ申し、加持などして差し上げるうちに、日が高くなった。
【いと尊き大徳なりけり】- 『首書源氏物語』は「地」といわゆる「草子地」であると指摘。『評釈』も「男君の美を認める目は持ち続けたこの老僧に、作者は、読者とともに讃辞を呈している」と注す。
【すかせたてまつり】- 『古典セレクション』は諸本に従って「すかせたてまつる」と終止形に改める。『集成』『新大系』は底本のまま。
第二段 山の景色や地方の話に気を紛らす
【見おろさるる】- 語り手と源氏の目とが一体化した表現。可能の助動詞「るる」連体形。
【ただこのつづら折の下に】- 以下「何人の住むにか」までを源氏の詞とみる説もある。
【うるはしくし渡して】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「うるわしう」とウ音便形に改める。『新大系』は底本のまま。
「何人 の住 むにか」
【二年】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「この二年」と改める。『新大系』は底本のままとする。
【籠もりはべる方にはべるなる】- 前者の「はべる」は丁寧の補助動詞、連体形。後者の「はべる」は丁寧の動詞、連体形+伝聞推定の助動詞「なる」連体形、係結びの法則。
何とも、あまりに粗末な身なりであったなあ。
聞きつけたら困るな」などとおっしゃる。
などと、源氏は言った。
【住むなる所にこそあなれ】- マ四動詞「住む」終止形+伝聞推定の助動詞「なる」連体形。「あなれ」の「あ」はラ変動詞「ある」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記+伝聞推定の助動詞「なれ」已然形、係結びの法則。
【聞きもこそすれ】- 連語「もこそ」(助詞「も」+係助詞「こそ」)懸念を表す。聞き付けられたら大変だ、困ったな、というニュアンス。サ変動詞「すれ」已然形。係結びの法則。
「いかなる人 ならむ」
と口々言 ふ。
下 りて覗 くもあり。
下りて覗く者もいる。
【童女なむ見ゆる】- 係助詞「なむ」--ヤ下二動詞「見ゆる」連体形、係結びの法則。
【日たくるままに】- 前に「日高くさし上がりぬ」とあった。時間の推移を表す。
【いかならむと思したるを】- 完了の助動詞「たる」連体形、存続の意。接続助詞「を」弱い順接。
【思し入れぬなむ】- 打消の助動詞「ぬ」連体形。係助詞「なむ」は「はべる」連体形に係る、係結び。
遠くまで霞がかかっていて、四方の梢がどことなく霞んで見える具合、
【はるかに霞みわたりて】- 以下「あらじかし」までを、源氏の詞とみる説(待井『文法全解』)もある。地の文から会話文(源氏の発言)へと移っていく文章である。
このような所に住む人は、心に思い残すことはないだろうよ」とおっしゃると、
と源氏が言うと、
【あらじかし】- ラ変「あら」未然形+打消推量の助動詞「じ」終止形+終助詞「かし」念押し、を表す。
地方などにございます海、山の景色などを御覧に入れましたならば、どんなにか、お絵も素晴らしくご上達あそばしましょう。
富士の山、何々の嶽」
【御覧ぜさせてはべらば】- 使役の助動詞「させ」連用形+接続助詞「て」+丁寧の補助動詞「はべら」未然形+接続助詞「ば」順接の仮定条件を表す。人をして(誰かが)源氏に(それらの景色を)御覧に入れさせましたならば、の意。
【富士の山、なにがしの嶽】- 「なにがしの嶽」は、古来浅間山かとされる。とすると、いずれも当時は噴煙を上げていた活火山である。
また、西国の美しい浦々や、海岸辺りについて話し続ける者もいて、何かとお気を紛らし申し上げる。
【紛らはしきこゆ】- 主語は供人。謙譲の補助動詞「きこゆ」終止形。
どこといって奥深い趣はないが、ただ、海の方を見渡しているところが、不思議と他の海岸とは違って、ゆったりと広々した所でございます。
【明石の浦こそ、なほことにはべれ】- 係助詞「こそ」--「はべれ」已然形、係結びの法則。強調の意。副詞「なほ」やはり。『古典セレクション』は「もともと名所だが、やはり格別で」と注す。「明石」は播磨国の歌枕。「あまさかる鄙(ひな)の長道(ながぢ)ゆ恋ひ来れば明石の門(と)より大和島見ゆ」(万葉集巻三)「ほのぼのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしぞ思ふ」(古今集、羇旅)などが有名。
大臣の後裔で、出世もできたはずの人なのですが、たいそうな変わり者で、人づき合いをせず、近衛の中将を捨てて、申し出て頂戴した官職ですが、
【大臣の後にて】- 後に、源氏の祖父按察使大納言(母桐壺更衣の父親)の兄に当たる人であることが「明石」巻で判明する。しかし、この巻でその構想があれば、源氏の縁者にあたる人の噂を以下に語るように何の考慮せずに語ったろうか、不審。
【出で立ちもすべかりける人の】- サ変「す」終止形+推量の助動詞「べかり」連用形、可能+過去の助動詞「ける」連体形、格助詞「の」主格を表す。できたはずの人がの意。「世のひがものにて」を挿入句として、以下の文の総主語のような形になっている。いかにも会話文的表現である。
【近衛の中将】- 従四位下相当の官職。若い貴公子の京官(太政官)出世コース。一方、播磨守は従五位上相当の地方官(受領)。ただし、大国であり、物質的利益には大変に恵まれた国。実益は大いに期待できる。
【申し賜はれりける司なれど】- 主語は「かの国の前の守」。「申し」連用形、謙譲語、「賜はれ」已然形、謙譲語、完了の助動詞「り」連用形、過去の助動詞「ける」連体形。断定の助動詞「なれ」已然形+接続助詞「ど」逆接の確定条件を表す。自分から申し出て頂戴した官職であるが、の意。
かの国 の人 にもすこしあなづられて、『何 の面目 にてか、また都 にも帰 らむ』と言 ひて、頭 も下 ろしはべりにけるを、すこし奥 まりたる山住 みもせで、さる海 づらに出 でゐたる、ひがひがしきやうなれど、げに、かの国 のうちに、さも、人 の籠 もりゐぬべき所々 はありながら、深 き里 は、人離 れ心 すごく、若 き妻子 の思 ひわびぬべきにより、かつは心 をやれる住 まひになむはべる。
【何の面目にてか、また都にも帰らむ】- 前播磨守の詞を引用。「何の--か--帰らむ」は反語表現。再び都には帰れないの意。
【頭も下ろしはべりにけるを】- 丁寧の補助動詞「はべり」連用形、完了の助動詞「に」連用形、過去の助動詞「ける」連体形、接続助詞「を」逆接を表す。髪を下ろしてしまった、すなわち出家してしまった、のでございますが、の意。
【さる海づらに出でゐたる】- 完了の助動詞「たる」連体形。上文を受け、それは、と下文に続ける。
【げに】- 語り手の入道の出家生活に納得する気持ち。
【さも】- 「さ」は「すこし奥まりたる山住み」をさす。
【籠もりゐぬべき所々はありながら】- 完了の助動詞「ぬ」終止形、確述+推量の助動詞「べき」連体形、適当の意。籠もってしまうに相応しい所々はのニュアンス。
【思ひわびぬべきにより】- 完了の助動詞「ぬ」終止形、確述、推量の助動詞「べき」連体形、当然の意。格助詞「に」起点を表す、ラ四「より」連用形。きっと心細がるにちがいないことによって、の意。
後世の勤行も、まことによく勤めて、かえって出家して人品が上がった人でございました」と申し上げると、
【京にてこそ】- 係助詞「こそ」は「やうなりけれ」已然形に係るが、係結びの逆接用法で、下文に続く。
【そこらはるかに】- 『新大系』は「見渡す限りいっぱい大規模に土地を所有して造営しているさまは、の意。長者屋敷の感じがある」と注す。
【さは言へど】- 「さ」は「かの国の人にもすこしあなづられ」をさす。
代々の国司などが、格別懇ろな態度で、結婚の申し込みをするようですが、全然承知しません。
【容貌、心ばせなどはべるなり】- 「はべる」連体形(ラ変型活用)+伝聞推定の助動詞「なり」終止形。『例解古語辞典』ではこの例文をあげて「明石の入道という人物の娘の話を、光源氏に、家来が申しあげていることば。娘の容貌などが「けしうはあらず」とか、父入道が「遺言しおきて侍る」とかいうことは、直接知っていることではなくて、女房などからの話などで得ているものだということが、それぞれ「なり」「なる」を添えるということで明らかにされている。話し手はこれで責任のがれにもなるわけである。もし、「けしうはあらず侍り」とか、「遺言しおきて侍る」とか言えば、ことばの上では、直接知っている事がらと理解され、その言に責任をおわされてもやむをえないはずのところ」と解説する。「容貌心ばせなどけしうはあらずはべるなり」の倒置表現。
【代々の国の司など】- 明石入道が国司を辞して後、播磨国の国司が二、三代交替する。国司の任期は四年だが必ずしも任期満了とは限らない。
【さる心ばへ見すなれど】- 「さる心ばへ」とは求婚の意志をいう。伝聞推定の助動詞「なれ」已然形。
【さらにうけひかず】- 副詞「さらに」は打消の助動詞「ず」終止形と呼応して、全然承知しないの意。
もし、わたしに先立たれて、その素志を遂げられず、わたしの願っていた運命と違ったならば、海に入ってしまえ』と、いつも遺言をしているそうでございます」
【かくいたづらに沈めるだにあるを】- 連語「だにある」は副助詞「だに」+ラ変「ある」連体形の形。「ある」の前に無念であるなど語が省略されている形。落ちぶれているのさえ無念であるのに、の意。『新大系』は「明石巻、さらには若菜巻で明かされる大きな構想が早くもここにあるらしい」と指摘。しかし、それにしては明石の君の年齢や明石の入道の系譜などの点で不自然さがある。
【この人ひとりにこそあれ】- 前の副助詞「だに」を受けて、「まして」の気持ちが加わる。「この人」は娘をさす。子供はこの娘一人だの意。期待するところの大きさをいう。『集成』『新大系』はこの文を、前後読点で、はさみ込まれた挿入句のごとく解す。『完訳』は前後句点で、独立した一文と解すが、『古典セレクション』では読点に改める。
【思ふさまことなり】- 断定の助動詞「なり」終止形。
【宿世違はば、海に入りね】- 「違は」未然形+接続助詞「ば」仮定条件を表す。完了の助動詞「ね」命令形。
【しおきてはべるなる】- 丁寧の補助動詞「はべる」連体形(ラ変型活用)+伝聞推定の助動詞「なる」連体形。連体中止法、余情表現。まだ話の続きがあるというニュアンス。
と聞 こゆれば、君 もをかしと聞 きたまふ。
人 びと、
供人たちは、
「心高 さ苦 しや」とて笑 ふ。
などと冷評する者があって人々は笑っていた。
【破りつべき心はあらむかし】- 連語「つべき」(完了の助動詞「つ」終止形、確述の意+推量の助動詞「べき」連体形、当然の意)確実な推量を表す。きっと--するにちがいない。ラ変「あら」未然形+推量の助動詞「む」終止形+終助詞「かし」念押し。
と言 ひあへり。
幼い時からそのような所に成長して、古めかしい親にばかり教育されていたのでは」
【田舎びたらむ】- バ上二「田舎び」連用形+完了の助動詞「たら」未然形+推量の助動詞「む」終止形。
【親にのみ従ひたらむは】- 副助詞「のみ」限定・強調、完了の助動詞「たら」未然形+推量の助動詞「む」連体形+終助詞「は」詠嘆の意、また「従ひたらむは、田舎びたらむ」という倒置法による係助詞「は」とも解せる。
美しい若い女房や、童女など、都の高貴な家々から、縁故を頼って探し集めて、眩しく育てているそうだ」
「しかし母親はりっぽなのだろう。若い女房や童女など、京のよい家にいた人などを何かの縁故からたくさん呼んだりして、たいそうなことを娘のためにしているらしいから、
【まばゆくこそもてなすなれ】- 係助詞「こそ」、「もてなす」終止形+伝聞推定の助動詞「なれ」已然形、係結びの法則。強調のニュアンス。
【え置きたらじをや】- 副詞「え」は打消推量の助動詞「じ」終止形と呼応して不可能の意を表す。連語「をや」(間投助詞「を」詠嘆+間投助詞「や」詠嘆)強い感動を表す。
など言 ふもあり。
君 、
源氏の君は、
海底の「海松布」も何となく見苦しい」
【海の底まで深う思ひ入るらむ】- 「深う」連用形「く」のウ音便形。ラ四「入る」終止形+推量の助動詞「らむ」終止形、原因推量の意。なぜ--なのだろうか。
【底の「みるめ】- 「みるめ」に「見る目」と「海松布」を掛ける。ちゃかした言い方。
このような話でも、普通以上に、一風変わったことをお好みになるご性格なので、お耳を傾けられるのだろう、と拝見する。
【もてひがみたること好みたまふ御心なれば】- 『古典セレクション』は「風変りを好む性癖があるとして、語り手が源氏の関心を強調する」と注す。
【御耳とどまらむをや】- 推量の助動詞「む」終止形+連語「をや」(間投助詞「を」詠嘆+間投助詞「や」詠嘆)強い感動を表す。
早くお帰りあそばされのがよいでしょう」
【おこらせたまはずなりぬるにこそはあめれ】- 「せたまは」は尊敬の助動詞「せ」連用形+「尊敬の補助動詞「たまは」未然形の最高敬語、会話文中の使用。打消の助動詞「ず」連用形。ラ四「なり」連用形、完了の助動詞「ぬる」連体形、格助詞「に」動作の帰着を表す。係助詞「こそ」、係助詞「は」、「あめれ」はラ変「ある」連体形「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「めれ」已然形、主観的推量の意、係結びの法則。強調のニュアンス。
【はや帰らせたまひなむ】- 副詞「はや」。「たまひ」は尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまひ」連用形、二重敬語。「なむ」は完了の助動詞「な」未然形+推量の助動詞「む」終止形、適当の意。
と言った。
【加持など参りて、出でさせたまへ】- 「参り」は尊敬語。加持などを奉仕させる、加持などなさる。「させたまへ」は尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまへ」命令形、二重敬語。
源氏の君も、このような旅寝もご経験ないことなので、何と言っても興味があって、
【慣らひたまはねば】- 尊敬の補助動詞「たまは」未然形、打消の助動詞「ね」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
「さらば暁 に」とのたまふ。
こう言っていた。
第三段 源氏、若紫の君を発見す
供人はお帰しになって、惟光朝臣とお覗きになると、ちょうどこの西面に、仏を安置申して勤行している、それは尼なのであった。
簾を少し上げて、花を供えているようである。
中の柱に寄り掛かって座って、脇息の上にお経を置いて、とても大儀そうに読経している尼君は、普通の人とは見えない。
四十過ぎくらいで、とても色白で上品で、痩せてはいるが、頬はふっくらとして、目もとのぐあいや、髪がきれいに切り揃えられている端も、かえって長いのよりも、この上なく新鮮な感じだなあ、と感心して御覧になる。
【かの小柴垣のほどに】- 前に「同じ小柴なれどうるはしくし渡して」とあったのをさす。『集成』『古典セレクション』は「かの小柴垣のもとに」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
【人びとは帰したまひて】- 供人を京に帰す。
【惟光朝臣と】- 榊原家本、池田本、三条西家本は「これみつはかり御ともにて」とある。河内本も「惟光はかり御ともにて」とある。源氏の乳母子。「夕顔」巻に初出。
【ただこの西面にしも】- 以下、源氏の目を通して語られる叙述。
【仏据ゑたてまつりて行ふ、尼なりけり】- 『集成』『古典セレクション』は「持仏すゑたてまつりて」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。「行ふ」連体形は、間合いを置いて下文に続く。それは、--なのであったという構文。断定の助動詞「なり」連用形、過去の助動詞「けり」終止形、詠嘆の意。源氏の目を通して語られた描写。驚きの気持ち。敬語が省略され臨場感がある。『首書源氏物語』所引或抄は「地よりことはりたる也」と注す。『完訳』は「源氏の視覚にもとづく推量。「けり」「めり」「見えず」は源氏の視線にそう表現。「あはれに見たまふ」などは語り手を通した表現。両様の視点の重層によって、かいま見の奥行が深められる」と注す。
【花たてまつるめり】- 推量の助動詞「めり」終止形、視界内推量。源氏の主観的推量のニュアンス。
【と、あはれに見たまふ】- 源氏の視点から語り手の視点に戻る。
その中に、十歳くらいかと見えて、白い袿の上に、山吹襲などの、糊気の落ちた表着を着て、駆けてきた女の子は、大勢見えた子供とは比べものにならず、たいそう将来性が見えて、かわいらしげな顔かたちである。
髪は扇を広げたようにゆらゆらとして、顔はとても赤く手でこすって立っている。
【さては童女ぞ出で入り遊ぶ】- 接続詞「さては」そして、その他には。係助詞「ぞ」「遊ぶ」連体形、係結びの法則。
【中に十ばかりやあらむと見えて】- 後の紫の上の初登場。
【萎えたる】- 『集成』は「なれたる」と本文を改め「糊気の落ちた表着を着て。ふだん着の感じである」と注し、『完訳』は「萎えたる」とし「「萎ゆ」は糊気が落ちる意」と注す。
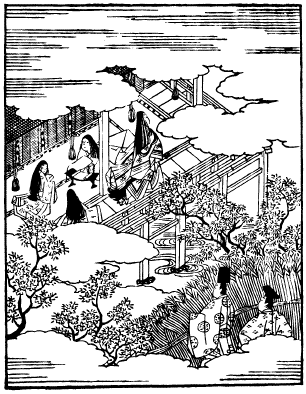
童女とけんかをなさったのですか」
【子なめり】- 「なめり」は断定の助動詞「なる」連体形「る」が撥音便化しさらに無表記+推量の助動詞「めり」終止形、主観的推量を表す。源氏の推測である。
犬君が逃がし
【犬君が逃がしつる】- 童女の名。完了の助動詞「つる」連体形、連体中止法。余意余情表現。
【籠めたりつるものを】- 完了の助動詞「たり」連用形、存続の意+完了の助動詞「つる」連体形、完了の意+終助詞「ものを」。ずっと閉じ籠めておいたのになあ、の意。
ここに座っていた女房が、
どこへ飛んで行ってしまいましたか。
とてもかわいらしく、だんだんなってきましたものを。
烏などが見つけたら大変だわ」
【さいなまるるこそ、いと心づきなけれ】- 受身の助動詞「るる」連体形。係助詞「こそ」「心づきなけれ」已然形、係結びの法則。
【いづ方へかまかりぬる】- 係助詞「か」疑問、完了の助動詞「ぬる」連体形、係結びの法則。
【いとをかしう、やうやうなりつるものを】- 「やうやういとをかしうなりつるものを」という文を「いとをかしう」を強調した倒置表現。完了の助動詞「つる」連体形、完了の意+終助詞「ものを」。
【烏などもこそ見つくれ】- 係助詞「も」+係助詞「こそ」--カ下二「見つくれ」已然形、危惧の念を表す。烏などが見つけたら大変だ。
髪はゆったりととても長く、見苦しくない女のようである。
少納言の乳母と皆が呼んでいるらしい人は、この子のご後見役なのだろう。
【少納言の乳母とこそ人言ふめるは、この子の後見なるべし】- 源氏の推量。物語には語られていないが、周囲の人たちがこの人を少納言の乳母と呼んでいるのを源氏は耳にしていて、今眼前の人をその人かと判断した。係助詞「こそ」は結びの流れ。断定の助動詞「なる」連体形+推量の助動詞「べし」終止形は、源氏の推測。なお大島本のみ「とこそ」とある。『集成』『古典セレクション』共に諸本に従って「とぞ」と本文を改める。『新大系』は底本のままとする。
幼いことよ。聞き分けもなくいらっし
ゃることね。わたしが、このように、今日明日にも思われる寿命を、何ともお考えにならず、雀を追いかけていらっし
ゃることよ。罪を得ることですよと、いつも申し上げていますのに、情けなく」と言って、「こちらへ、いらっしゃい」と言うと、ちょこ
と尼君は言って、また、
「ここへ」
と言うと美しい子は下へすわった。
【おのが、かく】- 『新大系』は「重々しい尼君らしい言い方。夕顔巻に出てきた物の怪が「おのがいとめでたしと見たてまつるをば尋ね思ほさで」と言うのと似るところがある言いざまである」と注す。
【罪得ることぞと】- 生き物を捕えることは仏教の教えからは罪に当る。
【常に聞こゆるを、心憂く】- 接続助詞「を」逆接で続ける。--なのに、残念なことです。
【こちや】- 尼君の詞。間投助詞「や」詠嘆。
【ついゐたり】- 主語は紫の君。完了の助動詞「たり」終止形。膝をついて座った、の意。
つらつきいとらうたげにて、眉 のわたりうちけぶり、いはけなくかいやりたる額 つき、髪 ざし、いみじううつくし。
「ねびゆかむさまゆかしき人 かな」と、目 とまりたまふ。
さるは、「限 りなう心 を尽 くしきこゆる人 に、いとよう似 たてまつれるが、まもらるるなりけり」と、思 ふにも涙 ぞ落 つる。
「ねびゆかむさまゆかしき
さるは、「
「成長して行くさまが楽しみな人だなあ」と、お目がとまりなさる。
それと言うのも、「限りなく心を尽くし申し上げている方に、とてもよく似ているので、目が引きつけられるのだ」と、思うにつけても涙が落ちる。
【ねびゆかむさまゆかしき人かな】- 源氏の感想。
【さるは】- 接続詞「さるは」下の文や句が補足的説明をする。それと言うのも。語り手の、その実は、という文脈。少女の将来像を想像すると、それが自然と藤壺の姿に重なってくるという意識の流れ。地の文からスライドして源氏の心内に立ち入った語り口。
【限りなう心を尽くしきこゆる人に】- 藤壺をさす。以下、源氏の心内。
【まもらるる】- 大島本のみ「まもらる」とある。断定の助動詞「なり」連用形が下接するので、「まもらるる」と連体形に本文を改める。ラ四「まもら」未然形+自発の助動詞「るる」連体形。過去の助動詞「けり」終止形、詠嘆の意。自らそうだったからなのだなあと気づくニュアンス。
【思ふにも涙ぞ落つる】- 係助詞「も」強調のニュアンス。係助詞「ぞ」--タ上二「落つる」連体形、係結びの法則。強調のニュアンス。
「梳 ることをうるさがりたまへど、をかしの御髪 や。
いとはかなうものしたまふこそ、あはれにうしろめたけれ。
かばかりになれば、いとかからぬ人 もあるものを。
故姫君 は、十 ばかりにて殿 に後 れたまひしほど、いみじうものは思 ひ知 りたまへりしぞかし。
ただ今 、おのれ見捨 てたてまつらば、いかで世 におはせむとすらむ」
いとはかなうものしたまふこそ、あはれにうしろめたけれ。
かばかりになれば、いとかからぬ
ただ
とても子供っぽくいらっしゃることが、かわいそうで心配です。
これくらいの年になれば、とてもこんなでない人もありますものを。
亡くなった母君は、十歳程で父殿に先立たれなさった時、たいそう物事の意味は弁えていらっしゃいましたよ。
この今、わたしがお残し申して逝ってしまったら、どのように過ごして行かれるおつもりなのでしょう」
【故姫君は】- 自分の娘でありまた幼い紫の君の母君をさしていう。当時は自分の娘に対しても「君」「たまふ」などと敬語を使う。
【十ばかりにて】- 榊原家本、肖柏本、三条西家本と書陵部本は「十二にて」とある。池田本は「十二(二、ミセケチ、はかりト訂正)にて」とある。御物本と横山本が大島本と同文。河内本も「とをはかりにて」とある。
【殿に後れたまひしほど】- 尼君の夫。故姫君の父親。紫の君の祖父。
【おのれ見捨てたてまつらば】- 謙譲の補助動詞「たてまつら」未然形+接続助詞「ば」仮定条件を表す。
【いかで世におはせむとすらむ】- サ変「おはせ」未然形+推量の助動詞「む」終止形、意志の意。サ変「す」終止形+推量の助動詞「らむ」連体形、視界外推量を表す。
子供心にも、やはりじっと見つめて、伏し目になってうつむいているところに、こぼれかかった髪が、つやつやとして素晴らしく見える。
【うつぶしたるに、こぼれかかりたる髪】- 完了の助動詞「たる」連体形+格助詞「に」場所を表す。
残してゆく露のようにはかないわたしは死ぬに死ねない思いです」
おくらす露ぞ消えんそらなき
またゐたる大人 、「げに」と、うち泣 きて、
どうして尼君様は先立たれるようなことをお考えになるのでしょう」
いかでか露の消えんとすらん
と聞 こゆるほどに、僧都 、あなたより来 て、
「こなたはあらはにやはべらむ。
今日 しも、端 におはしましけるかな。
この上 の聖 の方 に、源氏 の中将 の瘧病 まじなひにものしたまひけるを、ただ今 なむ、聞 きつけはべる。
いみじう忍 びたまひければ、知 りはべらで、ここにはべりながら、御 とぶらひにもまでざりける」とのたまへば、
この
いみじう
今日に限って、端近にいらっしゃいますね。
この上の聖の坊に、源氏中将が瘧病のまじないにいらっしゃったのを、たった今、聞きつけました。
ひどくお忍びでいらっしゃったので、知りませんで、ここにおりながら、お見舞いにも上がりませんでした」とおっしゃると、
と僧都は言った。
【源氏の中将の】- 僧都は「源氏の中将」「光る源氏」と呼称する。
【ただ今なむ、聞きつけはべる】- 係助詞「なむ」、丁寧の補助動詞「はべる」連体形、係結びの法則。
【までざりける】- 「まで」はダ下二「まうで」未然形の縮。他の青表紙諸本は「まうて」とある。『古典セレクション』は「まうで」と改める。『集成』『新大系』は底本のまま。
とても見苦しい様子を、誰か見たでしょうかしら」と言って、簾を下ろしてしまった。
尼君のこう言うのが聞こえて御簾はおろされた。
【人や見つらむ】- 係助詞「や」疑問、マ上一「見」連用形、完了の助動詞「つ」終止形、推量の助動詞「らむ」連体形、視界外推量。係結びの法則。
俗世を捨てた法師の気持ちにも、たいそう世俗の憂えを忘れ、寿命が延びるご様子の方です。
どれ、ご挨拶を申し上げよう」
【見たてまつりたまはむや】- 謙譲の補助動詞「たてまつり」連用形、源氏に対する敬語表現。尊敬の補助動詞「たまは」未然形、尼君に対する敬語表現。推量の助動詞「む」終止形、勧誘の意。終助詞「や」疑問。拝見なさいませんかの意。
【世の憂へ忘れ、齢延ぶる人】- 源氏のすぐれた魅力の一つ。その姿を拝見すると、世の物思いは消え寿命も延びる気持ちになる。あたかも仏様のような人柄。
第四段 若紫の君の素性を聞く
「あはれなる人 を見 つるかな。
かかれば、この好 き者 どもは、かかる歩 きをのみして、よくさるまじき人 をも見 つくるなりけり。
たまさかに立 ち出 づるだに、かく思 ひのほかなることを見 るよ」と、をかしう思 す。
「さても、いとうつくしかりつる児 かな。
何人 ならむ。
かの人 の御代 はりに、明 け暮 れの慰 めにも見 ばや」と思 ふ心 、深 うつきぬ。
かかれば、この
たまさかに
「さても、いとうつくしかりつる
かの
これだから、この好色な連中は、このような忍び歩きばかりをして、よく意外な人を見つけるのだな。
まれに外出しただけでも、このように思いがけないことに出会うことよ」と、興味深くお思いになる。
「それにしても、
とてもかわいかった少女
であるよ。どのような人であろう。あのお方の代わりとして、毎日の慰めに見たいもの
【さるまじき人】- 普通なら見つけられないような人、すなわち意外な人。
【たまさかに立ち出づるだに】- 副助詞「だに」最小限を表す。--だけでも。
【さても】- 以下「慰めにも見ばや」まで、再び源氏の心内。
【かの人の御代はりに】- 藤壺宮をさす。
【明け暮れの慰めにも見ばや】- 「明け暮れ」は毎日の意。「慰め」は気持ちを紛らしたり慰めたりする意だが、藤壺に対する思いが叶えられない代償行為として。「見ばや」は結婚する、一緒に暮らす意。
狭い所なので、源氏の君もそのままお聞きになる。
【惟光を呼び出でさす】- 使役の助動詞「さす」終止形。惟光を呼び出させる意。
「過 りおはしましけるよし、ただ今 なむ、人申 すに、おどろきながら、さぶらべきを、なにがしこの寺 に籠 もりはべりとは、しろしめしながら、忍 びさせたまへるを、憂 はしく思 ひたまへてなむ。
草 の御 むしろも、この坊 にこそ設 けはべるべけれ。
いと本意 なきこと」と申 したまへり。
いと
旅のお宿も、拙僧の坊でお支度致しますべきでしたのに。
残念至極です」と申し上げなさった。
と言うのが使いの伝える僧都の挨拶だった。
【ただ今なむ、人申すに】- 係助詞「なむ」は「申す」に係るが、接続助詞「に」が続き、結びの流れとなっている。
【おどろきながら、さぶらべきを】- 主語は自分。僧都。接続助詞「ながら」一つの動作と同時に他の動作を行うことを表す。接続助詞「を」逆接。気がつくと同時にさっそく伺うべきところを。
【しろしめしながら、忍びさせたまへるを】- 主語は源氏。御存知でいらっしゃりながら。尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、二重敬語。完了の助動詞「る」連体形+格助詞「を」目的格を表す。
【憂はしく思ひたまへてなむ】- 主語は僧都に変わる。謙譲の補助動詞「たまへ」連用形、接続助詞「て」、係助詞「なむ」、結びの省略。お恨みに存じまして。下に、今まで控えておりましたの意をこめる。
【草の御むしろも】- お宿泊の御座所を、という意を、旅にかけて風流にかつ謙虚に申し出たもの。
【この坊にこそ設けはべるべけれ】- 係助詞「こそ」--推量の助動詞「べけれ」已然形、当然の意。係結びの法則。こちらで御準備いたすべきでした。実際は、しなかったの意。
【申したまへり】- 「申し」(「言う」の謙譲語、源氏に対する敬意)連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、僧都に対する敬意、完了の助動詞「り」終止形。敬語が付いていることによって、僧都の伝言という趣。
「いぬる十余日 のほどより、瘧病 にわづらひはべるを、度重 なりて堪 へがたくはべれば、人 の教 へのまま、にはかに尋 ね入 りはべりつれど、かやうなる人 の験 あらはさぬ時 、はしたなかるべきも、ただなるよりは、いとほしう思 ひたまへつつみてなむ、いたう忍 びはべりつる。
今 、そなたにも」とのたまへり。
今、そちらへも」とおっしゃった。
と源氏は惟光に言わせた。
【瘧病にわづらひはべるを】- 接続助詞「を」弱い順接。
【堪へがたく】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「堪えがたう」と改める。『新大系』は底本のまま。
【人の教へのまま】- 。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「人の教へのままに」と改める。『新大系』は底本のまま。
【かやうなる人】- 源氏に験方の行をした聖をさす。
【ただなるよりは】- 普通の行者。
すなはち、僧都参 りたまへり。
法師 なれど、いと心恥 づかしく人柄 もやむごとなく、世 に思 はれたまへる人 なれば、軽々 しき御 ありさまを、はしたなう思 す。
かく籠 もれるほどの御物語 など聞 こえたまひて、「同 じ柴 の庵 なれど、すこし涼 しき水 の流 れも御覧 ぜさせむ」と、せちに聞 こえたまへば、かの、まだ見 ぬ人 びとにことことしう言 ひ聞 かせつるを、つつましう思 せど、あはれなりつるありさまもいぶかしくて、おはしぬ。
かく
法師であるが、とても気がおけて人品も重々しく、世間からもご信頼されていらっしゃる方なので、軽々しいお姿を、きまり悪くお思いになる。
このように籠っている間のお話などを申し上げなさって、「同じ草庵ですが、少し涼しい遣水の流れも御覧に入れましょう」と、熱心にお勧め申し上げなさるので、あの、まだ自分を見ていない人々に大げさに吹聴していたのを、気恥ずかしくお思いになるが、かわいらしかった有様も気になって、おいでになった。
「僧の家というものはどうせ皆寂しい貧弱なものですが、ここよりは少しきれいな水の流れなども庭にはできておりますから、お目にかけたいと思うのです」
僧都は源氏の来宿を乞うてやまなかった。源氏を知らないあの女の人たちにたいそうな顔の吹聴などをされていたことを思うと、しりごみもされるのであるが、心を惹いた少女のことも詳しく知りたいと思って源氏は僧都の坊へ移って行った。
【軽々しき御ありさまを、はしたなう思す】- 主語は源氏。
【同じ柴の庵なれど】- 以下「御覧ぜさせむ」まで、僧都の詞。「柴の庵」は、自分の庵を謙って言った表現。
【御覧ぜさせむ】- サ変「御覧ぜ」未然形+使役の助動詞「させ」未然形+推量の助動詞「む」終止形、意志を表す。
【かの、まだ見ぬ人びと】- まだ源氏の姿を見てない尼君や女房たちの意。
【ことことしう】- 『集成』『新大系』は清音に読むが、『古典セレクション』は「ことごとしう」と濁音に読む。
【言ひ聞かせつるを、つつましう思せど】- 完了の助動詞「つる」連体形+格助詞「を」目的格を表す。「思せ」已然形(「思ふ」の尊敬語)+接続助詞「ど」逆接を表す。
げに、いと心 ことによしありて、同 じ木草 をも植 ゑなしたまへり。
月 もなきころなれば、遣水 に篝火 ともし、灯籠 なども参 りたり。
南面 いと清 げにしつらひたまへり。
そらだきもの、いと心 にくく薫 り出 で、名香 の香 など匂 ひみちたるに、君 の御追風 いとことなれば、内 の人 びとも心 づかひすべかめり。
そらだきもの、いと
月もないころなので、遣水に篝火を照らし、灯籠などにも火を灯してある。
南面はとてもこざっぱりと整えていらっしゃる。
空薫物が、たいそう奥ゆかしく薫って来て、名香の香などが、匂い満ちているところに、源氏の君のおん追い風がとても格別なので、奥の人々も気を使っている様子である。
【月もなきころなれば】- 前に「三月の晦なれば」とあった。旧暦では月のないころである。
【灯籠なども】- 大島本「とゝ(ゝ$う<朱>)ろなとも」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「灯籠などにも」と「に」を補う。『新大系』は底本のまま。
【いと心にくく】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心にくく」と「いと」を削除する。『新大系』は底本のまま。
【心づかひすべかめり】- サ変「す」終止形+「べかめり」は推量の助動詞「べかる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「めり」終止形、視界内推量の意。語り手の推量。
まして
ご自分の罪障の深さが恐ろしく、「どうにもならないことに心を奪われて、一生涯このことを思い悩み続けなければならないようだ。
まして来世は大変なことになるにちがいない」。
お考え続けて、このような出家生活もしたく思われる一方では、昼間の面影が心にかかって恋しいので、
【我が罪のほど】- 以下「いみじかるへきこと」まで、源氏の心内を間接的に叙述。「我が罪」とは、継母である藤壺の宮を恋慕することをさす。
【あぢきなきことに心をしめて、生ける限りこれを思ひ悩むべきなめり】- 「あぢきなきこと」とは継母の藤壺恋慕の不可能な恋。愛執の罪。源氏は「生ける限りこれを思ひ悩む」「べき」(推量の助動詞)「な」(断定の助動詞)「めり」(推量の助動詞、視界内推量)と自制自覚する。
【いみじかるべき】- 推量の助動詞「べき」連体形の下に、御物本は「ことゝ」があり、横山本は「を」を補入。河内本は「ことゝ」とある。「こと」は「を」に誤写される可能性もある。大島本等はナシ。源氏の心内文が地の文に融合して続く。『古典セレクション』は「源氏の心内語。その末尾が切れ目なく地の文に続く」と注す。『源氏物語』には心内文が自然と地の文に変化したり、逆に地の文が競り上がって心内文になっていく叙述法がある。そうした表現世界として鑑賞すべき。
【かうやうなる住まひ】- 物思いを断ち切った出家生活、草庵生活。
【おぼえたまふものから】- 逆接の接続助詞「ものから」によって、源氏の心の両面を語る叙述。この語句によって理不尽複雑な人間心理を語り、この物語に深みを出すことに成功。
お尋ね申したい夢を拝見しましたよ。
今日、
【尋ねきこえまほしき夢を見たまへしかな】- 謙譲の補助動詞「きこえ」未然形。マ上一「見」連用形+謙譲の補助動詞「たまへ」連用形+過去の助動詞「し」連体形+終助詞「かな」詠嘆。
【今日なむ思ひあはせつる】- 係助詞「なむ」--完了の助動詞「つる」連体形、係結びの法則。強調のニュアンス。
と聞 こえたまへば、うち笑 ひて、
「うちつけなる御夢語 りにぞはべるなる。
尋 ねさせたまひても、御心劣 りせさせたまひぬべし。
故按察使大納言 は、世 になくて久 しくなりはべりぬれば、えしろしめさじかし。
その北 の方 なむ、なにがしが妹 にはべる。
かの按察使 かくれて後 、世 を背 きてはべるが、このごろ、わづらふことはべるにより、かく京 にもまかでねば、頼 もし所 に籠 もりてものしはべるなり」と聞 こえたまふ。
その
かの
お知りあそばされたても、きっとがっかりあそばされることでございましょう。
故按察使大納言は、亡くなってから久しくなりましたので、ご存知ありますまい。
その北の方が拙僧の妹でございます。
あの按察使が亡くなって後、出家しておりますのが、最近、患うことがございましたので、こうして京にも行かずにおりますので、頼り所として籠っているのでございます」とお申し上げになる。
僧都の答えはこうだった。
【尋ねさせたまひても】- 尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまひ」連用形、二重敬語。接続助詞「て」+係助詞「も」含みをもたせて表現を和らげる。逆接的文脈となる。
【御心劣りせさせたまひぬべし】- サ変「せ」未然形+尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまひ」連用形、二重敬語、完了の助動詞「ぬ」終止形、確述の意+推量の助動詞「べし」終止形。
【えしろしめさじかし】- 副詞「え」は打消推量の助動詞「じ」終止形と呼応して不可能の意を表す。「しろしめす」は「知る」の尊敬語。
【世を背きてはべるが】- この「が」は格助詞とも接続助詞とも解せる。
【このごろ】- 『集成』は「このころ」と清音、『古典セレクション』『新大系』は「このごろ」と濁音で読む。『岩波古語辞典』には「奈良時代にはコノコロと清音。平安時代にはコノゴロ」とあり、『名義抄』に「今来・比日・今属、コノゴロ」とあるのを典拠とする。
【かく京にもまかでねば】- 主語は僧都。期限を限って山籠もりしている最中。
好色めいた気持ちからではなく、真面目に申し上げるのです」と当て推量におっしゃると、
少女は大納言の遺子であろうと想像して源氏が言うと、
【聞きたまへしは】- 謙譲の補助動詞「たまへ」連用形+過去の助動詞「し」連体形。下に「方はこの姫君か」という内容が省略。『古典セレクション』は「源氏は例の少女を、尼君の娘であると思っているから、このように聞き尋ねる」と注す。
亡くなって、ここ十何年になりましょうか。
故大納言は、入内させようなどと、大変大切に育てていましたが、その本願のようにもなりませず、亡くなってしまいましたので、ただこの尼君が一人で苦労して育てておりましたうちに、誰が手引をしたものか、兵部卿宮がこっそり通って来られるようになったのですが、本妻の北の方が、ご身分の高い人であったりして、気苦労が多くて、明け暮れ物思いに悩んで、亡くなってしまいました。
物思いから病気になるものだと、目の当たりに拝見致しました次第です」
【この十余年にやなりはべりぬらむ】- 断定の助動詞「に」連用形+係助詞「や」疑問。完了の助動詞「ぬ」終止形、推量の助動詞「らむ」視界外推量。
【過ぎはべりにしかば】- 丁寧の補助動詞「はべり」連用形、完了の助動詞「に」連用形、過去の助動詞「しか」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。亡くなってしまいましたので。
【兵部卿宮なむ】- 藤壺の宮の兄。「桐壺」巻に初出。係助詞「なむ」は「語らひつきたまへりける」に係るが、下に接続助詞「を」弱い逆接が続き、結びの流れとなっている。
【なむ、亡くなりはべりにし】- 係助詞「なむ」--過去の助動詞「し」連体形、係結びの法則。丁寧の補助動詞「はべり」連用形、完了の助動詞「に」連用形。
【目に近く見たまへし】- 過去の助動詞「し」連体形、連体中止法。下に体言または感動を表す終助詞「かな」などを言いさした余韻を残した言い方。
など申 したまふ。
「さらば、その子 なりけり」と思 しあはせつ。
「親王 の御筋 にて、かの人 にもかよひきこえたるにや」と、いとどあはれに見 まほし。
「人 のほどもあてにをかしう、なかなかのさかしら心 なく、うち語 らひて、心 のままに教 へ生 ほし立 てて見 ばや」と思 す。
「さらば、その
「
「
「それでは、その人の子であったのだ」とご理解なさった。
「親王のお血筋なので、あのお方にもお似通い申しているのであろうか」と、ますます心惹かれて世話をしたい。
「人柄も上品でかわいらしくて、なまじの小ざかしいところもなく、一緒に暮らして、自分の理想通りに育ててみたいものだなあ」とお思いになる。
【親王の御筋にて】- 以下「かよひきこえたるにや」まで、源氏の心内。「かの人」は藤壺の宮をさす。
【見まほし】- 「見る」は異性を世話する、結婚する意。マ上一「見」未然形+希望の助動詞「まほし」終止形。養女としたいまたは妻としたいの意。
【人のほども】- 以下「うち語らひて心のままに教へ生ほし立てて見ばや」まで、源氏の心内。マ上一「見」未然形+終助詞「ばや」願望を表す。地の文が自然と心中文に移っていく。
その方には、
と、幼 かりつる行方 の、なほ確 かに知 らまほしくて、問 ひたまへば、
それも、女の子で。
それにつけても心配の種として、余命少ない年に思い悩んでおりますようでございます」と申し上げなさる。
【女にてぞ】- 係助詞「ぞ」、下に「ものせ」「し」連体形などの語句が省略。
【なむ、齢の末に思ひたまへ嘆きはべるめる】- 係助詞「なむ」--推量の助動詞「める」連体形、主観的推量の意、係結びの法則。謙譲の補助動詞「たまへ」連用形、丁寧の補助動詞「はべる」連体形。『古典セレクション』は「謙譲の「たまふ」が、第三者の尼君の動作につけて用いられているのは、僧都が尼君の立場に身をおいて代弁しているから」と注す。
「さればよ」と思 さる。
考えるところがあって、通い関わっています所もありますが、本当にしっくりいかないのでしょうか、独り暮らしばかりしています。
まだ不似合いな年頃だと世間並の男同様にお考えになっては、体裁が悪い」などとおっしゃると、
と源氏は言った。
【聞こえたまひてむや】- 僧都に尼君への伝言を依頼する。「聞こえ」は「言ふ」の謙譲語。尊敬の補助動詞「たまひ」連用形、完了の助動詞「て」未然形、確述の意、推量の助動詞「む」終止形、勧誘の意、係助詞「や」疑問の意。あなたから尼君にお話し申し上げてくださいませんか。
【思ふ心ありて】- 「独り住みにてのみなむ」に係る。途中「行きかかづらふ方もはべりながら世に心の染まぬにやあらむ」は挿入句。妻(左大臣家の娘の葵の上)はいるが、意に添わない、の意。
【まだ似げなきほどと】- 女の子の年齢(十歳くらい)が結婚にはまだ早すぎる意。
【はしたなくや】- 主語は自分、源氏をさす。結婚するにはまだ幼い十歳くらいの女の子を迎え取るなど、中途半端なことであろうか、そうではない、親代りになるつもりだ、という決意。『岩波古語辞典』は「ナシは甚だしいの意。落度や失礼・欠点などがあって無作法・ぶしつけであるの意。その結果、体裁がわるくて引込みがつかない状態。また、まともな愛想や情が欠けている意」と解説する。『評釈』は「いても立ってもいられない、穴があったら入りたい、という気持」と注す。
「いとうれしかるべき仰 せ言 なるを、まだむげにいはきなきほどにはべるめれば、たはぶれにても、御覧 じがたくや。
そもそも、女人 は、人 にもてなされて大人 にもなりたまふものなれば、詳 しくはえとり申 さず、かの祖母 に語 らひはべりて聞 こえさせむ」
そもそも、
もっとも、女性というものは、人に世話されて一人前にもおなりになるものですから、詳しくは申し上げられませんが、あの祖母に相談しまして、お返事申し上げさせましょう」
【いはきなき】- 大島本「いはきなき」とあり。他の青表紙諸本「いはけなき」とある。多くの校訂本は「いはけなき」とするが、『新大系』は「いはきなき」のままとする。
【御覧じがたくや】- 接尾語ク型「がたく」連用形+係助詞「や」疑問の意。下に「あらむ」(連体形)などの語句が省略。
【そもそも、女人は、人にもてなされて大人にもなりたまふものなれば】- 大島本「そも/\女人は」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「そもそも女は」と「人」を削除する。『新大系』は底本のままとする。女性は男性(父親または夫)に世話されて一人前の人(女)となる、という当時の考えを引く。断定の助動詞「なれ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【詳しくはえとり申さず】- 副詞「え」打消の助動詞「ず」終止形と呼応して不可能の意を表す。わたしは僧侶の手前男女関係の事柄には立ち入ることはできないが、という意。挿入句。
【かの祖母に語らひはべりて聞こえさせむ】- 「祖母(おば)」は「おほば」の約。使役の助動詞「させ」未然形、推量の助動詞「む」終止形。祖母からお返事をさせましょう、の意。
【ものごはきさましたまへれば】- 『集成』は「取りつく島もないご様子なので」と解し、『古典セレクション』は「堅苦しい様子をしておられるので」と解す。尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、完了の助動詞「れ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件。
初夜のお勤めを、まだ致しておりません。
済ませて参りましょう」と言って、お上りになった。
こう言って僧都は御堂のほうへ行った。
【することはべるころになむ】- 係助詞「なむ」下に「なりぬ」(連体形)などの語句が省略、係結びの結びの省略。
【初夜、いまだ勤めはべらず】- 「初夜」の勤行は、午後六時頃から十時頃までに行う勤行。
すこしねぶたげなる
まして、
少し眠そうな読経が途絶え途絶えにぞっとするように聞こえるなども、何でもない人も、場所柄しんみりとした気持ちになる。
まして、いろいろとお考えになることが多くて、お眠りになれない。
【雨すこしうちそそき】- 時は弥生の晦、月のないころ、しかも雨が降り出した夜。外は漆黒の闇。外の滝の音に混じって室内のかすかな物音が源氏の耳に入ってくる。 【そそき】-清音。『岩波古語辞典』に「江戸時代初期頃からソソギと濁音化した」という。
【山風ひややかに吹きたるに】- 格助詞「に」時間を表す。
【滝のよどみもまさりて】- 『河海抄』は「滝つ瀬の中にも淀はありてふをなど我が恋の淵瀬ともなき」(古今集、恋一、四九三 読人しらず)を指摘する。『完訳』も引歌として引用する。
【所からものあはれなり】- 「所から」は『易林本節用集』に「所柄 トコロカラ」とあり、『日葡辞書』には「トコロカラ トコロガラ」の両方がある。なお『古典セレクション』はこの句、読点。「神妙な思いにもなるが、まして君は」と文を続けて訳す。『集成』『新大系』は清音に読むが、『古典セレクション』は「所がら」と濁音に読んでいる。
【まして】- 以下、主語は源氏。
【まどろませたまはず】- 尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまは」未然形、二重敬語。他の青表紙諸本「まとろまれ給はす」。『集成』『古典セレクション』は「まどろまれたまはず」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。
すこし
奥でも、人々の寝ていない様子がよく分かって、とても密かにしているが、数珠の脇息に触れて鳴る音がかすかに聞こえ、ものやさしくそよめく衣ずれの音を、上品だとお聞きになって、広くなく近いので、外側に立てめぐらしてある屏風の中を、少し引き開けて、扇を打ち鳴らしなさると、意外な気がするようだが、聞こえないふりもできようかということで、いざり出て来る人がいるようだ。
少し後戻りして、
源氏はすぐ隣の室でもあったからこの座敷の奥に立ててある二つの屏風の合わせ目を少し引きあけて、人を呼ぶために扇を鳴らした。先方は意外に思ったらしいが、無視しているように思わせたくないと思って、一人の女が膝行寄って来た。襖子から少し遠いところで、
【人の寝ぬけはひ】- ナ下二「寝」未然形+打消の助動詞「ぬ」連体形。まだ寝ていない様子。なお「ぬ」が完了の助動詞ならば、「けはひ」(名詞)の前は連体形「ぬる」となる。
【扇を鳴らしたまへば】- 主語は源氏。人を呼ぶ合図。
【おぼえなき心地すべかめれど】- 主語は奥の女房。「べかめれ」は推量の助動詞「べかる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記+推量の助動詞「めれ」已然形、視界内推量。源氏側からの推量。語り手と源氏の気持ちが一体化している表現。
【聞き知らぬやうにや】- 打消の助動詞「ぬ」連体形、断定の助動詞「に」連用形、係助詞「や」疑問、下に「ものせむ」などの語句が省略。反語表現。知らないふりはできない、の意。語り手が奥の女房の気持ちを推測した挿入句的表現。
【ゐざり出づる人あなり】- 「あなり」はラ変「ある」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記+推定の助動詞「なり」終止形。源氏側からの推量。語り手と源氏の気持ちが一体化している表現。
【すこし退きて】- 主語は奥の女房。出てきた女房が誰も見えないので戻ろうとしたところ。
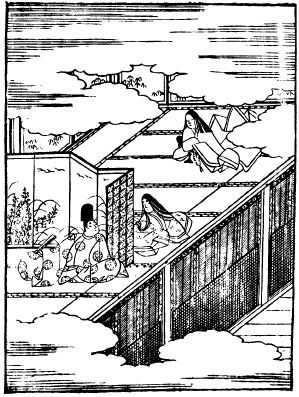
と一言うのを聞いて、源氏が、
【暗きに入りても】- 『源氏釈』は『法華経』の「従冥入於冥、永不聞仏名(冥きより冥きに入りて、永く仏名を聞かざりしなり)」(化城喩品)を指摘する。『古典セレクション』は「案内を頼む女房を釈尊に見立てる」と注す。
【さらに違ふまじかなるものを】- 副詞「さらに」は打消推量の助動詞「まじか」と呼応して、決して--ない、全然--ない、の意を表す。「まじかなる」は打消推量の助動詞「まじかる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記形+断定の助動詞「なる」連体形。接続助詞「ものを」逆接の意。下文を言いさした余意・余情表現。
とのたまふ御声 の、いと若 うあてなるに、うち出 でむ声 づかひも、恥 づかしけれど、
分かりかねますが」と申し上げる。
と言った。
【おぼめきたまはむも】- 尊敬の補助動詞「たまは」未然形+推量の助動詞「む」連体形、婉曲の意。
わたしの旅寝の袖は恋しさの涙の露ですっかり濡れております
旅寝の袖も露ぞ乾かぬ
と聞 こえたまひてむや」とのたまふ。
どなたに」と申し上げる。
【しろしめしたりげなるを】- 「しろしめしたりげ」は「しろしめし」連用形(「知る」の尊敬語)+完了の助動詞「たり」終止形+接尾語「げ」。断定の助動詞「なる」連体形+間投助詞「を」詠嘆。
【誰れにかは】- 係助詞「か」疑問+係助詞「は」。下に「とりつがむ」などの語句が省略。どなたに取り次いだらよろしいのでしょうか、の意。
【聞こゆるならむと】- 断定の助動詞「なら」未然形+推量の助動詞「む」終止形。
この姫君を、年頃でいらっしゃると、お思いなのだろうか。
それにしては、あの『若草を』と詠んだのを、どうしてご存知でいらっしゃることか」と、あれこれと不思議なので、困惑して、遅くなっては、失礼になると思って、
【この君や】- 係助詞「や」疑問、「おはする」連体形に係る、係結びの法則。
【とぞ、思すらむ】- 係助詞「ぞ」、推量の助動詞「らむ」連体形、係結びの法則。
深山に住むわたしたちのことを引き合いに出さないでくださいまし
深山の苔にくらべざらなん
と返辞をさせた。
恐縮ですが、このような機会に、真面目にお話させていただきたいことがあります」と申し上げなさると、尼君、
と源氏が言う。
【ならはぬことになむ】- 係助詞「なむ」。下に「はべる」連体形などの語が省略。
まことに厄介なお方に、どのようなことをお返事申せましょう」とおっしゃると、
尼君はこう言っていた。
【むつかしき】- 大島本は「むつかしき」とある。その他の青表紙諸本は「はつかしき」とある。『評釈』『集成』『古典セレクション』等は「はづかしき」と本文を改める。『新大系』は底本のままとする。
【何ごとをかは答へきこえむ】- 連語「かは」(係助詞「か」+係助詞「は」)推量の助動詞「む」連体形、反語表現の構文。どうお答えしてよいかわからない、の意。
「はしたなうもこそ思 せ」と人 びと聞 こゆ。
と言って、人々は尼君の出るのを勧めた。
【うたてもあらめ】- 係助詞「こそ」の係結び「あらめ」已然形。『集成』は読点。『古典セレクション』は句点。あなたがた若い人が応対するのは嫌でしょうが、年老いたわたしなら構わないでしょう、の気持ち。下文が省略。
【まめやかにのたまふ、かたじけなし】- 源氏が真剣におっしゃているのは畏れ多い、応対しなければ、の気持ち。
とて、ゐざり寄 りたまへり。
仏はもとよりお見通しでいらっしゃいましょう」
【御覧ぜられぬべきついでなれど】- 完了の助動詞「ぬ」終止形、確述+推量の助動詞「べき」連体形、当然の意。
【心にはさもおぼえはべらねば】- 丁寧の補助動詞「はべら」未然形、打消の助動詞「ね」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【仏はおのづから】- 下に「見知りたまひぬらむ」などの語句が省略された形。
【おとなおとなしう】- 尼君の態度。
【つつまれて】- 遠慮されて。主語は源氏。
【とみにもえうち出でたまはず】- 主語は源氏。副詞「え」は打消の助動詞「ず」終止形と呼応して不可能の意を表す。この後、少し間合いがあって、尼君の方から切り出す。
と尼君は言った。
【のたまはせ、聞こえさするも】- 「のたまはせ」の主語は源氏、「聞こえさする」の主語は尼君。それぞれ「言ふ」の最も高い敬語表現、「言ふ」の最も謙った謙譲表現。
【いかが】- 榊原家本、池田本、肖柏本、三条西家本は「あさくはいかゝ」とある。横山本は「あさくは」を補入する。御物本と書陵部本が大島本と同文。「あさくは思はむ」(反語表現)などの語句が省略されている。『集成』は「浅くはいかが」と本文を改める。『古典セレクション』は「いかが」のままとし「浅くはいかが思ひたまへむ」ぐらいの意と注す。
「あはれにうけたまはる御 ありさまを、かの過 ぎたまひにけむ御 かはりに、思 しないてむや。
言 ふかひなきほどの齢 にて、むつましかるべき人 にも立 ち後 れはべりにければ、あやしう浮 きたるやうにて、年月 をこそ重 ねはべれ。
同 じさまにものしたまふなるを、たぐひになさせたまへと、いと聞 こえまほしきを、かかる折 はべりがたくてなむ、思 されむところをも憚 らず、うち出 ではべりぬる」と聞 こえたまへば、
わたしも幼いころに、かわいがってくれるはずの母親に先立たれましたので、妙に頼りない有様で、年月を送っております。
同じような境遇でいらっしゃるというので、お仲間にしていただきたいと、心から申し上げたいのですが、このような機会がめったにございませんので、どうお思いになられるかもかまわずに、申し出たのでございます」と申し上げなさると、
【かの過ぎたまひにけむ御かはりに】- 少女の亡き母親の代りに。過去推量の助動詞「けむ」連体形の下に「人の」などの語句が省略。母親代りの後見を申し出る。
【思しないてむや】- 「思しない」の「い」は「し」のイ音便化。完了の助動詞「て」未然形、確述の意+推量の助動詞「む」終止形+係助詞「や」疑問。相手の意向を問う。
【言ふかひなきほどの齢】- 源氏自身の体験をいう。三歳の時に母親に死別。
【立ち後れはべりにければ】- 丁寧の補助動詞「はべり」連用形、完了の助動詞「に」連用形、過去の助動詞「けれ」已全然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。先立たれてしまったので、というニュアンス。
【年月をこそ重ねはべれ】- 係助詞「こそ」、丁寧の補助動詞「はべれ」已然形、係結びの法則。強調のニュアンスを添える。
【同じさまにものしたまふなるを】- 尊敬の補助動詞「たまふ」終止形、伝聞推定の助動詞「なる」連体形、接続助詞「を」順接、原因理由を表す。いらっしゃるというので、の意。
【たぐひになさせたまへと】- 尊敬の助動詞「せ」連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」命令形、二重敬語。会話文中での用法。
【いと聞こえまほしきを】- 接続助詞「を」逆接を表す。
「いとうれしう思 ひたまへぬべき御 ことながらも、聞 こしめしひがめたることなどやはべらむと、つつましうなむ。
あやしき身一 つを頼 もし人 にする人 なむはべれど、いとまだ言 ふかひなきほどにて、御覧 じ許 さるる方 もはべりがたげなれば、えなむうけたまはりとどめられざりける」とのたまふ。
あやしき
年寄一人を頼りにしている孫がございますが、とてもまだ幼い年頃で、大目に見てもらえるところもございませんようなので、お承りおくこともできないのでございます」とおっしゃる。
と尼君は言うのである。
【つつましうなむ】- 係助詞「なむ」。下に「思ふたまふる」などの語句が省略。
【あやしき身一つを頼もし人にする人】- 「あやしき身一つ」は尼君、自ら謙った表現。「頼もし人にする人」は孫の姫君、紫の君。
【御覧じ許さるる方もはべりがたげなれば】- 「御覧じ」の主体は源氏。受身の助動詞「るる」連体形。断定の助動詞「なれ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。あなた様から大目に見てもらえるところもございませんようなので。 【はべりがたげなれば】-大島本「侍りかたけなれハ」とある。御物本は「侍かたな〔な-補入〕けれは」、横山本、榊原家本、池田本、三条西家本は書陵部本は「侍りかたけれは」。肖柏本が大島本と同文。『集成』『新大系』は底本のまま。『古典セレクション』は「はべりがたければ」と本文を改める。
【えなむうけたまはりとどめられざりける】- 副詞「え」は打消の助動詞「ざり」連用形と呼応して不可能の意を表す。係助詞「なむ」は過去の助動詞「ける」連体形に係る、係結びの法則。強調のニュアンスを添える。可能の助動詞「られ」未然形。
【うけたまはるものを】- 接続助詞「ものを」順接、原因理由を表す。ので、のだから。
【思ひたまへ寄るさま】- 謙譲の補助動詞「たまへ」連用形。
僧都がお戻りになったので、
と言って、源氏は屏風をもとのように直して去った。
【おし立てたまひつ】- 「おし立て」は、「外に立てわたしたる屏風少し引き開けて」を受ける。屏風を閉めた。
【聞こえくる】- 「来る」(連体形)、文の連体中止であるとともに、以下の文の主語ともなる。余情を湛えて次に係ってゆく構文。
感涙を催す滝の音であることよ」
涙催す滝の音かな
これは源氏の作。
心を澄まして住んでいるわたしは驚きません
すめる心は騒ぎやはする
と僧都は答えた。
第五段 翌日、迎えの人々と共に帰京
名も知らない木や草の花々が、色とりどりに散り混じり、錦を敷いたと見える所に、鹿があちこちと立ち止まったり歩いたりしているのも、珍しく御覧になると、気分の悪いのもすっかり忘れてしまった。
【そこはかとなう】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「そこはかとなく」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
【木草の花どもも】- 大島本「はなとも・ゝ」とある。・(朱点)は後のものである。踊り字(ゝ)と読める文字が存在する。『集成』『古典セレクション』『新大系』は「ゝ」を無視して「木草の花ども」と校訂する。
【錦を敷けると見ゆるに】- 格助詞「に」場所を表す。「見ゆる」と「に」の間に「所」などの語が省略。
【めづらしく見たまふに】- 接続助詞「に」順接を表す。御覧になると、の意。
しわがれた声で、とてもひどく歯の間から洩れて聞きにくいのも、しみじみと年功を積んだようで、陀羅尼を誦していた。
【かれたる声の】- 格助詞「の」同格を表す。しわがれた声で、の意。
僧都は、見慣れないような果物を、あれこれと、谷の底から採ってきては、ご接待申し上げなさる。
【世に見えぬ】- 大島本「世にみえぬ」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「見えぬ」と「世に」を削除する。『集成』『新大系』は底本のままとする。
かえって残念に存じられてなりません」
【なかなかにも思ひたまへらるべきかな】- 『集成』は「かえって執心が残りそうにおもわれることでございます」と解し、『完訳』は「なまじ源氏と会ったために、かえって別れがたくつらい気持」と注し、「かえってお名残り惜しゅう存ぜられるしだいでございます」と解す。「たまへ」(下二段、謙譲の補助動詞)「らる」(自発の助動詞)「べき」(推量の助動詞)「かな」(詠嘆の終助詞)。
そのうち、この花の時期を過ごさずに参りましょう。
【心とまりはべりぬれど】- 丁寧の補助動詞「はべり」連用形、完了の助動詞「ぬれ」已全然形+接続助詞「ど」逆接を表す。
【内裏よりもおぼつかながらせたまへるも】- 「内裏」は帝をさす。格助詞「より」起点を表す。係助詞「も」同類を表す。尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまふ」連体形、最高敬語。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「内裏より」と「も」を削除する。『新大系』は底本のままとする。
【かしこければなむ】- 係助詞「なむ」の下に「まからむ」連体形などの語句が省略。帰らねばなりません、の意が省略。
【今、この花の折過ぐさず参り来む】- 辞去の挨拶。改めてお礼に参りましょうという意であるが、本人自身がではなく使者が代わって参上することであろう。
この山桜の美しいことを風の吹き散ら
風よりさきに来ても見るべく」
【声づかひさへ、目もあやなるに】- 副助詞「さへ」添加の意。断定の動詞「なる」連体形+接続助詞「に」順接、原因理由を表す。
咲くのにめぐり逢ったような気がして深山桜には目も移りません」
深山桜に目こそ移らね
「長い間にまれに一度咲くという花は御覧になることが困難でしょう。私とは違います」
と言っていた。
【かたかなるものを】- 「かたか」は形容詞「かたかる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記の形。伝聞推定の助動詞「なる」連体形+接続助詞「ものを」逆接を表す。難しいというのに。
まだ見たこともない花のごとく美しいお顔を拝見致しました」
まだ見ぬ花の顔を見るかな

と、うち泣 きて見 たてまつる。
聖 、御 まもりに、独鈷 たてまつる。
見 たまひて、僧都 、聖徳太子 の百済 より得 たまへりける金剛子 の数珠 の、玉 の装束 したる、やがてその国 より入 れたる筥 の、唐 めいたるを、透 きたる袋 に入 れて、五葉 の枝 に付 けて、紺瑠璃 の壺 どもに、御薬 ども入 れて、藤 、桜 などに付 けて、所 につけたる御贈物 ども、ささげたてまつりたまふ。
聖は、ご守護に、独鈷を差し上げる。
それを御覧になって、僧都は、聖徳太子が百済から得られた金剛子の数珠で、玉の飾りが付いているのを、そのままその国から入れてあった箱で、唐風なのを、透かし編みの袋に入れて、五葉の松の枝に付けて、紺瑠璃の壺々に、お薬類を入れて、藤や桜などに付けて、場所柄に相応しいお贈物類を、捧げて差し上げなさる。
【聖徳太子の百済より得たまへりける金剛子の数珠の】- 「聖徳太子の」の「の」は格助詞、主格を表し、「数珠の」の「の」は格助詞、同格を表す。『岩波古語辞典』に「室町時代までクタラと清音か」とあり、図書寮本「類聚名義抄」に「百済瑟、久太良古度」とあり明確に清点があるという。なお、書陵部本は「くたらく」とある。御物本も書陵部本同様に「くたらく」とあり後出の「く」をミセケチにする。一方、横山本は「くたらく」と後出の「く」を補入、榊原家本、池田本、三条西家本は「ふたらく」とある。
【やがてその国より入れたる筥の】- 「筥の」の「の」は格助詞、同格を表す。
【五葉の枝に付けて】- 「藤、桜などに付けて」と共に贈り物を時節や場所柄に応じて植物の枝に結んで贈る。
【法師の布施ども、まうけの物ども、さまざまに取りにつかはしたりければ】- 語られてはいないが、源氏は昨日京に帰した供人に迎えに来るときに、お礼のお布施の品々を持参するよう申し伝えていた。『古典セレクション』は「さまざまに取り遣はしたりければ」としている。
【出でたまふ】- いったん「出でたまふ」といってからその間の内容を後から詳しく語る。
【まねびきこえたまへど】- 謙譲の補助動詞「聞こえ」連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」已然形+接続助詞「ど」逆接を表す。僧都がそっくりそのまま尼君に申し上げなさるが。
もし、君にお気持ちがあるならば、もう四、五年たってから、ともかくも」とおっしゃると、「しかじか」と同じようにばかりあるので、つまらないとお思いになる。
と尼君は言うだけだった。源氏は前夜聞いたのと同じような返辞を僧都から伝えられて自身の気持ちの理解されないことを歎いた。
【いま四、五年を過ぐしてこそは】- 大島本「四五年」と表記。尼君の詞中の語句なので、「よとせ、いつとせ」と読んでおく。係助詞「こそ」、「ともかくも」の下に「考えめ」已然形などの語句が省略。
【さなむ】- 尼君の詞を源氏に伝言。語り手がそれを省略して「さなむ」と表現したもの。係助詞「なむ」、下に「はべりき」連体形などの語句が省略。
【本意なしと思す】- 『集成』は「がっかりなさる」と解し、『完訳』は「はがゆい気持」と解す。
今朝は霞の空に立ち去りがたい気がします」
今朝は霞の立ちぞわづらふ
そのようなことをおっしゃるお気持ちを見たいものです」
霞むる空のけしきをも見ん
【いとあてなるを】- 『集成』『古典セレクション』は「気品のある文字を」と格助詞「を」目的格で訳す。接続助詞「を」逆接、とても上品であるが、とも訳せよう。
頭中将、左中弁、その他のご子息もお慕い申して、
【いづちともなくて、おはしましにけること】- 左大臣の詞を迎えの人々が言上した間接話法的詞。「おはします」は「おはす」よりさらに一段高い尊敬語。
【頭中将、左中弁】- 頭中将は「桐壺」巻に蔵人少将として初出、「帚木」巻に頭中将、「夕顔」巻に三位中将。左中弁は「夕顔」巻に蔵人弁として初出。頭中将の異母の弟。
「かうやうの御供 には、仕 うまつりはべらむ、と思 ひたまふるを、あさましく、おくらさせたまへること」と恨 みきこえて、「いといみじき花 の蔭 に、しばしもやすらはず、立 ち帰 りはべらむは、飽 かぬわざかな」とのたまふ。
などと恨んで、
「美しい花の下で遊ぶ時間が許されないですぐにお帰りのお供をするのは惜しくてならないことですね」
とも言っていた。
【と思ひたまふるを】- 謙譲の補助動詞「たまふる」連体形、接続助詞「を」逆接を表す。
【おくらさせたまへること】- 大島本「おくらせ」の「ら」と「せ」の間に朱筆で「さ」を補入。なお「後る」は自ラ下二段動詞であって、四段動詞ではない。その他動詞形は「後(おく)らす」(他サ四)「後(おく)らかす」(他サ四)である。よって「後らさ」未然形+尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまへ」已然形+完了の助動詞「る」連体形。
【いといみじき花の蔭に】- 以下「飽かぬわざかな」まで、迎えの公達の詞。「花の蔭」は歌語。桜の花の咲いている木の蔭。『新大系』は「いざ今日は春の山辺にまじりなむ暮れなばなげの花の蔭かは」(古今集・春下・素性)を参考として指摘。他に「春来れば木隠れ多き夕月夜おぼつかなしも花蔭にして」(後撰集・春中・読人しらず)などがある。
【立ち帰りはべらむは】- 丁寧の補助動詞「はべら」未然形+推量の助動詞「む」連体形、仮定の意を表す。
落ちて来る水の様子など、風情のある滝のほとりである。
頭中将は、懐にしていた横笛を取り出して、吹き澄ましている。
弁の君は、扇を軽く打ち鳴らして、「豊浦の寺の、西なるや」と謡う。
普通の人よりは優れた公達であるが、源氏の君の、とても苦しそうにして、岩に寄り掛かっておいでになるのは、またとなく不吉なまでに美しいご様子に、他の何人にも目移りしそうにないのであった。
いつものように、篳篥を吹く随身、笙の笛を持たせている風流人などもいる。
【豊浦の寺の、西なるや】- 催馬楽「葛城」の一節。「葛城(かづらき)の 寺の前なるや 豊浦(とよら)の寺の 西なるや 榎(え)の葉井に 白璧(しらたま)沈(しづ)くや 真白璧沈くや おおしとと おしとど しかしては 国ぞ栄えむや 我家(わいへ)らぞ 富せむや おおしとと としとんど おおしとんど としとんど」。源氏の資質を讃美した。
【人よりは異なる君達を】- 接続助詞「を」逆接を表す。この二人は普通の公達以上に優れた方であるが、それでも源氏の君の素晴しさには、という文脈。
【源氏の君、いといたううち悩みて、岩に寄りゐたまへる】- 国宝『源氏物語絵巻』「若紫」断簡(東京国立博物館蔵)に描かれている。
【たぐひなくゆゆしき御ありさまにぞ】- この世にまたとなく不吉なまでに美しいお姿なのでの意。
【持て参りて】- 「持て」は「持ちて」の約。
と言いながらも、源氏が快く少し弾いたのを最後として皆帰って行った。
【けに憎からず】- 大島本は「けにゝ(ゝ+く<朱>)からす」とある。『集成』『古典セレクション』共に「けにくからず」と本文を改める。『新大系』は「げににくからず」と整定する。
【皆立ちたまひぬ】- 一行は北山を出発なさった。
まして、
彼ら以上に、室内では、年老いた尼君たちなどは、まだこのようにお美しい方の姿を見たことがなかったので、「この世の人とは思われなさらない」とお噂申し上げ合っていた。
僧都も、
【この世のものともおぼえたまはず】- 尼君たちの噂の詞。「たまふ」(四段尊敬の補助動詞)は、源氏に対する敬語表現。思われなさらないの意。仏菩薩の化身かと思う、という意。
と源氏の君のことを言って涙をぬぐっていた。
【かかる御さまながら】- 接続助詞「ながら」連用修飾をする。そのままで、の意。
【生まれたまへらむと】- 尊敬の補助動詞「たまへ」已然形+完了の助動詞「ら」未然形+推量の助動詞「む」連体形、推量の意。
などとほめていた。
【なりておはしませよ】- 接続助詞「て」順接、「おはしませ」命令形+終助詞「よ」強調のニュアンス。
お人形遊びにも、お絵描きなさるにも、「源氏の君」と作り出して、美しい衣装を着せ、お世話なさる。
第六段 内裏と左大臣邸に参る
「とてもひどくお痩せになってしまったものよ」とおっしゃって、ご心配あそばした。
聖の霊験あらたかであったことなどを、お尋ねあそばす。
詳しく奏上なさると、
【いといたう衰へにけり】- 桐壺帝の詞。「いたう」は形容詞「いたく」連用形のウ音便形。完了の助動詞「に」連用形+過去の助動詞「けり」終止形、詠嘆の意。
【ゆゆしと思し召したり】- 「思し召し」は「思ふ」の最高敬語。
【問はせたまふ】- 尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまふ」終止形、二重敬語。
修行の功績は大きいのに、朝廷からご存知になられなかったことよ」と、尊重なさりたく仰せられるのであった。
と敬意を表しておいでになった。
【なるべき者にこそあなれ】- 推量の助動詞「べき」連体形、適当の意。断定の助動詞「に」連用形、係り助詞「こそ」。「あなれ」は「あるなれ」の「る」が撥音便化しさらに無表記の形。推定の助動詞「なれ」已然形、係結びの法則。強調のニュアンス。
【行ひの労は積もりて】- 接続助詞「て」逆接の意。
【朝廷にしろしめされざりけること】- 「しろしめさ」未然形は「知る」の最高敬語。受身の助動詞「れ」未然形+打消の助動詞「ざり」連用形+過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意。
【尊がりのたまはせけり】- 「のたまはせ」連用形は「言ふ」の最高敬語。
「御迎 へにもと思 ひたまへつれど、忍 びたる御歩 きに、いかがと思 ひ憚 りてなむ。
のどやかに一 、二日 うち休 みたまへ」とて、「やがて、御送 り仕 うまつらむ」と申 したまへば、さしも思 さねど、引 かされてまかでたまふ。
のどやかに
のんびりと、一、二日、お休みなさい」と言って、「このまま、お供申しましょう」と申し上げなさるので、そうしたいとはお思いにならないが、連れられて退出なさる。
と言って、また、
「ここからのお送りは私がいたしましょう」
とも言ったので、その家へ行きたい気もなかったが、やむをえず源氏は同道して行くことにした。
【思ひたまへつれど】- 謙譲の補助動詞「たまへ」連用形+完了の助動詞「つれ」已然形+接続助詞「ど」逆接を表す。
【忍びたる御歩きに】- 格助詞「に」事の起こるもとを示す。によって、の意。
【いかがと思ひ憚りてなむ】- 係助詞「なむ」、下に「はべり」+過去の助動詞「き」連体形などの語句が省略。
【一、二日】- 大島本に「一二日」と漢字表記である。いま「いち、ににち」と字音で読んでおく。和読み「ひとひ、ふつか」。
【やがて、御送り仕うまつらむ】- 左大臣の詞。ラ四動詞「仕うまつら」未然形+推量の助動詞「む」終止形、意志。
【さしも思さねど】- 主語は源氏。副詞「さしも」。「思さ」未然形+打消の助動詞「ね」已然形+接続助詞「ど」確定逆接。
【引かされてまかでたまふ】- ラ下二動詞「引かされ」連用形+接続助詞「て」。
大切にお世話申し上げなさるお気持ちの有り難いことを、やはり胸のつまる思いがなさるのであった。
【自らは引き入りてたてまつれり】- 男性の場合、牛車の最上席は前方右側である。第二席がその向かいの左側、第三席は左側後ろ、第四席は右側後ろ席となる。時計の反対回り。女性の場合は、前方左側の席が最上席で、反対の時計回りの順。男女相乗りの場合は前方右側が男性、左側が女性となる。ラ四「たてまつれ」已然形(「乗る」の尊敬語)+完了の助動詞「り」終止形。
【さすがに】- やはりの意。『完訳』は「葵の上には気がすすまないが、それでも左大臣に対しては」と解す。
【心苦しく思しける】- 胸のつまる思い、気の毒なの意。『古典セレクション』は「おいたわしくお思いになるのだった」と訳す。
【久しく見たまはぬほど】- 主語は源氏。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「久しう」とウ音便形に改める。『』は底本のまま。
ただ
まるで絵に描いた姫君のように、座らされて、ちょっと身体をお動かしになることも難しく、きちんと行儀よく座っていらっしゃるので、心の中の思いを話したり、北山行きの話をもお聞かせたりするにも、話のしがいがあって、興味をもってお返事をなさって下さろうものなら、情愛もわこうが、少しも打ち解けず、源氏の君をよそよそしく気づまりな相手だとお思いになって、年月を重ねるにつれて、お気持ちの隔たりが増さるのを、とても辛く、心外なので、
【とみにも出でたまはぬを】- 係助詞「も」強調のニュアンス。格助詞「を」目的格を表す。
【からうして】- 『集成』『新大系』は「からうして」と清音、『古典セレクション』は「からうじて」と濁音で読む。『岩波古語辞典』は「古くは清音か」といい、語源と『日葡辞書』の用例を典拠にあげる。
【渡りたまへり】- 主語は葵の上。大殿邸の源氏の部屋に葵の上のほうが出て来たという意。『完訳』は「女君の部屋から源氏の前へ」と解す。
【ただ絵に描きたるものの姫君のやうに】- 当時の物語絵の中の姫君のように美しく着飾られているがじっとしていて動かない。
【し据ゑられて】- ワ下二動詞「し据ゑ」未然形+受身の助動詞「られ」連用形、接続助詞「て」。
【思ふこともうちかすめ】- 以下「御心の隔てもまさるを」まで、源氏の心中と地の文とが融合したような叙述である。その長文が源氏の屈曲した心の綾を表現する。「思ふこともうちかすめ」と「山道の物語をも聞こえむ」は並列の構文。
【言ふかひありて、をかしういらへたまはばこそ、あはれならめ】- 挿入句。係助詞「こそ」推量の助動詞「め」已然形、係結びの法則、逆接用法で下文に続く。
【世には心も解けず】- 『古典セレクション』「「世には」は強調の語法。じつにまあ、ことのほかに、の意」と注す。副詞「世に」実に。
【うとく恥づかしきものに思して】- 主語は葵の上。
【年のかさなるに添へて】- 源氏と葵の上の結婚は「桐壺」巻の源氏十二歳の元服の夜であった。当「若紫」巻は、新年立によれば、源氏十八歳。六年の歳月が流れる。
【いと苦しく、思はずに】- 主語は源氏。「思はずに」は連語「思はず」連用形、意外だの意+断定の助動詞「に」連用形。いわゆる形容動詞「思はずなり」の連用形。
私がひどく苦しんでおりました時にも、せめてどうですかとだけでも、お見舞い下さらないのは、今に始まったことではありませんが、やはり残念で」
【世の常なる御気色を見ばや】- 「世」は夫婦仲。終助詞「ばや」話者の願望を表す。
【いかがとだに】- 副助詞「だに」最小限を表す。せめて--だけでも。
【問ひたまはぬこそ】- 御物本、榊原家本、池田本、三条西家本は「とはせ給はぬこそ」という二重敬語表現。横山本は「とうたまはぬこそ」、肖柏本は「とふらひ給はぬこそ」とある。書陵部本が大島本と同文。河内本は「とはせ給はぬも」とある。『集成』は「とはせ給はぬこそ」と本文を改める。『古典セレクション』『新大系』は底本のままとする。係助詞「こそ」は断定の助動詞「なれ」已然形に係るが、下に接続助詞「ど」逆接が続いたために、結びの流れとなっている。
【なほうらめしう】- 「うらめしく」のウ音便形。言いさした形で余意余情表現。
と聞 こえたまふ。
からうして、
からうして、
ようやくのことで、
「まれまれは、あさましの御 ことや。
訪 はぬ、など言 ふ際 は、異 にこそはべるなれ。
心憂 くものたまひなすかな。
世 とともにはしたなき御 もてなしを、もし、思 し直 る折 もやと、とざまかうさまに試 みきこゆるほど、いとど思 ほし疎 むなめりかし。
よしや、命 だに」
よしや、
訪ねない、などという間柄は、他人が使う言葉でございましょう。
嫌なふうにおっしゃいますね。
いつまでたっても変わらない体裁の悪い思いをさせるお振る舞いを、もしや、お考え直しになるときもあろうかと、あれやこれやとお試し申しているうちに、ますますお疎んじなられたようですね。
仕方ない、
【訪はぬ、など言ふ際は】- 葵の上の「問はぬはつらき」を受けて切り返す。『古典セレクション』は「「問はぬはつらき」などという言葉は、忍んで通う程度の関係ならともかく、世間公認の夫婦である源氏と葵の上との仲で言うべきことではない、といなした」と注す。
【異にこそはべるなれ】- 「異」は他の夫婦。係助詞「こそ」、丁寧語「はべる」連体形、断定の助動詞「なれ」已然形、係結びの法則。強調のニュアンス。
【はしたなき御もてなし】- 『集成』は「取り付く島もないお仕打ち」と解す。
【とざまかうさまに】- 「左之右之、トザマカウサマ、自由自在義也(文明本節用集)」(岩波古語辞典)。
【いとど思ほし疎むなめりかし】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思し」と校訂。『新大系』は底本のまま。「思ほし」のまま。「なめり」は断定の助動詞「なる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「めり」終止形、主観的推量、終助詞「かし」念押し。
【よしや、命だに】- 『奥入』は「命だに心にかなふものならば何か別れの悲しからまし」(古今集 離別 三八七 しろめ)を指摘する。生きているうちにいつか直る時があろうの意。『集成』は「引歌があろうが、明らかでない」と注す。『完訳』は「やや不審」という。
女君は、すぐにもお入りにならず、お誘い申しあぐねなさって、溜息をつきながら横になっているものの、何となくおもしろくないのであろうか、眠そうなふりをなさって、あれやこれやと夫婦仲を思い悩まれることが多かった。
【なま心づきなきにやあらむ】- 語り手が源氏の心情を想像した挿入句。『休聞抄』に「双也」とあり草子地と指摘。
【ねぶたげにもてなして】- 『古典セレクション』は「源氏の、葵の上を避ける態度」と注す。
この若草 の生 ひ出 でむほどのなほゆかしきを、「似 げないほどと思 へりしも、道理 ぞかし。
言 ひ寄 りがたきことにもあるかな。
いかにかまへて、ただ心 やすく迎 へ取 りて、明 け暮 れの慰 めに見 む。
兵部卿宮 は、いとあてになまめいたまへれど、匂 ひやかになどもあらぬを、いかで、かの一族 におぼえたまふらむ。
ひとつ后腹 なればにや」など思 す。
ゆかりいとむつましきに、いかでかと、深 うおぼゆ。
いかにかまへて、ただ
ひとつ
ゆかりいとむつましきに、いかでかと、
申し込みにくいものだなあ。
何とか手段を講じて、ほんの気楽に迎え取って、毎日の慰めとして一緒に暮らしたい。
父兵部卿宮は、とても上品で優美でいらっしゃるが、つややかなお美しさはないのに、どうして、あの一族に似ていらっしゃるのだろう。
父宮が同じお后様からお生まれになったからだろうか」などとお考えになる。
血縁がとても親しく感じられて、何とかしてと、深く思われる。
【なほゆかしきを】- 接続助詞「を」順接、原因理由を表す。ので。
【似げないほどと思へりしも】- 主語は尼君。尼君の態度に対して特に敬語を使っていない。
【匂ひやかになどもあらぬを】- 接続助詞「を」逆接を表す。
【かの一族】- 先帝の一族。具体的には叔母の藤壺宮。大島本「ひとそう」と訓読した仮名表記。
【おぼえたまふらむ】- 主語は紫の上。「おぼえ」は、似る意。
【ひとつ后腹なればにや】- 主語は兵部卿宮。断定の助動詞「なれ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。断定の助動詞「に」連用形+係助詞「や」疑問を表す。
第七段 北山へ手紙を贈る
僧都にもそれとなくお書きになったのであろう。
尼上には、
【御文たてまつれたまへり】- 他下二「たてまつれ」連用形。人をして手紙を差し上げ、の意。尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、完了の助動詞「り」終止形。
【僧都にもほのめかしたまふべし】- 推量の助動詞「べし」終止形、語り手の想像。
これほどに申し上げておりますことにつけても、並々ならぬ気持ちのほどを、お察しいただけたら、どんなに嬉しいことでしょうか」
【思ひたまふるさまをも】- 主語は源氏。謙譲の補助動詞「たまふる」連体形。
【えあらはし果てはべらずなりにしをなむ】- 副詞「え」は打消の助動詞「ず」連用形と呼応して不可能の意を表す。丁寧の補助動詞「はべら」未然形、手紙文中の用例。官僚の助動詞「に」連用形+過去の助動詞「し」連体形+格助詞「を」目的格+係助詞「なむ」。下に「口惜しう思ひ給ふる」などの語句が省略。言いさした形で、余意余情表現。
【おしなべたらぬ志のほどを】- バ下二「おしなべ」連用形+完了の助動詞「たら」未然形+打消の助動詞「ぬ」連体形。並々ならない、の意。
【御覧じ知らば】- 「知ら」未然形+接続助詞「ば」順接の仮定条件を表す。
【いかにうれしう】- 「うれしう」連用中止法。下に「思はむ」などの語句が省略。
中に、小さく結んで、
心のすべてをそちらに置いて来たのですが
心の限りとめてこしかど
ご筆跡などはさすがに素晴らしくて、ほんの無造作にお包みになった様子も、年配の人々のお目には、眩しいほどに素晴らしく見える。
どのようにお返事申し上げましょう」と、お困りになる。
まだ「難波津」をさえ、ちゃんと書き続けませんようなので、お話になりません。
それにしても、
【思ひたまへなされしを】- 謙譲の補助動詞「たまへ」連用形、自発の助動詞「れ」連用形、過去の助動詞「し」連体形+接続助詞「を」逆接を表す。
【まだ「難波津」をだに】- 『紫明抄』は「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」(古今集仮名序)を指摘。初心者の手習い歌である。副助詞「だに」最小限を表す。
【はかばかしう続けはべらざめれば】- 仮名文字を連綿体で書くこと。「ざめれ」は「打消の助動詞「ざる」連体形「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「めれ」已然形、主観的推量+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【かひなくなむ】- 係助詞「なむ」、下に「はべる」連体形などの語が省略。
【さても】- 連語(副詞「さて」+係助詞「も」)そんな状態でもやはり。
その散る前にお気持ちを寄せられたように頼りなく思われます
心とめけるほどのはかなさ
というのが尼君からの返事である。
僧都のお返事も同じようなので、残念に思って、二、三日たって、惟光を差し向けなさる。
【惟光をぞたてまつれたまふ】- 係助詞「ぞ」は尊敬の補助動詞「たまふ」連体形に係る、係結びの法則。強調のニュアンス。下二「たてまつれ」連用形、使者を差し上げる、意。
その人を尋ねて、詳しく相談せよ」などとお言い含めなさる。
「何とも、
どのようなことにもご関心を寄せられる好き心だなあ。あれほど子供じみた様子であった様子なのに」と、はっきりとで
などと源氏は命じた。どんな女性にも関心を持つ方だ、姫君はまだきわめて幼稚であったようだのにと惟光は思って、真正面から見たのではないが、自身がいっしょに隙見をした時のことを思ってみたりもしていた。
【と言ふ人あべし】- 「あべし」はラ変「ある」連体形「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「べし」終止形。
【さも、かからぬ隈なき】- 以下「いはけなげなかりしけはひを」まで、惟光の心中。副詞「さも」まったく、いかにも。「かから」未然形は「関る・係る・懸る・掛る」の意+打消の助動詞「ぬ」連体形。抜け目ない。
【さばかりいはけなげなりしけはひを】- 副詞「さばかり」。過去の助動詞「し」連体形。接続助詞「を」逆接を表す。あれほど幼げな様子だったのに。
わざと、かう御文 あるを、僧都 もかしこまり聞 こえたまふ。
少納言 に消息 して会 ひたり。
詳 しく、思 しのたまふさま、おほかたの御 ありさまなど語 る。
言葉多 かる人 にて、つきづきしう言 ひ続 くれど、「いとわりなき御 ほどを、いかに思 すにか」と、ゆゆしうなむ、誰 も誰 も思 しける。
少納言の乳母に申し入れて面会した。
詳しく、お考えになっておっしゃったご様子や、日頃のご様子などを話す。
多弁な人なので、もっともらしくいろいろ話し続けるが、「とても無理なお年なのに、どのようにお考えなのか」と、大変心配なことと、どなたもどなたもお思いになるのであった。
【詳しく、思しのたまふさま、おほかたの御ありさまなど語る】- 主語は惟光。「詳しく」は「語る」に掛かる。「思しのたまふさま」と「おほかたの御ありさま」は並列の構文。
【言葉多かる人にて】- 惟光の人柄。『集成』は「多弁な人物で」と解し、『完訳』は「口の達者な男」と解す。
【いとわりなき御ほどを、いかに思すにか】- 尼君と僧都の心中。源氏の心を思う。
【誰も誰も思しける】- 「誰も誰も」は「思す」という敬語表現なので、僧都と尼上のこと。過去の助動詞「ける」連体形、係助詞「なむ」の係結びの法則。
一つずつ離してお書きになる姫君のお字をぜひ私に見せていただきたい。
ともあった。例の中に封じたほうの手紙には、
【なほ見たまへまほしき】- 謙譲の補助動詞「たまへ」連用形、希望の助動詞「まほしき」連体形、係助詞「なむ」の係結びの法則。
どうしてわたしからかけ離れていらっしゃるのでしょう」
など山の井のかけ離るらん
浅いお心のままどうして孫娘を御覧に入れられましょう」
浅きながらや影を見すべき
尼君が書いたのである。、
と言っていたというのである。源氏はたよりない気がしたのであった。
【このごろ】- 『古典セレクション』は「このごろ」と濁音に読む。『集成』『新大系』は清音に読んでいる。「今来・比日・今属、コノゴロ」(名義抄)。「奈良時代にはコノコロと清音。平安時代以後コノゴロ」(岩波古語辞典)。
【聞こえさすべき】- 「聞こえさす」終止形は「言ふ」の最も丁重な謙譲語。推量の助動詞「べき」連体形、係助詞「なむ」と係結びの法則。
【とあるを、心もとなう思す】- 助詞「を」について、『今泉忠義訳』は「と少納言からの口上なので」と接続助詞、順接の意に、『古典セレクション』は「少納言の乳母の返事があるのを」と格助詞、目的格の意に、それぞれ訳す。
第二章 藤壺の物語 夏の密通と妊娠の苦悩物語
第一段 夏四月の短夜の密通事件
主上が、お気をもまれ、ご心配申し上げていらっしゃるご様子も、まことにおいたわしく拝見しながらも、せめてこのような機会にもと、魂も浮かれ出て、どこにもかしこにもお出かけにならず、内裏にいても里邸にいても、昼間は所在なくぼうっと物思いに沈んで、夕暮れになると、王命婦にあれこれとおせがみになる。
【まかでたまへり】- 後の「賢木」巻に三条宮邸と知られる。尊敬の補助動詞「たまへ」已然形+完了の助動詞「り」完了の意。
【いといとほしう見たてまつりながら】- 主語は源氏。父帝に対する気持ち。
【かかる折だにと】- 副助詞「だに」最小限の願望。せめてこのような機会にでもと。
【つれづれと】- 御物本は「つく(く$れ)つく(く$れ)と」。榊原家本、池田本、肖柏本、三条西家本、書陵部本は「つくつくと」とある。横山本は大島本と同文。河内本は「つくつくと」とある。
【王命婦】- 藤壺の宮付きの女房。その呼称によって皇族出身の命婦と知られる。
【わびしきや】- 間投助詞「や」詠嘆。語り手の感想を交えた叙述。萩原広道『評釈』は「源氏の心を評じたる也」と指摘。『集成』は「たまさかの、はかない逢瀬を悲しむ源氏の気持」と解し、『完訳』は「予想外の事態に処しかねる気持」と解す。この逢瀬が夢ではなく現実であるにもかかわらず、それが現実のことと思えない、つらさ。
【さてだにやみなむと】- 藤壺の心中。副助詞「だに」最小限。完了の助動詞「な」未然形、確述の意+推量の助動詞「む」終止形、意志。せめてそれきりだけで終わりにしたい、の意。
【深う思したるに】- 主語は藤壺。接続助詞「に」逆接を表す。
【いと憂くて】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心憂くて」と「心」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。『古典セレクション』は「この「心憂し」は「憂し」とほぼ同意。「憂し」は、自分自身のせいでつらく思う意で、自らの運命を痛恨する気持。藤壺は、源氏との関係を避けがたい宿運として嘆く」と注す。
【いみじき御気色なるものから、なつかしうらうたげに】- 藤壺の心中叙述から源氏の見た藤壺像へと文章は変化し移ってゆく。
【さりとてうちとけず】- すっかり馴れ馴れしくはならないのは、高貴な貴族にとって品位を保つ上で大切なこと。
【なほ人に似させたまはぬを】- 副詞「なほ」。尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまは」未然形、最高敬語。打消の助動詞「ぬ」連体形+格助詞「を」目的格を表す。
【などか】- 以下「たまはざりけむ」まで、源氏の心中。
【なのめなることだに】- 「なのめ」は普通、平凡の意。副助詞「だに」最小限を表す。
【つらうさへぞ思さるる】- 副助詞「さへ」添加を表す。係助詞「ぞ」、自発の助動詞「るる」連体形、係結びの法則。
鞍馬の山に泊まりたいところだが、あいにくの短夜なので、情けなく、かえって辛い逢瀬である。
【くらぶの山に】- 歌語「暗部山」。「鞍馬山」のこと。「比ぶ」「暗し」のイメージを内包する語句。ここは後者の意。『源氏釈』は「墨染の鞍馬の山に入る人はたどるたどるも帰り来ななむ」(後撰集 恋四 八三三 平中興が女)を指摘。「秋の夜の月の光し明かければ暗部の山も越えぬべらなり」(古今集・秋上・元方)。『集成』『完訳』は、歌枕として指摘する。
【あやにくなる】- 語り手の感情を交えた表現。
【短夜にて】- 夏四月頃の短夜。
【あさましう、なかなかなり】- 「あさまし」は、あきれて情けない意。副詞「なかなか」かえって--しない方がましなくらいである、の意。
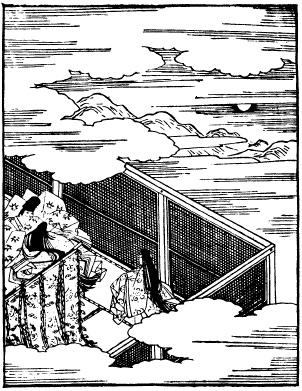
夢の中にそのまま消えてしまいとうございます」
やがてまぎるるわが身ともがな
【さすがにいみじければ】- 藤壺の源氏を拒絶しきれない心情。
この上なく辛い身の上を覚めることのない夢の中のこととしても
憂き身をさめぬ夢になしても
とお言いになった。
命婦の君が、お直衣などは、取り集めて持って来た。
【かき集め持て来たる】- 『集成』は「悲しみに茫然として帰ろうとしない源氏に、脱ぎ捨てておいた直衣などをかき集めて持って来て、帰り支度をうながすのである」と解す。部屋の中での出来事とする。
お手紙なども、例によって、御覧にならない旨ばかりなので、いつものことながらも、全く茫然自失とされて、内裏にも参内せず、二、三日閉じ籠もっていらっしゃるので、また、「どうかしたのだろうか」と、ご心配あそばされているらしいのも、恐ろしいばかりに思われなさる。
【御文なども】- 源氏から藤壺への後朝の手紙。
【例の、御覧じ入れぬよしのみあれば】- 例の」は「御覧じ入れぬ」を修飾。『古典セレクション』は「藤壺は源氏の消息を受け付けない。「例の」とあり、それが習慣化している」と注す。王命婦から源氏へ、藤壺は源氏の手紙を御覧になりません、という返事の意。
【二、三日】- 大島本は漢字表記で「二三日」とある。今字音で「にさむにち」と読んでおく。
【また、「いかなるにか」と】- 前にわらわ病みを心配。
【御心動かせたまふべかめるも】- 主語は帝。尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまふ」終止形。「べかめる」は推量の助動詞「べかる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「める」連体形、主観的推量、係助詞「も」。きっと御心配あそばすにちがいないらしいにつけてもというニュアンス。
【恐ろしうのみおぼえたまふ】- 源氏の心理。『集成』は「罪深いことだ」と解す。『完訳』は「帝の自分へのいたわりにつけても、源氏は犯した罪を恐れる」と解す。源氏は再犯である。
第二段 妊娠三月となる
【思しも立たず】- 主語は藤壺。係助詞「も」強調のニュアンス。
【人知れず思すこと】- 源氏との逢瀬。
三か月におなりになると、とてもよく分かるようになって、女房たちもそれとお気付き申すにつけ、思いもかけないご宿縁のほどが、恨めしい。
他の人たちは、思いもよらないことなので、「この月まで、ご奏上あそばされなかったこと」と、意外なことにお思い申し上げる。
ご自身一人には、はっきりとお分かりになる節もあるのであったのだ。
【三月になりたまへば】- 妊娠して三か月。源氏との密通事件は四月の短夜、今は、夏の最も暑い六月。密通・妊娠という主題が夏の暑苦しさを季節的背景としてかたられていく。この物語の主題と季節との類同的発想の一つ。
【人びと見たてまつりとがむるに】- 注目する、不審がる、の意。女房たちは事の真実を知らないから、非難する、という意ではない。接続助詞「に」順接を表す。
【あさましき御宿世のほど、心憂し】- 「心憂し」とは、語り手と登場人物藤壺の心が一体化したような表現。敬語が付かない。『新大系』「子種をさずかることは前世からの宿縁によるという考え方」と注す。
【この月まで、奏せさせたまはざりけること】- 女房たちの詞。どうして今までめでたいことを隠していたのかという驚き。「奏す」は帝に申し上げる意。尊敬の助動詞「させ」未然形+尊敬の補助動詞「たまは」未然形+打消の助動詞「ざり」連用形+過去の助動詞「ける」連体形。
【我が御心一つには、しるう思しわくこともありけり】- 源氏の子をみごもったという事をさす。王命婦を除く他の女房たちは知らない。「ありけり」というように、語り手は、読者の前に秘話を語る。
【御乳母子の弁、命婦】- 藤壺の乳母子の弁と王命婦。下文に「命婦は」とあり、弁はともかくも、源氏の手引きをした命婦は運命を感じ取っている、という叙述。
【なほ逃れがたかりける御宿世をぞ】- 地の文であるが、「なほ」には王命婦の感想が交えられた表現である。
周囲の人もそうとばかり思っていた。
ますますこの上なく愛しくお思いあそばして、御勅使などがひっきりなしにあるにつけても、空恐ろしく、物思いの休まる時もない。
【おはしましけるやうに】- 主語は藤壺。
【奏しけむかし】- 過去推量の助動詞「けむ」終止形+終助詞「かし」念押し。奏上したのであろうよの意。『集成』は「奏上したらしかった」と解し、『完訳』は「奏上したようである」と解す。
【見る人も】- 御物本、横山本、肖柏本は「みな人も」とある。榊原家本、池田本、三条西家本は大島本と同文。『新大系』「判断する人、占いを見る人のたぐいか」と注す。
【いとどあはれに】- 主語は帝。寵妃の藤壺が懐妊したことを喜ぶ気持ち。
【そら恐ろしう】- 主語は藤壺。
【おどろおどろしうさま異なる夢】- 通常の夢とは違った異様な夢、霊夢。予言的な意味のある夢。
【合はする者】- 夢占いをする者。
【問はせたまへば】- 使役の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまへ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。夢占いをして占わせなさると。
【及びなう思しもかけぬ筋のこと】- 実に尊い子を授かるだろう、という内容か。当時の感覚でいえば、神の子の異常出生か将来に帝となる子ということだろう。『集成』は「源氏が天子の父となるであろうということ」と注す。『古典セレクション』も同じ。『真大系』「分に過ぎたるお思い寄りもせぬ方面の内容を合せたことだ。謎として読者に与えられる」と注す。
この夢が現実となるまで、誰にも話してはならぬ」
【人の御ことを】- 敬語「御」が付いているので帝を想定した発言。
【また人にまねぶな】- 副詞「また」は他にの意。「なねぶ」は見聞きしたことを他人に言う意。
とのたまひて、心 のうちには、「いかなることならむ」と思 しわたるに、この女宮 の御 こと聞 きたまひて、「もしさるやうもや」と、思 し合 はせたまふに、いとどしくいみじき言 の葉尽 くしきこえたまへど、命婦 も思 ふに、いとむくつけう、わづらはしさまさりて、さらにたばかるべきかたなし。
はかなき一行 の御返 りのたまさかなりしも、絶 え果 てにたり。
はかなき
ほんの一行のお返事がまれにはあったのも、すっかり絶えはててしまった。
【もしさるやうもや】- 『集成』は「もしや自分のお子ではないか」と解す。『完訳』は「もしかするとあの夢はこういうわけがあってのことでもあろうか」と解す。
【さらにたばかるべきかたなし】- 副詞「さらに」、形容詞「なし」と呼応して、全然ない、意。
【たまさかなりしも、絶え果てにたり】- 断定の助動詞「なり」連用形、過去の助動詞「し」連体形、係助詞「も」、完了の助動詞「に」連用形、完了の助動詞「たり」終止形。
第三段 初秋七月に藤壺宮中に戻る
珍しい事で感動深くて、以前にも増す御寵愛ぶりはこの上もない。
少しふっくらとおなりになって、ちょっと悩ましげに、面痩せしていらっしゃるのは、それはそれでまた、なるほど比類なく素晴らしい。
【めづらしうあはれにて】- 「めづらし」には四か月ぶりの参内と御懐妊の事の両方の気持ちがある。
【すこしふくらかになりたまひて】- 藤壺の妊娠の具合をさしていう。接続助詞「て」弱い逆接的接続。
【はた、げに似るものなくめでたし】- 副詞「はた」ある一面を認めながらそれとはべつの一面について述べる。副詞「げに」帝の御寵愛が深いのももっともだという、語り手の感情移入表現。
いみじうつつみたまへど、
つとめてお隠しになっているが、我慢できない気持ちが外に現れ出てしまう折々、藤壺宮も、さすがに忘れられない事どもをあれこれとお思い悩み続けていらっしゃるのであった。
【源氏の君も暇なく召しまつはしつつ】- 係助詞「も」同類を表す。藤壺の他に源氏も。接続助詞「つつ」同じ動作の繰り返し。
【いみじうつつみたまへど、忍びがたき気色の漏り出づる折々】- 源氏の藤壺思慕の態度。時々は外に現れることがあったと語る。「桐壺」巻に「琴笛の音に聞こえ通ひ」とあった。
【宮も、さすがなる事どもを多く思し続けけり】- 藤壺の悩む態度。『完訳』は「「さすがに」は、源氏への感情を抑えようにも抑え切れない気持」と指摘。物語には帝について何とも語られていないが、やがて二人の関係を知って行くのではなかろうか。それが自然なふうに布石されているように思われる。
第三章 紫上の物語(2) 若紫の君、源氏の二条院邸に盗み出される物語
第一段 紫の君、六条京極の邸に戻る
京のお住まいを尋ねて、時々お手紙などがある。
同じような返事ばかりであるのももっともであるが、ここ何か月は、以前にも増す物思いによって、他の事を思う間もなくて過ぎて行く。
【出でたまひにけり】- 完了の助動詞「に」連用形、過去の助動詞「けり」終止形。その間に山から京の邸に帰って来ていたのであったというニュアンス。
【この月ごろは、ありしにまさる物思ひに】- 藤壺の宮との事件以後の悩みをさす。
【異事なくて】- 他の事を省みる間もなくての意。
おはする
月の美しい夜に、お忍びの家にやっとのことでお思い立ちになると、時雨めいてさっと降る。
おいでになる先は六条京極辺りで、内裏からなので、少し遠い感じがしていると、荒れた邸で木立がとても年代を経て鬱蒼と見えるのがある。
いつものお供を欠かさない惟光が、
【いともの心細くて嘆きたまふ】- 主語は源氏。
【からうして思ひ立ちたまへるを】- 接続助詞「を」弱い逆接。やっとのことで思い立って出掛けたのに、あいにく時雨が降ってきて、というニュアンス。『集成』『新大系』は清音に読むが、『古典セレクション』は「からうじて」と濁音に読む。
【おはする所は六条京極わたりにて】- 「夕顔」巻に「六条わたりの御忍びありきのころ」とあった。六条の貴婦人のもと。
【すこしほど遠き心地するに】- 接続助詞「に」弱い順接。--していると。
【荒れたる家の】- 格助詞「の」同格を表す。荒れた邸で。
【木暗く見えたるあり】- 大島本「こくらく」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「木暗う」とウ音便形に改める。『新大系』は底本のまま。
【とぶらひて】- 御物本は「〔せうなこん-補入〕とふらひて」、榊原家本は「少納言とふらひて」とある。
【はべりしかば】- 丁寧の補助動詞「はべり」連用形、過去の助動詞「しか」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。ある事態を契機として、たまたま以下の事態が起きたことに気付いたことを表す。--したところ。
【かの尼上】- 惟光は詞文の中では、敬意をもって「尼上」と呼称する。
【となむ申してはべりし】- 主語は少納言の乳母。惟光が要約した間接話法的表現であろう。係助詞「なむ」、丁寧の補助動詞「はべり」連用形、過去の助動詞「し」連体形、係結びの法則。
お見舞いすべきであったのに。
どうして、そうと教えなかったのか。
入って行って、
【とぶらふべかりけるを】- ハ四「とぶらふ」終止形、推量の助動詞「べかり」連用形、当然の意、過去の助動詞「ける」連体形、接続助詞「を」逆接を表す。お見舞いをすべきであったのに。
【などか、さなむとものせざりし】- 連語「などか」(副詞「など」+係助詞「か」疑問)、過去の助動詞「し」連体形に係る。副詞「さ」は惟光の詞を受ける。係助詞「なむ」の下に「はべる」連体形などの語が省略。サ変「ものせ」未然形、は「言ふ」「告ぐ」などの代動詞。打消の助動詞「ざり」連用形、過去の助動詞「し」連体形。
わざわざこのようにお立ち寄りになった旨を言わせたので、入って行って、
【わざとかう立ち寄りたまへること】- 間接話法であろう。わざわざとは、虚偽である。
と言った。大納言家では驚いた。
ここ数日、ひどくご衰弱あそばされましたので、お目にかかることなどはとてもできそうにありません」
【ならせたまひにたれば】- 尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまひ」連用形、二重敬語、会話文中の用例。完了の助動詞「に」連用形、完了の助動詞「たれ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件、原因理由を表す。
などと女房は言って、南向きの縁座敷をきれいにして源氏を迎えたのである。
何の用意もなく、鬱陶しいご座所で恐縮です」
【ゆくりなう】- 『集成』は「ぶしつけに」と解し、『完訳』は「思いがけぬご訪問で」と解す。
【もの深き御座所になむ】- 大島本は仮名表記で「おまし所」とある。係助詞「なむ」の下に「はべる」連体形などの語が省略。『古典セレクション』は「実際には源氏の御座所は建物の外側に近い廂の間だから、「もの深き」と矛盾し、古来不審とされてきた。ここでは、源氏のいる位置そのものはなく、気分的に薄暗くうっとうしい雰囲気をさすものとみておく。木立も鬱蒼とした古家で、しかも病人が近くに臥している」と注す。
なるほどこのような所は、普通とは違っているとお思いになる。
ご病気でいらっしゃること、重いこととも、存じませんでしたもどかしさを」などと申し上げなさる。
と源氏が言った。
【もてなさせたまふに】- 尊敬の助動詞「せ」+尊敬の補助動詞「たまふ」連体形、二重敬語。会話文中での用例。下にも「悩ませたまふ」とある。接続助詞「に」順接、原因理由を表す。
【つつまれはべりてなむ】- 自発の助動詞「れ」連用形。係助詞「なむ」、下に「参らざりし」などの語句が省略。
【おぼつかなさ】- 体言止め、詠嘆の気持ちを表す。「おぼつかなきことよ」に同じ。
「乱 り心地 は、いつともなくのみはべるが、限 りのさまになりはべりて、いとかたじけなく、立 ち寄 らせたまへるに、みづから聞 こえさせぬこと。
のたまはすることの筋 、たまさかにも思 し召 し変 はらぬやうはべらば、かくわりなき齢過 ぎはべりて、かならず数 まへさせたまへ。
いみじう心細 げに見 たまへ置 くなむ、願 ひはべる道 のほだしに思 ひたまへられぬべき」など聞 こえたまへり。
のたまはすることの
いみじう
仰せられますお話の旨は、万一にもお気持ちが変わらないようでしたら、このような頑是ない時期が過ぎましてから、きっとお目をかけて下さいませ。
ひどく頼りない身の上のまま残して逝きますのが、願っております仏道の妨げに存ぜずにはいられません」などと、申し上げなさった。
【みづから聞こえさせぬこと】- 直接申し上げられないこと。この言葉によって女房を介しての詞とわかる。
【のたまはすることの筋】- 「あやしきことなれど、幼き御後見に思すべく、聞こえたまひてむや」(第一章第四段 「若紫の君の素性を聞く」)など、源氏が紫の君を引き取りたいという意向。
【かならず数まへさせたまへ】- 尊敬の助動詞「させ」連用形+尊敬の補助動詞「たまへ」命令形。「数まふ」は人並み(皇族の一人)として扱う意だが、ここは孫女を源氏に託すと許した言葉。
【願ひはべる道のほだしに】- 『古典セレクション』は「本願である極楽往生を遂げるための支障。当時、親子夫婦など人間的な絆が往生の最大の支障と考えられていた」と注す。
【思ひたまへられぬべき】- 謙譲の補助動詞「たまへ」未然形、自発の助動詞「られ」連用形、完了の助動詞「ぬ」終止形、確述の意、推量の助動詞「べき」連体形、係助詞「なむ」の係結び。強調のニュアンス。
【など聞こえたまへり】- 実際には女房が言っているのではあるが、尼君の伝言なので敬語が付く。
もったいないことでございます。せめてこの姫君が、お礼申し上げなされるお
【この君だに】- 副助詞「だに」最小限の希望。
【聞こえたまつべき】- 大島本「きこえたまつへき」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「聞こえたまひつべき」と「ひ」を補訂する。『集成』『新大系』は底本のまま。
【ほどならましかば】- 仮想の助動詞「ましか」未然形+接続助詞「ば」、反実仮想の構文。下に「よからまし」などの語句が省略されている。
とのたまふ。
あはれに聞 きたまひて、
あはれに
しみじみとお聞きになって、
「何 か、浅 う思 ひたまへむことゆゑ、かう好 き好 きしきさまを見 えたてまつらむ。
いかなる契 りにか、見 たてまつりそめしより、あはれに思 ひきこゆるも、あやしきまで、この世 のことにはおぼえはべらぬ」などのたまひて、「かひなき心地 のみしはべるを、かのいはけなうものしたまふ御一声 、いかで」とのたまへば、
いかなる
どのような前世からの因縁によってか、初めてお目にかかった時から、愛しくお思い申しているのも、不思議なまでに、この世の縁だけとは思われません」などとおっしゃって、「いつも甲斐ない思いばかりしていますので、あのかわいらしくいらっしゃるお一声を、ぜひとも」とおっしゃると、
などと源氏は言って、また、
「自分を理解していただけない点で私は苦しんでおります。あの小さい方が何か一言お言いになるのを伺えればと思うのですが」
と望んだ。
【この世のことにはおぼえはべらぬ】- 『古典セレクション』は「現世だけの縁ではないとする。前の「契り」に照応」と注す。『集成』は「この世だけのご縁とは思われません」と訳す。すなわち、現世だけの縁とは思われない、来世までの縁、夫婦二世の縁と思われるの意。夫婦となるべく運命づけられていることをいう。
【かひなき心地のみしはべるを】- 以下「御一声いかで」まで、引続いて源氏の詞。サ変「し」連用形、丁寧の補助動詞「はべる」連体形+接続助詞「を」順接、原因理由を表す。
【いかで】- 副詞「いかで」、下に「聞かばや」などの願望の語句が省略。
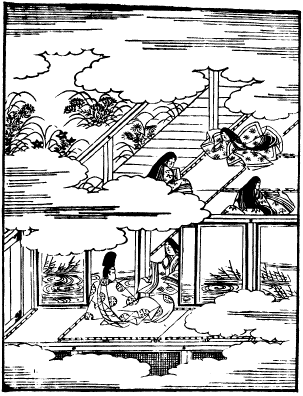
【大殿籠もり入りて】- 「大殿籠もり入り」で一語。「寝入る」の尊敬表現。下に「おはします」などの語が省略。
【あなたより来る音して】- 紫の君が。対の屋からであろうか。
どうしてお会いさらないの」
【この寺にありし】- 「この」は以前に話題になった物事をさす語。今の「あの」「その」に当たる。
【源氏の君こそ】- 紫の君にとっての源氏の呼称。前にも「源氏の君と作り出でて」とあった。接尾語「こそ」呼び掛けを表す。
【おはしたなれ】- 「たなれ」は完了の助動詞「たる」の連体形「る」が撥音便化しさらに無表記形「た」+伝聞推定の助動詞「なれ」已然形、係助詞「こそ」の係結びの法則。おいでになっているそうですね、の意。
【など見たまはぬ】- 副詞「など」疑問の意。尊敬の補助動詞「たまは」未然形、打消の助動詞「ぬ」連体形。どうしてお会いなさらないの。
「静かにあそばせよ」
と言っていた。
【あなかま】- 連語「あなかま」。感動詞「あな」+形容詞「かまし」または「かまびすし」の語幹「かま」の形。制止する際に用いる語句。
【とのたまひしかばぞかし】- 「のたまひ」(連用形)は「言ふ」の尊敬表現。過去の助動詞「しか」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。終助詞「かし」念押し。おっしゃったからですよ。
と、かしこきこと聞 こえたりと思 してのたまふ。
「なるほど、まるで子供っぽいご様子だ。
けれども、よく教育しよう」とお思いになる。
【さりとも、いとよう教へてむ】- 接続詞「さりとも」逆接。下二「教へ」連用形、完了の助動詞「て」未然形、確述、推量の助動詞「む」終止形、意志。よく教育しよう。
いつものように、小さく結んで、
葦の間を行き悩む舟はただならぬ思いをしています
葦間になづむ船ぞえならぬ
少納言がお返事申し上げた。
このよう緩お見舞いいただきましたお礼は、あの世からでもお返事をさせていただきましょう」
かたじけないお見舞いのお礼はこの世界で果たしませんでもまた申し上げる時がございましょう。
【山寺にまかりわたるほどにて】- 北山の僧坊。尼君の死期の近いことをいう。
【この世ならでも聞こえさせむ】- 「聞こえさせ」未然形は「言ふ」最も丁重な謙譲表現。推量の助動詞「む」終止形。尼君の立場になって返事を結んでいる。
とあり。
いとあはれと思 す。
いとあはれと
とてもお気の毒とお思いになる。
「
尼君が「死にきれない」と詠んだ夕暮れを自然とお思い出しになられて、恋しく思っても、また、実際に逢ってみたら見劣りがしないだろうかと、やはり不安である。
【ゆかりも尋ねまほしき】- 紫の君をさす。「ゆかり」は縁。藤壺の姪にあたる。
【心もまさりたまふなるべし】- 大島本「心もまさり給ふなるへし」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「心まさり」と「も」を削除する。『集成』『新大系』は底本のまま。断定の助動詞「なる」連体形+推量の助動詞「べし」終止形は語り手の推測。『完訳』は読点で文を続けて読む。
【消えむ空なき】- 前出の尼君の「生ひ立たむ」歌の一節。
【恋しくも、また、見ば劣りやせむ】- 源氏の心中。マ上一「見」未然形+接続助詞「ば」、順接の仮定条件を表す。係助詞「や」疑問、推量の助動詞「む」連体形、係結びの法則。
【さすがにあやふし】- 語り手の評言。源氏の気持ちを忖度してみせる。
紫草にゆかりのある野辺の若草を」
根に通ひける野辺の若草
このころの源氏の歌である。
第二段 尼君死去し寂寥と孤独の日々
舞人などを、高貴な家柄の子弟や、上達部、殿上人たちなどの、その方面で適当な人々は、皆お選びあそばされたので、親王たちや、大臣をはじめとして、それぞれ伎芸を練習をなさり、暇がない。
【みな選らせたまへれば】- 尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、二重敬語。帝主導による朱雀院行幸の準備である。完了の助動詞「れ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【ふりはへ遣はしたりければ】- 副詞「ふりはへ」わざわざ。完了の助動詞「たり」連用形、過去の助動詞「けれ」已然形+接続助詞「ば」順接の確定条件、--したところ。
【世間の道理】- 「世間」「道理」、僧侶の漢語仏語を多用した物の言い方。
【悲しび思ひたまふる】- 語誌的には「悲しぶ」から「悲しむ」に変化していき、源氏物語には両方見られる。「悲しぶ」はやや古風で男性的な物の言い方。謙譲の補助動詞「たまふる」連体形、係助詞「なむ」の係結び。
などあるを見 たまふに、世 の中 のはかなさもあはれに、「うしろめたげに思 へりし人 もいかならむ。
幼 きほどに、恋 ひやすらむ。
故御息所 に後 れたてまつりし」など、はかばかしからねど、思 ひ出 でて、浅 からずとぶらひたまへり。
少納言 、ゆゑなからず御返 りなど聞 こえたり。
子供心にも、尼君を恋い慕っているだろうか。
わたしも亡き母御息所に先立たれた頃には」などと、はっきりとではないが、思い出して、丁重にお弔いなさった。
少納言の乳母が、心得のある返礼などを申し上げた。
そんな場合にはいつも少納言が行き届いた返事を書いて来た。
【故御息所に後れたてまつりし】- 以下、わが身の上を引き比べて思う。「故御息所」は母桐壺更衣をさす。過去の助動詞「し」連体形、自己の体験。下に「ほど」云々の内容が省略。
いとすごげに
まことにぞっとするくらい荒れた所で、人気も少ないので、どんなに小さい子には怖いことだろうと思われる。
いつもの所にお通し申して、少納言が、ご臨終の有様などを、泣きながらお話申し上げると、他人事ながら、お袖も涙でつい濡れる。
【京の殿に】- 京極の邸に。下に戻ったという内容が省略。
【荒れたる所の、人少ななるに】- 格助詞「の」同格を表す。--で。断定の助動詞「なる」連体形+接続助詞「に」順接、原因理由を表す。--ので。
【いかに幼き人恐ろしからむ】- 源氏の心中。
【例の所に入れたてまつりて】- 寝殿の南廂の間。前回尼君を見舞った折の御座所。
【あいなう】- 他人事ながら。語り手の感情移入の語。源氏の気持ちに沿った表現。
「宮 に渡 したてまつらむとはべるめるを、『故姫君 の、いと情 けなく憂 きものに思 ひきこえたまへりしに、いとむげに児 ならぬ齢 の、まだはかばかしう人 のおもむけをも見知 りたまはず、中空 なる御 ほどにて、あまたものしたまふなる中 の、あなづらはしき人 にてや交 じりたまはむ』など、過 ぎたまひぬるも、世 とともに思 し嘆 きつること、しるきこと多 くはべるに、かくかたじけなきなげの御言 の葉 は、後 の御心 もたどりきこえさせず、いとうれしう思 ひたまへられぬべき折節 にはべりながら、すこしもなぞらひなるさまにもものしたまはず、御年 よりも若 びてならひたまへれば、いとかたはらいたくはべる」と聞 こゆ。
と少納言が言った。
【故姫君の】- 紫の君の母君をさす。以下「交じりたまはむ」まで、生前の尼君の言葉を引用。
【思ひきこえたまへりしに】- 紫の君の母親が兵部卿宮の北の方を。謙譲の補助動詞「きこえ」連用形、母親の北の方に対する敬意。尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、話者祖母の紫の君の母親に対する敬意。完了の助動詞「り」連用形、過去の助動詞「し」連体形、祖母の自己の体験。接続助詞「に」逆接。
【いとむげに児ならぬ齢の】- 格助詞「の」同格を表す。
【まだはかばかしう】- 『集成』は「まだ」と濁音で、『古典セレクション』『新大系』は「また」と清音で読む。副詞「まだ」は「見知りたまはず」に係る。
【あまたものしたまふなる中の】- 北の方に大勢の子供がいる。尊敬の補助動詞「たまふ」終止形+伝聞推定の助動詞「なる」連体形、格助詞「の」同格を表す。
【あなづらはしき人にてや交じりたまはむ】- 断定の助動詞「に」連用形、接続助詞「て」、係助詞「や」疑問、推量の助動詞「む」連体形に係る、係り結び。
【過ぎたまひぬるも】- 尼君の亡くなったことをさしていう。完了の助動詞「ぬる」連体形と係助詞「も」の間に「方」などの語が省略。
【嘆きつること】- 大島本は「なけきつること」とある。その他の青表紙諸本は「なけきつるも」とある。『集成』『古典セレクション』共に「嘆きつるも」と本文を改める。『新大系』は底本のままとする。
【かくかたじけなきなげの御言の葉は】- 「なげの」はかりそめの、口先だけの、の意。「かたじけなき」とはいいながらもまだ源氏の言葉を信じ切っていない。
【いとうれしう思ひたまへられぬべき折節にはべりながら】- 尼君が亡くなった矢先のことなので。謙譲の補助動詞「たまへ」未然形、自発の助動詞「られ」連用形、完了の助動詞「ぬ」終止形、推量の助動詞「べき」連体形、強調の意。
【なぞらひ】- 大島本は「なそらひ」とある。横山本は「なすらへ」、その他の青表紙諸本は「なすらひ」とある。『集成』『古典セレクション』は「なずらひ」と本文を改める。『新大系』は底本のままとする。
「何 か、かう繰 り返 し聞 こえ知 らする心 のほどを、つつみたまふらむ。
その言 ふかひなき御心 のありさまの、あはれにゆかしうおぼえたまふも、契 りことになむ、心 ながら思 ひ知 られける。
なほ、人伝 てならで、聞 こえ知 らせばや。
その
なほ、
その、幼いお考えの様子がかわいく愛しく思われなさるのも、宿縁が特別なものと、わたしの心には自然と思われてくるのです。
やはり、人を介してではなく、直接お伝え申し上げたい。
【御心のありさまの】- 大島本は「御心のありさまの」とある。その他の青表紙諸本は「御ありさまの」とある。『集成』『古典セレクション』は「御ありさまの」と本文を改める。『新大系』は底本のままとする。「ありさまの」の格助詞「の」動作の対象を表す。
【ゆかしうおぼえたまふも】- 尊敬の補助動詞「たまふ」は客体の紫の君に対する敬意。
【心ながら思ひ知られける】- 自分の心には自然と。自発の助動詞「れ」連用形、過去の助動詞「ける」連体形、詠嘆の意、「なむ」の係り結び。
和歌の浦の波のようにこのまま立ち帰ることはしません
こは立ちながら帰る波かは
めざましからむ」とのたまへば、
源氏がこう言うと、
「げにこそ、いとかしこけれ」とて、
相手の気持ちをよく確かめもせずに従うことは頼りないことです
玉藻なびかんほどぞ浮きたる
「どうして逢わずにいられようか」と、口ずさみなさるのを、ぞくぞくして若い女房たちは感じ入っていた。
【なぞ越えざらむ】- 大島本「なそこえさらん」とある。御物本、榊原家本、池田本、三条西家本は「なそこひさらん」、横山本は「なそこひ(ひ=え)さらん」とあり、肖柏本と書陵部本は大島本と同文。河内本では尾州家本、大島本、鳳来寺本は「なそこひさらん」、七毫源氏は「こなそひ(ひ=え)さらむ」、高松宮家本は「なそこえさらん」とある。変体仮名の「江」と「比」のくずし字体の類似から生じた誤写である。定家本では「越ゆ」(ヤ行下二)の連用形は「江」で表記されるので、それから生じたものである。「人知れぬ身は急げども年を経てなど越えがたき逢坂の関」(後撰集 恋三 七三一 伊尹朝臣)の文句を変えて口ずさんだもの。反語表現。『古典セレクション』は「なぞ恋ひざらん」と本文を改めながら、訳文では「「なぞ越えざらむ」とお口ずさみになるのを」と訳している。『集成』『新大系』は底本のままである。
【宮のおはしますなめり】- 「おはします」連体形。「な」は断定の助動詞「なる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「めり」終止形、話者の主観的推量。
と聞 こゆれば、起 き出 でたまひて、
直衣を着ているという方は、どちら。
父宮がいらしたの」
【直衣着たりつらむは】- 完了の助動詞「たり」連用形、完了の助動詞「つ」終止形、推量の助動詞「らむ」連体形、係助詞「は」。「らむ」と「は」の間に「人」などの語が省略。
こちらへ」
「こちらへいらっしゃい」
【恥づかしかりし人】- 紫の君の心中。源氏をさしていう。
と言う。
わたしの膝の上でお寝みなさいませ。
もう少し近くへいらっしゃい」
【など忍びたまふらむ】- 副詞「など」、尊敬の補助動詞「たまふ」終止形、推量の助動詞「らむ」連体形、原因推量。どうして逃げ隠れなさるのでしょう、そうする必要はありませんよ。
とのたまへば、乳母 の、
このようにまだ頑是ないお年頃でして」
【御ほどにてなむ】- 係助詞「なむ」の下に「おはします」などの語が省略。
とて、押 し寄 せたてまつりたれば、何心 もなくゐたまへるに、手 をさし入 れて探 りたまへれば、なよらかなる御衣 に、髪 はつやつやとかかりて、末 のふさやかに探 りつけられたる、いとうつくしう思 ひやらる。
手 をとらへたまへれば、うたて例 ならぬ人 の、かく近 づきたまへるは、恐 ろしうて、
お手を捉えなさると、気味の悪いよその人が、このように近くにいらっしゃるのは、恐ろしくなって、
【何心もなくゐたまへるに】- 主語は紫の君。母屋の御簾または几帳の内側に座った様子である。
【手をさし入れて探りたまへれば】- 主語は源氏。御簾または几帳などの下から手をさし入れて探った様子である。
【なよらかなる御衣に】- 大島本「なよらかなる」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「なよよかなる」と校訂し、『新大系』は「なよらかなる」と校訂する。糊けの落ちて柔らかくなった様子。「ら」と「ゝ」の字体の近さから生じた異文である。「艶 ナヨヨカナリ」(名義抄)。「なよらか」という語も存在する。
【探りつけられたる】- 大島本は「さくりつけられたる」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「探りつけられたるほど」と「ほど」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【やらる】- 大島本は「やらるる」とある。肖柏本が「やらるる」、他の青表紙諸本は「やらる」とある。諸本に従って「やらる」(「思ひやら」+自発の助動詞「る」終止形)と本文を改める。
【うたて例ならぬ人の、かく近づきたまへるは、恐ろしうて】- 他人がこのように接近し手を握るなどということは深窓に育った姫君には経験のないことなので、気味悪く恐ろしくも思う。
とて、強 ひて引 き入 りたまふにつきてすべり入 りて、
お嫌いにならないでね」
【まろぞ】- 「まろ」は親しい者どうしの間で使う一人称。男女共使用。親しみをこめていう。係助詞「ぞ」、「人」の下に「なる」(連体形)などの語が省略。
【な疎みたまひそ】- 副詞「な」--終助詞「そ」禁止の構文を作る。
とのたまふ。
乳母 、
乳母が、
あまりのなさりようでございますわ。
いくらお話申し上げあそばしても、何の甲斐もございませんでしょうに」といって、つらそうに困っているので、
と困ったように言う。
【聞こえさせ知らせたまふとも】- 姫君にあなたさま(源氏)が。「聞こえさせ」は「聞こゆ」より丁重な謙譲語。姫君を敬う。尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまふ」終止形、二重敬語は源氏の動作に対する敬語。接続助詞「とも」逆接を表す。
【さらに何のしるしもはべらじものを】- 副詞「さらに」打消推量の助動詞「じ」と呼応して全然--ないでしょう、の意を表す。接続助詞「ものを」逆接を表す。
やはり、ただ世間にないほどのわたしの愛情をお見届けください」とおっしゃる。
【いかがはあらむ】- 反語表現の構文。何としようか、どうすることもない。
【見果てたまへ】- 源氏が少納言の乳母に対して言った言葉。尊敬の補助動詞「たまへ」が使われている。
何となく恐そうな夜の感じのようですから、宿直人となってお勤めしましょう。
女房たち、近くに参りなさい」
【夜のさまなめるを】- 「なめる」は断定の助動詞「なる」の連体形「る」が撥音便化しさらに無表記形+推量の助動詞「める」連体形、視界内推量、接続助詞「を」順接、原因理由を表して下文に続ける。
【人びと、近うさぶらはれよかし】- 「人々」は女房たち。尊敬の助動詞「れよ」命令形、終助詞「かし」念押し。前に少納言の乳母に対しては尊敬の補助動詞「たまふ」が使われていたが、たの女房たちに対しては、やや軽い尊敬の助動詞「る」が使い分けられている。
乳母は、心配で困ったことだと思うが、事を荒立て申すべき場合でないので、嘆息しながら見守っていた。
【あやしう思ひのほかにも】- 女房の心中。少女と添い寝する源氏を、奇妙に思う。
【荒ましう聞こえ騒ぐべきならねば】- 大島本「きこえさハくへきならねハ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「聞こえ騒ぐべきほどならねば」と「ほど」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【いかならむとわななかれて】- 自発の助動詞「れ」連用形。どうなるのだろうとぶるぶると震えずにはいられないで。
【単衣ばかりを押しくくみて】- 『集成』は「単(肌着)だけで(若君の身体を)包みこんで」と解す。
【かつは】- もう一方ではの意。源氏の意識の両面を語り、人間性の思考と行動の不可解さに深みや奥行きを与えている。
美しい絵などが多く、お人形遊びなどする所に」
【さすがに】- 「かつは」と同様に、紫の君の気持ちの両面を語り、人間性の複雑さに奥行きと幅を与えている。
少納言の乳母は、心配で、すぐ近くに控えている。
風が少し吹き止んだので、夜の深いうちにお帰りになるのも、いかにもわけありそうな朝帰りであるよ。
【ことあり顔なりや】- 『集成』は「草子地」と指摘。『湖月抄』は「風すこし」以下を「草子地也」と指摘。『完訳』は「夜明け直前に帰る後朝の風情から、あたかも逢瀬を遂げたかのようだとする語り手の評言」と指摘する。断定の助動詞「なり」終止形、間投助詞「や」詠嘆は、語り手の口吻を表す。
毎日物思いをして暮らしている所にお迎え申し上げましょう。
こうしてばかりいては、どんなものでしょうか。
姫君はお恐がりにはならなかった」とおっしゃると、
と源氏が言った。
【明け暮れ眺めはべる所に】- 源氏の自邸二条院。
【かくてのみは、いかが】- 副詞「いかが」。下に「過ごされむ」などの語句が省略。反語表現。どうして過ごされましょう、できないでしょう。
【この御四十九日過ぐして】- 尼君の逝去は八月二十日。その四十九日忌は、十一月九日頃となる。
【思うたまふる】- 大島本「思ふ給ふる」とある。「思ふ」の「ふ」は「思ひ」のウ音便化「う」を「ふ」と誤表記した形。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ひたまふる」と校訂する。『新大系』は底本のまま。謙譲の補助動詞「たまふる」連体形、連体中止法。言い切らない余意余情表現。
今夜初めてお会いしたが、わたしの深い愛情は父宮様以上でしょう」
【浅からぬ心ざしはまさりぬべくなむ】- わたしの愛情は実の父以上だ、の意。完了の助動詞「ぬ」終止形、確述、推量の助動詞「べく」連用形、係助詞「なむ」、下に「ある」などの語が省略。
いみじう霧 りわたれる空 もただならぬに、霜 はいと白 うおきて、まことの懸想 もをかしかりぬべきに、さうざうしう思 ひおはす。
いと忍 びて通 ひたまふ所 の道 なりけるを思 し出 でて、門 うちたたかせたまへど、聞 きつくる人 なし。
かひなくて、御供 に声 ある人 して歌 はせたまふ。
いと
かひなくて、
たいそう忍んでお通いになる方への道筋であったのをお思い出しになって、門を叩かせなさるが、聞きつける人がいない。
しかたなくて、お供の中で声の良い者に歌わせなさる。
【まことの懸想もをかしかりぬべきに】- 係助詞「も」仮定の意を表す。語り手の感情移入された評言である。少女の紫の君の家からの朝帰り、これが成人女性の家からの朝帰りであったら、というニュアンス。接続助詞「に」逆接で下文に続ける。
【いと忍びて通ひたまふ所の道】- 『集成』は「誰か不明である。前に出た「六条京極わたり」の女性らしくもあるが、位置関係からいうと逆の位置のように読める」と解し、『完訳』でも「誰であるか不明」と注す。『新大系』は「先に「忍びたる所」とあったのとは別の女」と注す。

素通りし難い貴女の家の前ですね」
行き過ぎがたき妹が門かな
生い茂った草が門を閉ざしたことぐらい何でもないでしょうに」
草の戸ざしに障りしもせじ
他に誰も出て来ないので、帰るのも風情がないが、空が明るくなって行くのも体裁が悪いので邸へお帰りになった。
日が高くなってからお起きになって、手紙を書いておやりになる時、書くはずの言葉も普通と違うので、筆を書いては置き書いては置きと、気の向くままにお書きになっている。
美しい絵などをお届けなさる。
【文やりたまふに】- 後朝(きぬぎぬ)の文。接続助詞「に」逆接で下文に続ける。
【筆うち置きつつすさびゐたまへり】- 接続助詞「つつ」動作の反復を表す。『古典セレクション』は「この「すさび」は、心がすすんで熱中する意」と注す。
数年来以上にすっかり荒れ行き、広く古めかしくなった邸が、ますます人数が少なくなって月日を経ているので、ずっと御覧になって、
【今日しも】- 源氏が朝帰りして後朝の文を送った、その日。
【年ごろよりも】- 以下、兵部卿宮の目を通して語られる。
【久しければ】- 大島本は「ひさしけれは」とある。その他の青表紙諸本は「さひしけれは」とある。『集成』『古典セレクション』は「さびしければ」と本文を改める。
【見わたしたまひて】- 主語は兵部卿宮。
「かかる所 には、いかでか、しばしも幼 き人 の過 ぐしたまはむ。
なほ、かしこに渡 したてまつりてむ。
何 の所狭 きほどにもあらず。
乳母 は、曹司 などしてさぶらひなむ。
君 は、若 き人 びとあれば、もろともに遊 びて、いとようものしたまひなむ」などのたまふ。
なほ、かしこに
やはり、あちらにお引き取り申し上げよう。
けっして窮屈な所ではない。
乳母には、部屋をもらって仕えればよい。
姫君は、若い子たちがいるので、一緒に遊んで、とても仲良くやって行けよう」などとおっしゃる。
などとお言いになった。
【いかでか、しばしも幼き人の過ぐしたまはむ】- 連語「いかでか」は「過ぐしたまはむ」に係る、反語表現の構文。どうしてお過ごしになれよう、できまい。
【かしこに渡したてまつりてむ】- 兵部卿宮邸。謙譲の補助動詞「たてまつり」(連用形)は紫の君を敬った表現。完了の助動詞「て」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形、意志。きっと--しよう。
【曹司などしてさぶらひなむ】- 部屋を決めて。完了の助動詞「な」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形、適当・勧誘。お仕えするのがよかろう。
【若き人びとあれば】- 大島本「わかき人/\あれハ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「若き人々などあれば」と「など」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【いとようものしたまひなむ】- 完了の助動詞「な」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形、推量。
お召し物はすっかりくたびれているが」と、お気の毒にお思いになった。
「いい匂いだね。げれど着物は古くなっているね」
心苦しく思召す様子だった。
【かの御移り香の】- 源氏の移り香。
【染みかへらせたまへれば】- 大島本「しみかへらせ給へれハ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「染みかへりたまへれば」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。補助動詞「--かへる」は程度のはなはだしいさまを表す。尊敬の助動詞「せ」連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、完了の助動詞「れ」已然形、存続+接続助詞「ば」順接、原因理由を表し、下文に続ける。
【をかしの御匂ひや。御衣はいと萎えて】- 宮の心中とも詞ともとれる文。『集成』『古典セレクション』は詞と解す。接続助詞「て」逆接。
「年 ごろも、あつしくさだ過 ぎたまへる人 に添 ひたまへるよ、かしこにわたりて見 ならしたまへなど、ものせしを、あやしう疎 みたまひて、人 も心置 くめりしを、かかる折 にしもものしたまはむも、心苦 しう」などのたまへば、
と宮がお言いになる。
【あつしくさだ過ぎたまへる人に】- 尼君をさしていう。
【添ひたまへるよ】- 間投助詞「よ」詠嘆。他の青表紙諸本この語が無い。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「添ひたまへる」と「よ」を削除する。『新大系』は底本のまま。
【あやしう疎みたまひて】- 主語は亡くなった尼君。
【人も心置くめりしを】- 北の方をさしていう。推量の助動詞「めり」連用形、視界内推量の意。過去の助動詞「し」連体形、自己の体験のニュアンス。接続助詞「を」逆接で下文に続ける。
心細くても、今暫くはこうしておいであそばしましょう。
もう少し物の道理がお分かりになりましたら、お移りあそばされることが良うございましょう」と申し上げる。
少納言はこう答えていた。
【おはしましなむ】- 「おはします」は最も高い尊敬表現。姫君に対して使っている。完了の助動詞「な」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形、強調のニュアンス。
【こそ、よくははべるべけれ】- 係り助詞「こそ」、推量の助動詞「べけれ」已然形、係結びの法則。
【いとあてにうつくしく、なかなか見えたまふ】- 副詞「なかなか」は語順倒置、「なかなかいとあてにうつくしく見えたまふ」。
今はもうこの世にいない方のことは、
しかたがありません。わたし
【おのれあれば】- 下に「思しわづらふな」「心頼もしからむ」などの語句が省略。
【いと心細しと思いて泣いたまへば】- 主語は紫の君。挿入句。
そんなにご心配なさるな。今日明日のうちに、お移し申そう」などと、繰り返しなだめす
などと、いろいろになだめて宮はお帰りになった。
【思ひな入りたまひそ】- 「思ひ入る」の間に副詞「な」が介入、終助詞「そ」禁止を表す。
なごりも慰 めがたう泣 きゐたまへり。
行 く先 の身 のあらむことなどまでも思 し知 らず、ただ年 ごろ立 ち離 るる折 なうまつはしならひて、今 は亡 き人 となりたまひにける、と思 すがいみじきに、幼 き御心地 なれど、胸 つとふたがりて、例 のやうにも遊 びたまはず、昼 はさても紛 らはしたまふを、夕暮 となれば、いみじく屈 したまへば、かくてはいかでか過 ごしたまはむと、慰 めわびて、乳母 も泣 きあへり。
将来の身の上のことなどはお分りにならず、ただ長年離れることなく一緒にいて、今はお亡くなりになってしまったと、お思いになるのが悲しくて、子供心であるが、胸がいっぱいにふさがって、いつものようにもお遊びはなさらず、昼間はどうにかお紛らわしになるが、夕暮時になると、ひどくおふさぎこみなさるので、これではどのようにお過ごしになられようかと、慰めあぐねて、乳母たちも一緒に泣いていた。
【立ち離るる折なうまつはしならひて】- 「まつはしならひて」の主語について、『今泉忠義訳』では紫の君が「片時も離れず付き纏ふことにしていたのに」と訳し、『古典セレクション』では「尼君がいつもずっとおそばにおいてくださったのに」と訳す。
【かくてはいかでか過ごしたまはむ】- 大島本「すこし給はむ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「過ぐしたまはむ」と校訂する。『新大系』は底本のまま。乳母の心中。主語は紫の上。副詞「いかで」+係助詞「か」疑問、推量の助動詞「む」連体形、係結び、反語表現の構文。
お気の毒に拝見致しましたのにつけても、気がかりで」と伝えて、宿直人を差し向けなさった。
源氏からの挨拶はこれで惟光が代わりの宿直をするわけである。
【内裏より召あればなむ】- 係助詞「なむ」の下に「え参らぬ」などの語句が省略。
【心苦しう見たてまつりしも】- 過去の助動詞「し」連体形、係助詞「も」強調の意。
ご冗談にも結婚の最初からして、このようなお事とは」
【もののはじめ】- 「もの」は結婚をさす。成婚の当初からの意。
「あり経 て後 や、さるべき御宿世 、逃 れきこえたまはぬやうもあらむ。
ただ今 は、かけてもいと似 げなき御 ことと見 たてまつるを、あやしう思 しのたまはするも、いかなる御心 にか、思 ひ寄 るかたなう乱 れはべる。
今日 も、宮渡 らせたまひて、『うしろやすく仕 うまつれ。
心幼 くもてなしきこゆな』とのたまはせつるも、いとわづらはしう、ただなるよりは、かかる御好 き事 も思 ひ出 でられはべりつる」
ただ
ただ今は、まったく不釣り合いなお話と拝察致しておりますが、不思議にご熱心に思ってくださり、またおっしゃってくださいますのを、どのようなお気持ちからかと、判断つかないで悩んでおります。
今日も、宮さまがお越しあそばして、『安心の行くように仕えなさい。
うっかりしたことは致すな』と仰せられたのも、とても厄介で、なんでもなかった時より、このような好色めいたことも改めて気になるのでございました」
【さるべき御宿世】- 前世からの御縁、すなわち結婚。
【逃れきこえたまはぬやうもあらむ】- 謙譲の補助動詞「きこえ」連用形、紫の君を謙らせて源氏を敬う、尊敬の補助動詞「たまは」未然形、紫の君に対する敬意。打消の助動詞「ぬ」連体形。推量の助動詞「む」連体形、係助詞「や」の係り結び。
【宮渡らせたまひて】- 尊敬の助動詞「せ」連用形+尊敬の補助動詞「たまひ」連用形、二重敬語、会話文中の用例。
【うしろやすく】- 以下「きこゆな」まで、兵部卿宮の詞を引用。横山本と肖柏本は「うしろやすう」とある。
【心幼くもてなしきこゆな】- 幼稚な考え、あさはkな考え、の意。
【思ひ出でられはべりつる】- 自発の助動詞「られ」連用形、完了の助動詞「つる」連体形、確述。連体中止法。思わずにはいられないという気持ちと余情または含みを残した言い方。
惟光大夫も、「どのような事なのだろう」と、ふに落ちなく思う。
【あいなければ】- 乳母は、源氏が来ないのを気にしているが、それを惟光に察せられたくないでいる。『完訳』は「局外者の惟光からあれこれ忖度されるのは不本意、の気持」と注す。
【大夫も】- 惟光をさす。源氏の使者としての一個人というより、「大夫」という公人かつ身分ある(五位)一人格者としてのニュアンスを強調した表現。
【あはれに思しやらるれど】- 以下、主語は源氏。自発の助動詞「るれ」已然形+接続助詞「ど」逆接で下文に続ける。
【すずろなる心地】- 『集成』は「どうかと思われて」と解し、『完訳』は「行き過ぎという感じ」と解す。
【軽々しう】- 以下「漏り聞かむ」まで、源氏の心中。
【人もや漏り聞かむ】- 係助詞「も」仮定のニュアンス、係助詞「や」疑問、推量の助動詞「む」連体形、係結び。
【ただ迎へてむ】- 完了の助動詞「て」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形。いっそ迎えてしまおう、という強いニュアンスを表す。
暮れると、いつものように惟光大夫をお差し向けなさる。
「差し障りがあって参れませんのを、不熱心なとでも」などと、伝言がある。
やむをえぬ用事があって出かけられないのを、私の不誠実さからだとお思いにならぬかと不安です。
などという手紙が書かれてくる。
【障はる事どもの】- 以下「おろかにや」まで、源氏の伝言。『集成』と『新大系』は「源氏の手紙の文面」と解す。「おろかにや」の下に「思さむ」などの語句が省略。
長年住みなれた蓬生の宿を離れますのも、何と言っても心細く、お仕えする女房たちも思い乱れております」
【心あわたたしくてなむ】- 係助詞「なむ」の下には「はべる」(連体形)などの語が省略。「アワタタシイ」(日葡辞書)。
【蓬生を離れなむも】- 歌語「蓬生」は自邸を謙って言った表現。「荒れたる宿をばよもぎふといふ」(能因歌枕)。「かれ」は「離れ」と「枯れ」との掛詞、「蓬生」と「枯れ」は縁語。完了の助動詞「な」未然形、確述+推量の助動詞「む」連体形、強調のニュアンス。
【さすがに心細く】- 大島本「心ほそく」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心細う」と校訂する。『新大系』は底本のまま。
【思ひ乱れて】- 接続助詞「て」の下には「はべる」(連体中止法)などの語が省略。
【もの縫ひいとなむけはひなどしるければ】- 引越しの際の常套場面。国宝『源氏物語絵巻』「早蕨」参照。
第三段 源氏、紫の君を盗み取る
君は何となくおもしろくなくお思いになって、和琴を即興に掻き鳴らして、「常陸では田を作っているが」という歌を、声はとても優艶に、口ずさんでおいでになる。
【ものむつかしくおぼえたまひて】- 主語は源氏。
【あづまを】- 東琴の略、すなわち和琴をさす。
【すががきて】- 主語は源氏。軽い即興的な奏法。
【常陸には田をこそ作れ】- 源氏の口ずさみ。「風俗歌」の「常陸」の一節。「常陸にも 田をこそ作れ あだ心 や かぬとや君が 山を越え 雨夜来ませる」。本来、女性側から歌う内容であるが、源氏がこう歌ったのは皮肉なあてこすり。『古典セレクション』は「相手になってくれない葵の上への不満をかこつ」と注す。
「これこれしかじかです」と申し上げるので、残念にお思いになって、「あの宮邸に移ってしまったら、わざわざ迎え取ることも好色めいたことであろう。
子供を盗み出したと、きっと非難されるだろう。
その前に、暫くの間、女房の口を封じさせて、連れて来てしまおう」とお考えになって、
【かの宮に渡りなば】- 以下「渡してむ」まで、源氏の心中。完了の助動詞「な」未然形+接続助詞「ば」順接の仮定条件を表す。
【もどきおひなむ】- 完了の助動詞「な」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形、きっと--となろう、自然的事態の強調ニュアンス。
【渡してむ】- 完了の助動詞「て」未然形、確述+推量の助動詞「む」終止形、きっと--してしまおう、人為的事態の強調のニュアンス。
車の準備はそのままに。
随身を一、二名を申し付けておけ」とおっしゃる。
承知して下がった。
という命令を受けて惟光は立った。
【仰せおきたれ】- 『古典セレクション』は「「おきたれ」は「おきてあれ」。「おき(掟)つ」は、計画をたてる意」と注す。
噂が広がって好色めいたことになりそうな事よ。
せめて相手の年齢だけでも物の分別ができ、女が情を通じてのことだと想像されるようなのは、世間一般にもある事だ。
もし父宮がお探し出された場合も、体裁が悪く、格好もつかないことになるだろうから」と、お悩みになるが、この機会を逃したら大変後悔することになるにちがいないので、まだ夜の深いうちにお出になる。
【人のほどだにものを思ひ知り】- 副助詞「だに」最小限を表す。せめて--だけでも。
【女の心交はしけることと推し測られぬべくは】- 女が合意の上で引き取られることになった、と推測されるようなのは。
【尋ね出でたまへらむも】- 尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、完了の助動詞「ら」未然形、推量の助動詞「む」連体形、仮定の意、係助詞「も」。
【すずろなるべきを】- 『集成』は「言いわけも立たないことだと」、『古典セレクション』は「格好のつかないことになるだろう」と訳す。接続助詞「を」順接、原因理由を表す。きっと--になるだろうから。下に「いかにせむ」などの語句が省略。
【いと口惜しかべければ】- 「かべけれ」は「かるべけれ」の「る」が撥音便化しさらに無表記形。推量の助動詞「べけれ」已然形、当然の意、接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
「かしこに、いとせちに見 るべきことのはべるを思 ひたまへ出 でて、立 ちかへり参 り来 なむ」とて、出 でたまへば、さぶらふ人 びとも知 らざりけり。
わが御方 にて、御直衣 などはたてまつる。
惟光 ばかりを馬 に乗 せておはしぬ。
わが
ご自分のお部屋の方で、お直衣などはお召しになる。
惟光だけを馬に乗せてお出になった。
と源氏は不機嫌な妻に告げて、寝室をそっと出たので、女房たちも知らなかった。自身の部屋になっているほうで直衣などは着た。馬に乗せた惟光だけを付き添いにして源氏は大納言家へ来た。
【思ひたまへ出でて】- 大島本「おもひ給へいてゝ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「思ひたまへ出でてなむ」と「なむ」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【立ちかへり参り来なむ】- カ変「来(き)」連用形、完了の助動詞「な」未然形、確述の意、推量の助動詞「む」終止形、意志。きっと帰ってまいりましょう。
【わが御方にて】- 源氏は左大臣邸でも私的な部屋がある。
【御直衣などはたてまつる】- 「たてまつる」は「着る」の尊敬語。
【惟光ばかりを馬に乗せておはしぬ】- 源氏は牛車で。副助詞「ばかり」限定。
【妻戸を鳴らして、しはぶけば】- 来訪を告げる合図。
「ここに、おはします」と言 へば、
と言うと、
どうして、こんな暗いうちにお出あそばしたのでしょうか」と、どこかからの帰りがけと思って言う。
と少納言が言う。源氏が人の所へ通って行った帰途だと解釈しているのである。
【御殿籠もりてなむ】- 接続助詞「て」、係助詞「なむ」、下に「おはします」(連体形)などの語が省略。
【などか、いと夜深うは出でさせたまへる】- 連語「などか」(副詞「など」+係助詞『か」)は、「出でさせたまへる」(尊敬の助動詞「させ」連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」已然形、二重敬語、完了の助動詞「る」連体形)に係る、係結びの法則。
【もののたよりと思ひて】- どこかの女の家からの帰りがけと思って、の意。
と源氏が言った。
【聞こえ置かむとてなむ】- 係助詞「なむ」の下に「参りぬ」などの語句が省略。
どんなにしっかりしたお返事ができましょう」
【いかにはかばかしき御答へ聞こえさせたまはむ】- 主語は姫君、紫の君が。「きこえさせ」(「きこゆ」よりさらに丁重な謙譲語)、尊敬の補助動詞「たまは」未然形、推量の助動詞「む」連体形。反語表現の構文だが、表の意だけで言ったもの。よって、冗談なので「とて、うち笑ひてゐたり」とある。『集成』は「どんなにか、はきはきしたお返事を申し上げなさることでしょう。源氏の意図を察せず、のんきに冗談を言っている」、『古典セレクション』も「紫の上がさぞはきはきと応答するだろうと、わざと戯れて言った」と注す。
源氏の君が、お入りになると、とても困って、
【君、入りたまへば】- 源氏が紫の君の寝所に。
【古人どものはべるに】- 接続助詞「に」順接、原因理由を表す。下に「おそれおほし」などの語句が省略。
【聞こえさす】- 「言ふ」の最も丁重な謙譲語。
どれ、お目をお覚まし申しましょう。
このような素晴らしい朝霧を知らないで、寝ていてよいものですか」
【寝るものか】- 連語「ものか」意外なことに対して驚きを表す。
【宮の御迎へにおはしたる】- 紫の君の心。
父宮さまのお使いとして参ったのですよ」
わたしも同じ人ですよ」
「あ、どうなさいます」
と同時に言った。
【こは、いかに】- 大輔と少納言の乳母の詞。
誰か一人付いて参られよ」
【心やすき所にと聞こえしを】- 前出「いざ給へよ。をかしき絵など多く、雛遊びなどする所に」をさす。
【心憂く、渡りたまへるなれば】- 大島本「心うくわたり給へるなれハ」とある。『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心憂く渡りたまふべかなれば」と校訂する。『新大系』は底本のままとする。紫の君が父兵部卿宮邸に。伝聞推定の助動詞「なれ」已然形、接続助詞「ば」順接の確定条件を表す。
【聞こえがたかべければ】- 接続助詞「ば」順接の確定条件。下に「渡したてまつらむ」などの語句が省略。
「今日 は、いと便 なくなむはべるべき。
宮 の渡 らせたまはむには、いかさまにか聞 こえやらむ。
おのづから、ほど経 て、さるべきにおはしまさば、ともかうもはべりなむを、いと思 ひやりなきほどのことにはべれば、さぶらふ人 びと苦 しうはべるべし」と聞 こゆれば、
おのづから、ほど
宮さまがお越しあそばした時には、どのようにお答え申し上げましょう。
自然と、年月をへて、そうなられるご縁でいらっしゃれば、ともかくなられましょうが、何とも考える暇もない急な事でございますので、お仕えする者どももきっと困りましょう」と申し上げると、
と言うと、
【いと便なくなむはべるべき】- 係助詞「なむ」、推量の助動詞「べき」連体形、係結びの法則。
【宮の渡らせたまはむには】- 尊敬の助動詞「せ」連用形、尊敬の補助動詞「たまふ」未然形、二重敬語。推量の助動詞「む」連体形、仮定の意。
【さるべきにおはしまさば】- 大島本は「さ(さ+る)へきにおハしまさハ」とある。『古典セレクション』は諸本に従って「さべきに」と校訂する。『集成』『新大系』は「さるべきに」とする。
【いと思ひやりなきほどの】- 「思ひやり」は、思いをはせること、考えおよぼすこと。あれこれ考える間もない。
こんなふうに言って源氏は車を前へ寄せさせた。
少納言の乳母は、お止め申し上げるすべもないので、昨夜縫ったご衣装類をひっさげて、自分も適当な着物に着替えて、車に乗った。
若君を、とても軽々と抱いてお下ろしになる。
【かき抱きて下ろしたまふ】- 源氏が紫の君を。
少納言は下車するのを躊躇した。
【いかにしはべるべきことにか」と、やすらへば】- 紫の君と共に二条院まで来たが、それは見送りのためで到着後は帰るべきか、とどまるべきか。主人の紫の君だけでなく源氏の意向も聞かなければならない。
あなたの考え次第でしょう。ご本人はお移し申し上げてしまったのだから、帰ろうと思
【御自ら渡したてまつりつれば】- 「御自ら」は紫の君をさす。謙譲の補助動詞「たてまつり」連用形、完了の助動詞「つれ」已然形、接続助詞「ば」順接の確定条件、原因理由を表す。
【帰りなむとあらば】- 完了の助動詞「な」未然形、確述、推量の助動詞「む」終止形、意志
とのたまふに、笑 ひて下 りぬ。
にはかに、あさましう、胸 も静 かならず。
「宮 の思 しのたまはむこと、いかになり果 てたまふべき御 ありさまにか、とてもかくても、頼 もしき人 びとに後 れたまへるがいみじさ」と思 ふに、涙 の止 まらぬを、さすがにゆゆしければ、念 じゐたり。
にはかに、あさましう、
「
急な事で、驚きあきれて、心臓がどきどきする。
「宮さまがお叱りになられることや、どうおなりになる姫君のお身の上だろうか、とにもかくにも、身内の方々に先立たれたことが本当にお気の毒」と思うと、涙が止まらないのを、何と言っても不吉なので、じっと堪えていた。
【宮の】- 以下「いみじさ」まで、少納言の乳母の心中。
【いかになり果てたまふべき】- 紫の上が。
【さすがにゆゆしければ】- 新しい生活の出発にさいして、涙は縁起でもないとする考え。
こなたは住 みたまはぬ対 なれば、御帳 などもなかりけり。
惟光召 して、御帳 、御屏風 など、あたりあたり仕立 てさせたまふ。
御几帳 の帷子引 き下 ろし、御座 などただひき繕 ふばかりにてあれば、東 の対 に、御宿直物召 しに遣 はして、大殿籠 もりぬ。
惟光を呼んで、御帳や、御屏風など、ここかしこに整えさせなさる。
御几帳の帷子を引き下ろし、ご座所など、ちょっと整えるだけで使えるので、東の対にお寝具類などを取り寄せに人をやって、お寝みになった。
【御宿直物召しに遣はして、大殿籠もりぬ】- 源氏の寝具類か。源氏は紫の君とお寝みになった。
【ふるはれたまへど】- 自発の助動詞「れ」連用形、尊敬の補助動詞「たまへ」已然形。
少納言の乳母は横になる気もせず、何も考えられず起きていた。
たまのお客などが参った折に使う部屋だったので、男たちが御簾の外に控えているのであった。
【見わたせば】- 少納言の乳母の視点から語られる。
【かかやく心地するに】- 「かかやく」の第二音節は近世前期まで清音。
【はしたなく】- 『集成』は「(今までわびしい暮しに馴れてきたみすぼらしい自分など)場違いだときまり悪い思いでいたが」と解し、『完訳』は「邸にふさわしい女房も大勢いるかと恥ずかしい」と解す。
並大抵の人ではあるまい」と、ひそひそ噂する。
御手水や、お粥などを、こちらの対に持って上がる。
日が高くなってお起きになって、
「だれだろう、よほどお好きな方なんだろう」
などとささやいていた。源氏の洗面の水も、朝の食事もこちらへ運ばれた。遅くなってから起きて、源氏は少納言に、
【誰れならむ。おぼろけにはあらじ】- 西の対の家来たちのひそひそ声。
【日高う寝起きたまひて】- 時刻は日が高くなるころ、主語は源氏。
【悪しかめるを】- 「悪しかるめる」の「る」が撥音便化しさらに無表記形。推量の助動詞「める」連体形、視界内推量。
【迎へさせたまはめ】- 使役の助動詞「させ」連用形、尊敬の補助動詞「たまは」未然形、推量の助動詞「め」適当の意。あなたが女房たちを迎えさせなさるがよかろう。
「小さい子たちだけ、特別に参れ」と言ったので、とてもかわいらしい格好して、四人が参った。
お嫌がりなさいますな。いい加減な男は、このよう
に親切にしましょう
【かうはありなむや】- 完了の助動詞「な」未然形、確述、推量の助動詞「む」終止形、係助詞「や」疑問の意。反語表現の構文。こんなに親切になさいましょうか、しませんよ。『集成』は「こんなに親切にするものですか」と解す。
など、今 より教 へきこえたまふ。
【取りに遣はして】- 東の対の源氏の居室に。
【鈍色のこまやかなるが】- 外祖母の服喪は三か月。喪服の色。格助詞「が」同格を表す。「鈍色のこまやかなる」と「うち萎えたるども」が同じものをさし、共に「着て」に係る。「やむごとなき際にはあらぬが、すぐれてときめきたまふありけり」(桐壺)と同例。
【我もうち笑まれて見たまふ】- 「我」は源氏をさす。自発の助動詞「れ」連用形。
御屏風類などの、とても素晴らしい絵を見ては、機嫌を良くしていらっしゃるのも、あどけないことよ。
【四位、五位こきまぜに】- 四位は黒色の袍、五位は赤色の袍を着る。
【隙なう出で入りつつ】- 接続助詞「つつ」動作の反復を表す。下文の「いとをかしき絵を見つつ」も同じ用法。
【げに、をかしき所かな】- 紫の君の心中。「げに」は源氏が言っていたとおりの意。
【はかなしや】- 語り手の紫の上に対する評言。『首書源氏物語』所引「或抄」に「地よりいへり」と注す。『集成』は「何といっても子供のことではある。草子地」、『完訳』は「悲しみや不安を早くも紛らわす無心な姿への、語り手の評言」と注す。
やがて
いみじうをかしげに
「
すこし
そのまま手本にとのお考えか、手習いや、お絵描きなど、いろいろと書いては描いては、御覧に入れなさる。
とても素晴らしくお書き集めになった。
「武蔵野と言うと文句を言いたくなってしまう」と、紫の紙にお書きになった墨の具合が、とても格別なのを取って御覧になっていらっしゃった。
少し小さくて、
【さまざまに書きつつ】- 接続助詞「つつ」動作の繰り返し。
【武蔵野と言へばかこたれぬ】- 『源氏釈』は「知らねども武蔵野といへばかこたれぬよしやさこそは紫のゆゑ」(古今六帖第五 紫)を指摘。その第四句の文句。『集成』はさらに「紫の一本ゆゑに武蔵野の草は見ながらあはれとぞ思ふ」(古今集 雑上 八六七 読人しらず)をも引歌として指摘する。自発の助動詞「れ」連用形、完了の助動詞「ぬ」終止形、確述の意。藤壺のゆかりの人だと思うと懐かしく思われてしまうの意。しかし、紫の君はこのような事情とは知らない。
【取りて見ゐたまへり】- 主語は紫の君。
武蔵野の露に難儀する紫のゆかりのあなたを」
露分けわぶる草のゆかりを
とあり。
「いで、君 も書 いたまへ」とあれば、
と源氏が言うと、
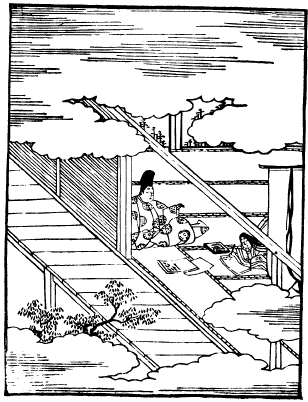
とて、見上 げたまへるが、何心 なくうつくしげなれば、うちほほ笑 みて、
お教え申し上げましょうね」
「書き損ってしまった」と、恥ずかしがってお隠しになるのを、無理に御覧になると、
「書きそこねたわ」
と言って、恥ずかしがって隠すのをしいて読んでみた。
【書きそこなひつ】- 紫の上の詞。
わたしはどのような方のゆかりなのでしょう」
いかなる草のゆかりなるらん
亡くなった尼君の筆跡に似ているのであった。
「当世風の手本を習ったならば、とても良くお書きになるだろう」と御覧になる。
【いとよう書いたまひてむ】- 「よう」は「よく」のウ音便形。完了の助動詞「て」連用形、確述、推量の助動詞「む」終止形、推量の意。きっと上手にお書きになるだろう。
かのとまりにし人 びと、宮渡 りたまひて、尋 ねきこえたまひけるに、聞 こえやる方 なくてぞ、わびあへりける。
「しばし、人 に知 らせじ」と君 ものたまひ、少納言 も思 ふことなれば、せちに口固 めやりたり。
ただ、「行方 も知 らず、少納言 が率 て隠 しきこえたる」とのみ聞 こえさするに、宮 も言 ふかひなう思 して、「故尼君 も、かしこに渡 りたまはむことを、いとものしと思 したりしことなれば、乳母 の、いとさし過 ぐしたる心 ばせのあまり、おいらかに渡 さむを、便 なし、などは言 はで、心 にまかせ、率 てはふらかしつるなめり」と、泣 く泣 く帰 りたまひぬ。
「もし、聞 き出 でたてまつらば、告 げよ」とのたまふも、わづらはしく。
僧都 の御 もとにも、尋 ねきこえたまへど、あとはかなくて、あたらしかりし御容貌 など、恋 しく悲 しと思 す。
「しばし、
ただ、「
「もし、
「暫くの間、他人に聞かせてはならぬ」と源氏の君もおっしゃるし、少納言の乳母も考えていることなので、固く口止めさせていた。
ただ、「行く方も知れず、少納言の乳母がお連れしてお隠し申したことで」とばかりお答え申し上げるので、宮もしょうがないとお思いになって、「亡くなった尼君も、あちらに姫君がお移りになることを、とても嫌だとお思いであったことなので、乳母が、ひどく出過ぎた考えから、すんなりとお移りになることを、不都合だ、などと言わないで、自分の一存で、連れ出してどこかへやってしまったのだろう」と、泣く泣くお帰りになった。
「もし、消息をお聞きつけ申したら、知らせなさい」とおっしゃる言葉も、厄介で。
僧都のお所にも、お尋ね申し上げなさるが、はっきり分からず、惜しいほどであったご器量など、恋しく悲しいとお思いになる。
「もし居所がわかったら知らせてよこすように」
宮のこのお言葉を女房たちは苦しい気持ちで聞いていたのである。宮は僧都の所へも捜しにおやりになったが、姫君の行くえについては何も得る所がなかった。美しかった小女王の顔をお思い出しになって宮は悲しんでおいでになった。
【しばし、人に知らせじ】- 前に「しばし人にも口固めて」(第三章三段)とあったのを踏まえる。
【行方も知らず、少納言が率て隠しきこえたる】- 女房たちの宮に対する返事の要旨。謙譲の補助動詞「聞こえ」連用形、完了の助動詞「たる」連体形、連体中止法。言いさして余情を残した。
【故尼君も】- 以下「率てはふらかしつるなめり」まで、兵部卿宮の心中。
【おいらかに渡さむを、便なし、などは言はで】- 「おいらかに」は「渡さむ」に係る。また「言はで」に係るとする説もある。
【心にまかせ】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「心にまかせて」と「て」を補訂する。『新大系』は底本のままとする。
【もし、聞き出でたてまつらば、告げよ】- 宮の女房たちへの詞。
【わづらはしく】- 連用中止法。余情を残して言いさした文型。「わづわし」は女房と語り手の感情が一体化した表現。
お遊び相手の童女や、幼子たちも、とても珍しく当世風なご様子なので、何の屈託もなくて遊び合っていた。
【思ふことなくて遊びあへり】- 敬語がないので、主語は「童女、児ども」。
最初からご一緒ではなく過ごして来られたので、今ではすっかりこの後の親を、たいそう馴れお親しみ申し上げていらっしゃる。
外出からお帰りになると、まっさきにお出迎えして、親しくお話をなさって、お胸の中に入って、少しも嫌がったり恥ずかしいとは思っていない。
そうしたことでは、ひどくかわいらしい態度でなのあった。
【夕暮などばかりぞ】- 係助詞「ぞ」は「うち泣きなどしたまふ」に係るが、接続助詞「ど」が下続したために、結びの流れとなっている。
【宮をば】- 父兵部卿宮をさす。
【この後の親を】- 源氏をさす。親代り、という立場である。
【さるかたに】- そうした関係の意。『集成』は「実際の夫婦ではないが、という含み」と解し、『古典セレクション』は「無邪気な遊び相手という点で。親子という方面からみると、とする説もある」と注す。
【いみじう】- 『集成』『古典セレクション』は諸本に従って「いみじく」と校訂。『新大系』は底本のまま。
自分の娘などでも、これほどの年になったら、気安く振る舞ったり、一緒に寝起きなどは、とてもできないものだろうに、この人は、とても風変わりな大切な娘であると、お思いのようである。
【むつかしき筋】- 夫婦関係が長くなりうっとうしく思われる関係。
【女など】- 自分の実の娘でもの意。前に「後の親」とあったのを受ける。
【心やすく】- 大島本は、「心やすく」以下の改丁から書体が藤原俊成ふうのものに変わる。親本の書体を参考に書きとどめたものか、とされる。
【これは】- 源氏からみた紫の上。
【思ほいためり】- 御物本は「おほいたり」。横山本、榊原家本、池田本、三条西家本は書陵部本は「おほいためり」。肖柏本は大島本と同文。河内本は「おほしためり」とある。『集成』『古典セレクション』は「おぼいためり」と本文を改める。『新大系』は底本のまま。主語は源氏。「ためり」の「た」は完了の助動詞「たる」連体形の「る」が撥音便化しさらに無表記形。推量の助動詞「めり」終止形、視界内推量。語り手が源氏と紫の上の側近くで見て推測しているニュアンスである。
| 底本 | 大島本 |
| 校訂 | Last updated 9/11/2010(ver.2-2) 渋谷栄一校訂(C) オリジナル 修正版 比較 |
| ローマ字版 | Last updated 3/28/2009 (ver.2-2) Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C) オリジナル 修正版 比較 |
| ルビ抽出 (ローマ字版から) |
Powered by 再編集プログラム v4.05 ひらがな版 ルビ抽出 |
| 挿絵 (ローマ字版から) |
'Eiri Genji Monogatari' (1650 1st edition) |
| Latest Updated 4/26/2001 渋谷栄一訳(C)(ver.1-2-2) オリジナル 修正版 比較 |
| 現代語訳 | 与謝野晶子 |
| 電子化 | 上田英代(古典総合研究所) |
| 底本 | 角川文庫 全訳源氏物語 |
| 渋谷栄一訳 との突合せ |
宮脇文経 2003年8月14日 |
| Last updated 3/28/2009(ver.2-2) 渋谷栄一注釈(C) オリジナル 修正版 比較 |